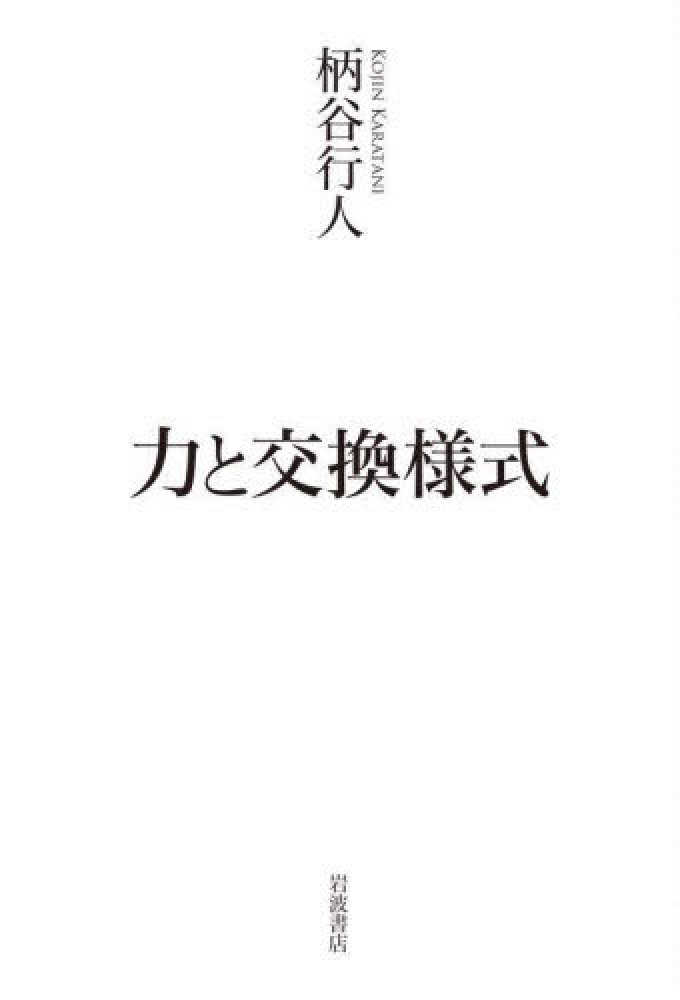ナミビアのブッシュマン(サン人)
【43】 ジーグムント・フロイト
――文化と「攻撃性」
『フロイトは超自我に、〔…〕「おびえて尻込みしている自我に、ユーモアによって優しい慰めの言葉をかける」ものを見いだしている。超自我は、自我を抑えるというより、むしろ自我の自律性を支援するものである。その意味で、〔…〕超自我は内部から来るものだと言ってよい。
とはいえ、それは自我にとって、あたかも外から来たかのように、強迫的に到来する。
さらに、超自我は、個人に限定されるものではない。実際、フロイトはこう述べている。《共同体もまたひとつの超自我を形成し、その影響下に文化が発展すると断じてよい》〔『文化の中の居心地悪さ』 in:『フロイト全集 20』,p.157.〕。』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,pp.91-92.
前回までに見たフロイトの叙述では、「超自我」とは、一人の人間の「自我」の一部であり、人間の「前意識」の中にあるものでした。ところが、ここで柄谷氏は突然、「超自我は個人に限定されるものではない」と言い出し、複数の人間の集団である「共同体もまた、ひとつの超自我を形成」すると述べるフロイトの片句を引用しています。フロイトがここで言う「文化」もまた、個人の特性や行為ではなく、集団的な現象です。個人の「超自我」と「共同体」(社会)ないし「文化」との関係について、フロイトは、どう考えているのでしょうか? 両者の関係は、柄谷氏が言うほどに単純なものではないと思われます。柄谷氏が引用している文章の前後を見てみましょう:
『個人の発達過程では、幸福の満足を見いだそうという快原理〔快感原則――ギトン註〕のプログラムが主たる目標として堅持されており、〔…〕個人の発達においては、〔…〕幸福を追求する利己的努力に主眼が置かれる〔…〕
これが〔ギトン註――社会の〕文化過程の場合となると話が違ってくる。ここでは、個々人からひとつの統一体を作り出すという目標が断然主要な案件であり、幸福実現という目標は〔…〕影が薄くなっている。ひとつの大きな人間共同体を創出するには、いちいち個人の幸福を顧みる必要なぞないと思われるほどだ。〔…〕個人の発達過程も、それが共同体との連結を目標とする以上、やはり文化過程と符牒を合わせなくてはならない。
〔…〕こうして、個人的な幸福を求める努力と、人間相互の連結をめざす努力という2つの努力も、一人ひとりの個人の中で互いに闘わなければならず、個人の発達と〔ギトン註――社会の〕文化の発展という両過程は互いに敵として遭遇し、それぞれ相手の領土を奪い合わねばならない。もっとも、個人と社会とのあいだでくりひろげられる・この闘いは、エロースとタヒという2つの根源的欲動のあいだの〔…〕対立から〔…〕派生したのではなく、リビードの家計のやりくりの中での確執を意味し、自我とその対象とのあいだのリビードの配分をめぐる争いに喩えられるべきものである。そして、〔…〕個人においては、また望むらくは文化の将来においても、いつかはこれが最終的な和解に達するのが不可能なわけではない。』
フロイト,嶺秀樹・他訳「文化の中の居心地悪さ」, in:『フロイト全集』20,2011,岩波書店,pp.156-157.
フロイト博物館、ロンドン。
ここまでの行論は問題ないと思います。フロイトが前提する二元論は、個人の心の中で起こることは、「快感原則」ないし「エロス,リビドー,生/性の欲動」と、「タヒの欲動/本能」及びそこから派生する「攻撃性/攻撃欲動」という2大原則に支配されているというものです。しかし、個人と集団との関係において鬩ぎ合う2つの動向:個人の自己保存ないし幸福実現と、複数個人の連結による集団的文化の結成・維持とは、どちらも「快感原則」に基くものであり、個人優位か、集団優位かをめぐる「リビドーの配分をめぐる争い」にほかなりません。「快感原則」にもとづく派生的「力」のあいだで、集団により多くのエネルギーを配分するか、個人により多く配分するかをめぐって、争いが起きているというのです。
したがって、フロイトの考えでは、この・個人か集団(文化)か、をめぐる争いは、解決不可能なものではなく、いつかは「最終的な和解」に達することも十分に期待できるというのです。(たとえば、「最大多数の最大幸福」は、その「和解」方策の一提案だったと言えます。)
ところが、そこに、他方の原理である「タヒの欲動/本能」から派生する「攻撃性/攻撃欲動」、およびその内向化である「超自我」が介入してくると、事態はより複雑になります。(ちなみに、前回のフロイト引用から解るように、「超自我」は一方的に「タヒの欲動」から派生したわけではなく、そこにはエロス:「生/性の欲動」もまた流れ込んでいます。自我の自律性を支援しようとする「ユーモア」の高貴さ・優しさは、まさに「超自我」のこの面に基くものです。)
『文化過程と個人の発達行程との類似には、さらにもうひとつ重要な1点が付け加わる。共同体もまたひとつの超自我を形成し、その影響下に文化が発展すると断じてよい。〔…〕
ある文化期の超自我は、個々人の超自我と似た起源をもっている。それは、偉大な指導者たちが残していった印象に根ざしている。〔…〕ちょうどあの原父〔トーテミズム起源説⇒:(11)【35】――ギトン註〕が無残に刹害され、ずっと後になってようやく神格に上りつめたのと同じように、これらの人物たちも〔…〕往々、他の者らから嘲笑され、あるいは虐待され、時には残酷なしかたで亡き者とされることすらあった。そうした運命の結節を示す例のなかでも、われわれを最も捉えて放さないのが、ほかならぬイエス・キリストという人物である。〔…〕
〔ギトン註――文化の超自我と個人の超自我の〕もうひとつの符合は、文化の超自我も個人の超自我とまったく同じように厳格な理想要求を掲げており、この要求に従わないと「良心の不安」によって罰せられるという点にある。』個々人の超自我の無意識の『要求を意識的な認識に引き上げてみると、それらが各時代の文化の超自我が指図するところと一致していることが分かる。集団の文化的発展の過程と、個人の固有の発達過程という2つの経路は、決まってこの地点で互いに絡み合うのである。〔…〕
文化の超自我も従来、固有の理想を形成してきたところであり、また今も固有の要求を掲げている。これらの要求のうち、人間相互の関係にかかわるものが集大成されたのが、倫理である。〔…〕つまり、倫理とは、ひとつの治療的な試み、これまで他の文化的作業によっては達成できなかったあることを、超自我の命令によって達成しようと努めるものだと捉えることができる。ここで問われているのが、文化の最大の障碍、すなわち人間が素質として生まれ持った互いに攻撃しあう傾向を、どのようにして取り除くか、ということであるのをわれわれはすでに知っている。文化的超自我の発した命令のうちでどうやら最も新しいものとおぼしき、「汝の隣人を汝自身と同じように愛せ」という命令が、とりわけわれわれの関心をひくのも、まさにこのためにほかならない。』
フロイト,嶺秀樹・他訳「文化の中の居心地悪さ」, in:『フロイト全集』20,2011,岩波書店,pp.157-159.
パブロ・ピカソ『サビニの女たちの掠奪』 © Wikimedia
人間の心に、個人の他の個人に対する「攻撃性」ないし「攻撃欲動」が発現する(動物の時からすでにあったのですが)ことによって、人間の集団形成の過程は、実際にはもっと複雑になります。すなわちフロイトの言い方でいうと、「文化の最大の障碍」とは、「人間が‥互いに攻撃しあう傾向」であって、これを「どのようにして取り除くか」が、「文化の超自我」に課せられた課題であった、というのです。このような「文化の超自我」の発生起源についてフロイトは明言していませんが、個人の「攻撃性」のひとつの折り返しであった、つまり、個人の「超自我」の発生と並行するものであった、ということは容易に想像できます。
フロイトの↑上の議論をまとめますと:
① 個人における超自我の起源がエディプス・コンプレクス(親の権威のアンビヴァレントな内面化)にあるのと同様に、文化共同体における超自我の起源は、イエス・キリストのような先駆者を迫害した罪責感・による先駆者権威の神格化にある。② 個人の超自我と同様に、文化の超自我もまた個人(自我)に対して、その能力を超えた過大な理想的要求を押しつける。
この2点になるでしょう。
個々ばらばらな人間たちが互いに連結しあって「ひとつの統一体(文化集団)を作り出す目標」とは、もとから言えば、個人のエロス(快感原則)が追求する方向のひとつにほかなりません。その努力を邪魔するのが、他方の根本原理である「タヒの欲動」に基づく個人相互間の攻撃性です。この関係を図示すると、つぎのようになります:
このように、個人⇔社会,快感原則⇔タヒの欲動 の関係は複雑になっています。そして、「攻撃性」の内向的「折り返し」である「超自我」は、個人にあっては「自我」の自律性を支持し、社会・文化にあっては、個人相互間の「攻撃性」を抑制し和らげるものとして働くのです。後者の働きは、集団が自らの内発的な力によって分解を防ぎ凝集性を高めるわけですから、集団の自律性と言ってもよいと思います。
なお、フロイトがここで「共同体」と呼んでいるのは、柄谷氏の用語で言えば「国家=資本=ネーション」のことです。つまり、仮想的に共同社会と見なされた近代の “全体社会” のことです。「むら」共同体や原始共同社会のようなものではありません。
ここで、柄谷氏のほうの叙述に眼を戻すと、やや不可解な表現に出くわします:
『すなわち、超自我は自我を超えているだけではなく、共同体をも超えている。それが共同体に新たな倫理をもたらす。フロイトは、次のように言う。《倫理とは、ひとつの治療的な試み、これまで他の文化的作業によっては達成できなかったあることを、超自我の命令によって達成しようと努めるものだと捉えることができる》〔『文化の中の居心地悪さ』 in:『フロイト全集 20』,pp.158-159.〕』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,p.92.
柄谷氏のこの叙述は、フロイトの引用文ともども謎めいています。「超自我は‥共同体をも超えている」という表現は、まったく意味不明です。フロイトの該当箇所は、↑前記引用の最後の段落にあります。が、そこでは、何ら謎めいたことを言っていたわけではありません。その内容は、↑前掲の図示に尽きます。柄谷氏の書き方に釣られて神秘の世界に踏みこまないように気をつけましょう。
【44】 ジーグムント・フロイト
――キリスト教倫理と共産主義
「超自我」の機能、とりわけ社会・文化の中で果たす倫理的役割に関するフロイトの考察は続きます。そこでは、個人の超自我(倫理)と社会・文化の超自我(倫理)とは、しばしば同じ理想的方向を向いて個人の自我を規制(攻撃)します。これを一面から見ると、個人の超自我は、社会倫理(ないし宗教)を内面化した他律的なものであるように見えます(これが「前期フロイト」)。しかし本質は、そうではありません。個人の「超自我」もまた、個人の無意識的本能「エス」を背景に負った自律的なものにほかならないのです。
『狼森と笊森、盗森』ミキハウス刊。片山健・画。
『超自我は、もっぱら厳しい命令や禁止を出すだけで、それに服従しようにも、エスの欲動の強さや周囲の現実のさまざまな困難など、さまざまな抵抗があるのを十分に考慮せず、自我の幸福についてはおよそ頓着しない。それゆえわれわれも、治療の立場から、しばしば超自我〔…〕の要求を低下させるように努めている。〔…〕文化の超自我も、人間の心的資質の事実を十分に顧慮しておらず、命令を出すものの、人間はその命令に服従することが可能かどうかは問わない。むしろ、人間の自我には、〔…〕自らのエスを無制限に支配する権限がある、と決めてかかっている。〔…〕「汝の隣人を汝自身と同じように愛せ」という命令は、人間の攻撃性を撃退する最強の防衛であるとともに、文化の超自我がいかに人の心理というものを理解しないかを示すみごとな例である。この命令では実行しようがない。愛をこれほど気前よく大盤振る舞いすれば、その価値が下がるだけで、これでは人の苦境を救えない。現代の文化の中でそのような言いつけを守れば、それを無視する者に比べて損をするだけだ。攻撃性』にたいして防禦『することが、この攻撃性と同じように人を不幸にしうるとなると、攻撃性が文化に及ぼす障害のなんと大きいことか。〔ギトン註――「隣人愛」のような〕いわゆる自然な倫理が提供してくれるものといえば、せいぜい、おまえは自分を他人より善い人間であると見なしてよい、というナルシシズム的な満足くらいのものである。〔…〕
所有にたいする人間の関係を現実に変革することができれば、どのような倫理の命令よりも害悪の軽減に役立つであろうことは、私にとっても疑いようがない〔…〕。ただ、せっかくのこうした洞察も、社会主義者たちの場合、人間本性を見誤る近頃の理想主義的な妄念のせいで霞がかかり、実行に移すだけの価値をもたなくなっている。』
嶺秀樹・他訳「文化の中の居心地悪さ」, in:『フロイト全集』,pp.159-160.
つまりフロイトは、「汝の隣人を愛せ」「敵を愛せ」のようなキリスト教的宗教倫理に対しては、たいへんに厳しい批判を向けています。それよりも、「所有秩序を変革せよ」と主張する共産主義者のほうがまだしも現実的だというのです。これはたいへんに興味深い指摘です。フロイトは、共産主義にも理解を示し、「キリスト教よりは、ましだ」と言っていたのです。
ただし、現実の社会主義(当時のロシア革命とレーニン時代のソ連)に対しては否定的です。なぜなら、彼らのイデオロギーは「人間本性を見誤る理想主義的な妄念」であって、その点ではキリスト教倫理と何ら異ならないからです。
「所有の変革」ないし「私有財産の廃止」という提案それ自体は良い。それは、人間社会の矛盾を解決する一助(あくまでも一助)になるからだ。しかし、けっきょく社会主義イデオロギーはダメだ。なぜならそれは科学ではなく “宗教” だからだ。フロイトの社会主義観をかんたんに言い換えれば、そうなるでしょう。
『共産主義者たちは悪から脱却する道を見つけたと信じている。いわく、人間はひとえに善であり、隣人を善く思ってもいるのだが、私的所有の制度が人間の本性を堕落させてしまった。〔…〕私有財産を廃止しあらゆる財を共有化して、万人がその享受にあずかることができるようにするなら、人間相互の悪意や敵意は消え去るだろう。すべての欲求が充足されているので、他人を自分の敵とみなす理由がなくなるし、必要な労働には万人がすすんで従事することになる……。
私は共産主義の体系を経済の面から批判するつもりはない〔…〕しかし、この体系の心理学的前提が何の裏付けもない錯覚であるのを見極めることはできる。私有財産を廃止することで、人間の攻撃欲から道具のひとつが取り上げられることにはなる。これが〔ギトン註――攻撃欲の〕強力な武器であるのはまちがいないが、最強の武器でないのもまたまちがいない。攻撃性は、権力や影響力に差があることを、自らの意図に悪用するのだが、〔ギトン註――私有財産を廃止しても、〕この力の差に関しては何ひとつ変わらないし、攻撃性の本質にも変化はない。攻撃性は、財産所有によって創り出されたものではなく、財産所有がまだはなはだ乏しい原始時代にあってもほとんど無制限に荒れ狂っていた。〔…〕
物的な財にたいする個人の占有権を撤廃したところで、性的関係に対する特権は残り、他の点では平等となった人間たちのあいだに烈しい妬みと猛烈な敵意を生む源泉となるにちがいない。〔…〕この特権も廃棄』するには、『文化発現の原点である家族を廃止』して『性生活を全面的に解放する』ほかはないが、そうなると人類はゼロに戻って文化の発展をやり直すことになろう。その場合、文化の発展が『どのような新たな道をたどる〔…〕かは予測できない』が、その場合でも、『人間の不壊の特質というべき攻撃性が、文化の行く』ところ・どこまでも永遠に『付き従ってゆく〔…〕ことだけは、今から見当がつく。』
嶺秀樹・他訳「文化の中の居心地悪さ」, in:『フロイト全集』,pp.124-125.
フロイトの・この先駆的預言との関係で、現代の諸思想、とりわけ柄谷行人の「交換様式」が、フロイトの提起した問題を解決しうるものなのかどうか、慎重に吟味される必要があります。
フロイトの「心理学」を歴史的社会の中で見た場合、彼は決して「心の問題」だけを論じたのではない。安っぽい文明論を繰り広げたのでもなかった。あらゆる社会変革思想ともユートピア主義とも拮抗しうるだけのものを構築している。われわれは、その問いかけに答えなければならない、ということが、お解りでしょうか?
おそらくカギになるのは、「攻撃性は、財産所有によって創り出されたものではなく、財産所有がまだはなはだ乏しい原始時代にあってもほとんど無制限に荒れ狂っていた。」という部分です。ここは、突破口となりえます。
というのは、フロイトの時代には、まだ人類の原始社会の実像が、今日ほど解明されてはいなかったからです。宗教も国家もない原始時代には、人間の「攻撃性が‥荒れ狂っていた」というのが、当時の常識的な原始社会像だったと言えます。それは、ホッブズ以来、マルクスもダーウィンもスペンサーも、あらゆる社会思想にたいしてその前提として通用していました。
しかし、フロイトから現在までの間に、人類の先史社会に関する研究は、考古学・人類学の両面で大いに進展し、原始社会像は塗り替えられてきました。原始社会とは、何ものにも制約されない動物的野蛮人たちが野放図な弱肉強食的争いを繰り広げている社会ではなく、むしろ一人ひとりは弱小な人間たちが、相互の厳しい規制によって結束し、圧倒的な自然の脅威に打ち克って生き延びようとした社会だった、そう言えるのではないかと思います。
この先史に関するパラダイム転換をどの程度取り入れているのか?……によって、マルクス・フロイト以後の社会思想は真価を問われると思います。
柄谷行人氏の「交換様式」は、はたしてどうか? 私たちは慎重に見定めてゆく必要があります。
ジョゼフ=ノエル・シルヴェストル『ローマの劫掠』 © Wikimedia
【45】 「国家の出現を不可能にする?」兄弟同盟
『前記フロイトでは、父刹し(原父刹し)が最初に置かれる。それは、交換様式でいえばB〔「保護と服従」――ギトン註〕から出発して考えることに等しい。』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,p.386.
『後期フロイトの視点に立って見れば、トーテミズムの強制力は、外から来るのではなく、内にある「タヒの欲動」が攻撃性として外に向かったのちに、内に向かって戻ってくるときに成立する。したがって、原父が先行しなくても、超自我、あるいは厳しい自律が可能になる。のみならず、重要なのは、そのことが、彼らの間に原父的な存在の発生いいかえれば国家の出現を不可能にする、ということである。すなわち、トーテミズム=「兄弟同盟」が、国家の出現を不可能にするのだ。
では、トーテミズム=兄弟同盟をもたらす「力」は、何であり、どこから来るのか? 後期フロイトは、それを「無意識」に見いだした。〔…〕後期フロイトが見出した反復強迫的な「力」は、まさに「無意識」から来るといってよい。そしてそれが、いわば霊的な力として働く、と。』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.92-93.
原始的な集団の「自律」を可能にする「超自我」(「兄弟同盟」「トーテミズム」「氏族社会」)の出現が「国家の出現」を妨げ、「不可能にする」と柄谷氏は言うのです。論理の飛躍が大きすぎて、容易に賛同できる見解ではないし、柄谷氏が差しはさむ神秘主義的な表現も気になります。科学者として誠実なフロイトは、「いわば霊的な力として働く」などという言い方はしていません。
『原遊動民が定住した後の社会に生じた事柄を、後期フロイトの観点から説明し直す』と、『彼は「タヒの欲動」を、単細胞の結合からなる有機体から、無機質であった状態に戻ろうとする衝動であると考えた。それが先ず、対他的に攻撃欲動として現れる。
単細胞の要素的な有機体が、多細胞の生物に結合する結果、単細胞のタヒの本能を中和し、破壊的興奮を、特別な器官を媒介にして外界に向け換えることができたのであろう。この器官は筋肉系統であり、タヒの本能は――おそらくただその一部分がであろうが――外界あるいは他の生物を破壊する衝動として現れることになったようにみえる。〔フロイト,小此木啓吾・訳「自我とエス」, in:『フロイト著作集 6』,p.300.〕
このような比喩は、遊動バンドが定住した後にどう変化したかを見るのに役立つ。』もともと、『遊動的な狩猟採集民たちは、社会的な葛藤や縛りをもたなかった。したがって、特に利己的なわけでも利他的なわけでもなかった。
狩猟に出かけるボツワナのブッシュマン(サン人)
しかし、定住した後、彼らは未曽有の危機に出会った。一口で言えば、定住が「有機的」な状態をもたらしたのである。無機質の状態に戻ろうとするタヒの欲動が現れたのは、そのときである。それは先ず、他に向けられる攻撃欲動として奔出したが、さらに、それを抑えて他者への譲渡=贈与を迫る「反復強迫」が現れた。そして、それは「霊」の命令として出現した。それが、後期フロイトが「超自我」と呼んだものである。』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.93-94.
柄谷氏は、定住以前の人類の状態が「無機的」(無生物的)だと言っていますが、たとえ比喩にすぎないとしても、どの程度的確な比喩でありうるのか、疑問なしとしません。もちろんフロイトは、そのようなことはひとことも言っていません。
おそらく柄谷氏は、構成員が互いにさまざまな関係を結んで有機的に機能しあっている定住後の社会を、「有機的」というイメージで把え、それに対して、定住以前の人類の状態を「無機的」と言っているのでしょう。
しかし、「定住」以前の人類が、ばらばらで、相互に一切のつながりをもたない人たちだった、という想定には、何の根拠もありません。たとえば、原始狩猟社会(日本でいえば、旧石器時代でも初期の縄文時代でも)には、集団的なキャンプの遺跡があります。原始狩猟人は完全にバラバラに「遊動」していたわけではなく、一次的なキャンプのような集落を形成することはあったのです。離合集散はあるにしろ、原始狩猟民は、集まって集団で猟をしたり、助け合って越冬などの生活の困難を乗り切ることはあったはずです。
しかも、集落の形状には「環状」「線状」などがあり、住民の間に一定の秩序のあったことをうかがわせます。「環状」集落の中央は、墓地になっている場合もあり、何か宗教的な意味があったかもしれません。そもそも、そのような居住地がなければ、遺跡など発掘しようがないのです。
人類より以前を考えてみても、たとえば動物にはナワバリというものがあります。動物の「弱肉強食」は、異なる種のあいだで起きることであって、同種の動物のあいだの「共食い」は稀ですし、同種の動物同士は、何らかの(本能的?)規制を及ぼしあって生きています。動物でさえそうなのですから、人類は誕生の初めから、無制限の「自由」のなかで生きていたわけではない。そう考えなければ辻褄が合いません。
このように考えてみると、柄谷氏のいう原始の「無機的」状態には大きな疑問符が付く以上、「定住」後に「タヒの欲動」が「現れた」(復活した?)とか、その時に「タヒの欲動」→「攻撃性」→「超自我」への「折り返し」が起きたなどという想定は、とうてい受け入れられないでしょう。フロイトの想定では、これらが起きたのは、もっとずっと前の氷河期人類(ネアンデルタール人以前)の段階においてでした。柄谷氏が「反復強迫」現象に注目する点は、キルケゴール、ブロッホとの関係でも考慮に値しますが、それをここに結び付けるのは無理な付会というものです。
まして「霊の命令」うんぬんは、いただけない神秘主義です。
『マルセル・モースは〔…〕氏族社会における交換〔…〕は、人間がやっているように見えるが、そうではない』と述べた。『《そこでは人間は、結局のところ霊の代理として行動しているにすぎない。それというのも、こうした交換・契約は、……人や物に程度の差はあれ結びついている聖なる存在者たち・をも巻き込むからなのだ》〔『贈与論』岩波文庫〕
環状集落・再現図(イラスト:田畑修) 埼玉県・行司免遺跡、縄文中期
ここで簡単にまとめておこう。人類社会の初期は、遊動民の社会であった。それは、フロイトの言い方でいえば、原遊動民の「無機質」の状態である。私はそれを原遊動性(U)と呼ぶことにする。
だが、人類が定住したのち、さまざまな葛藤と対立が生じた。それを解消したのが、交換様式Aである。それは、フロイトの言葉でいえば、「忘却されたものの回帰」として生じた。それは反復強迫的である。ただし、「忘却されたもの」とは、〔…〕原遊動性(U)である。それは定住後に失われたが、消滅したのではない。それは、贈与交換を命じる霊として現れた。それによって、原父のようなものの出現をけっして許さないような兄弟同盟(氏族社会)が作り出されたのである。
その意味で、氏族社会やその拡大としての首長制社会は、たんに禁忌によって縛られた抑圧的な社会なのではない。そこにはいわば、ユーモアに見られるような高貴な自律性もまた存するというべきである。』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,pp.95-96.
「高貴な自律性」というのも、イメージとしてはわかりますが、「なんとなく」のイメージで非論理を埋めることはできません。ここで柄谷氏が持ち出しているのは、首長制社会における首長の地位についてのレヴィ=ストロースの意見です。「首長制社会では、首長が一定の権力を持つ。しかし、人々は首長になりたがらない。」として、レヴィ=ストロースが『悲しき熱帯』で述べているエピソードが紹介されています。モンテーニュの時代にも、レヴィ=ストロースの 20世紀にも、ブラジル先住民にとって「首長の特権」とは、「戦いのとき先頭に立って進むこと」であり、そんな地位には誰も就きたくないので、首長の選定はなかなか決まらない。選定は何度もやり直しになる、というのです。(pp.96-97.)
このエピソード自体は、古代史では常識と言ってよい「首長制」の基本性格を表わすものでしょう。「首長制」またそれ以前の「氏族制社会」は、「保護と服従」すなわち「交換様式B」を原理とする「国家」型社会とは異なること、「首長」とは、いわば「同輩中の犠牲者」にすぎないことを示している――のは、理解できます。
しかし、「戦いのとき先頭に立って進む」任務を受け入れて「首長」になる者もいるという事実を、このエピソードは説明してくれません。誰も首長になる者がいなければ、首長制は維持できなくなり、それこそ「国家」の一部として併呑されてしまう以外に生きる道は無くなります。「国家の成立を不可能にする」どころではないのです。
おそらく、「首長制」社会が健全に機能していた時代には、「首長」に就任した者は「神」となるから、矢が当たらなくなる、というような信仰があったのでしょう。ヨーロッパ人には理解できなくとも、『古事記』の天皇伝説を負っている私たちには理解可能なことです。そして、20世紀ともなると、ブラジルの先住民も、このような「首長」の神力を信じられなくなってきたので、「首長」のなり手がいなくなった、ということではないでしょうか?
フロイトを「交換様式論」につなぐ柄谷氏の議論――定住による「原遊動性(U)」の消滅とその「反復回帰」の理論――は、柄谷氏の「社会主義の科学」のカナメの部分です。ので、次回も継続してこれを扱い、一見神秘主義的な氏の論述の中から、なにか “救い出せる” ものがないか、慎重に見極めていきたいと思います。
よかったらギトンのブログへ⇒:
ギトンのあ~いえばこーゆー記
こちらはひみつの一次創作⇒:
ギトンの秘密部屋!