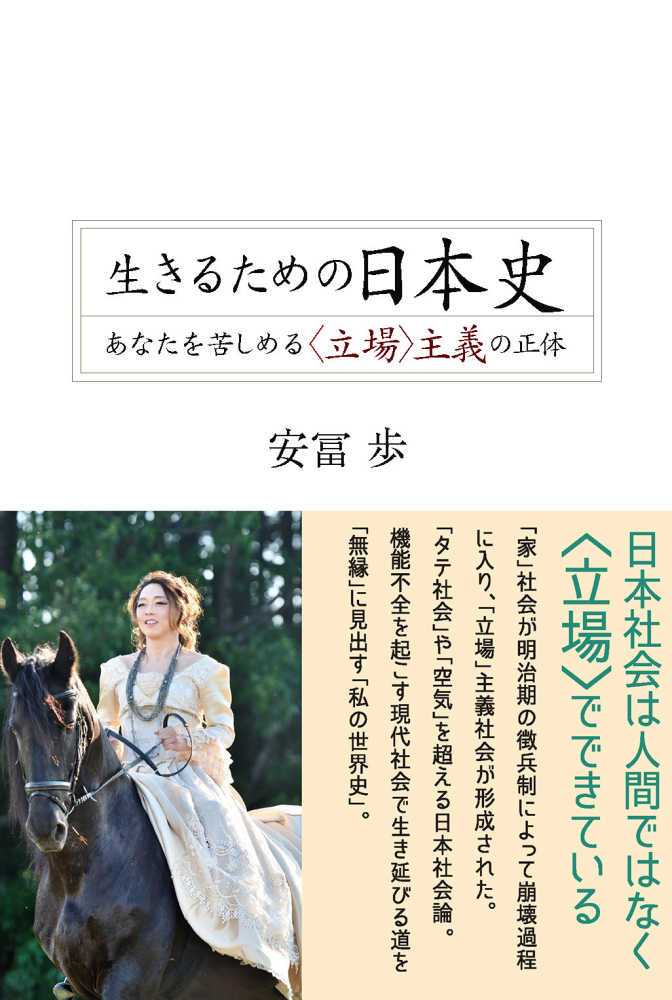ロボット工場の組み立てライン 日産自動車栃木工場.
【31】黄金時代の「立場主義」
『今日の日本社会にとって最大の見えざる問題は、立場主義社会そのものが崩壊をしはじめているということです。なぜなら、立場主義がその経済的基盤を失っているからです。』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, p.191.
「立場主義の経済的基盤」とは、何でしょうか? それを見るには、立場主義の「黄金時代」――高度経済成長がつづいていた 1960-70年代に遡る必要があります。
『私は、この立場主義社会のシステムこそが、〔…〕日本の経済活動に大いに役立ったのではないか、と考えています。〔…〕
立場システムは、多くの人が一糸乱れぬ行動をとるべき時に、大いに力を発揮します。細々(こまごま)としたそれぞれの「立場」に「役」が割り振られ、その担当者は「立場」を守るために死に物狂いでその「役」を果たそうとするからです。
ですから、巨大で複雑な機械を、多くの人間からなる集団が、一糸乱れずに操作をする必要があった「近代」は、立場システムを持つ日本人と日本社会にジャストフィットしていたのです。』
安冨歩『ジャパン・イズ・バック』,2014,明石書店, p.194.
「近代」のなかでも、「立場」がもっとも威力を発揮したのは、経済成長のスピードが最大だった戦後「高度成長」の時期でした。
戦時中の「総力戦」遂行によって、「立場主義」は日本の社会に広がり、「進め一億火の玉だ!」のスローガンのもとで日本人の心身に刻まれました。そして、いちど刻み込まれたものは、敗戦によっても失われることはなく、戦後の復興過程でその特質を発現し、成長のスピードを最大化させたのです。
高度経済成長の当時から、すでに、大企業の工場では機械化が進んでいました。化学工場では、多数のさまざまな機械装置が複雑なパイプでつながれ、機械群の一方から原料を入れれば、装置から装置へと中間生成物が送られ、種々の化学反応を経て自動的に製品ができあがる仕組みになっていました。しかし、だからと言って人手がかからないわけではありません。むしろ、機械だけで生産する仕組みになっているからこそ、熟練した多くの人手による調整の手間を必要としたのです。
当時の機械は、生成物の出来ぐあいを見て、自分で運転を調整するような仕組み――つまり「フィードバック」の機構を備えていませんでした。「フィードバック」ができるためには、コンピュータが必要なのです。当時はまだ、工場に導入できるほどコンピュータ技術が進歩してはいなかったのです。「フィードバック」調整は、人間がしてやる必要がありました。たとえて言えば、一つ一つの機械に係の人間が張り付いて運転手の役目をする必要がありました。しかも、それら多数の機械の・おおぜいの運転手の働きは、工場全体として統率のとれたものでなければなりません。個々の運転手が自分の好きなように運転したのでは、工場全体として生産を行なうことはできないのです。
このような、自己制御能力のない機械が立ち並んだ工場で、「立場主義」が組織的な力を十二分に発揮することは明らかでしょう。
あるいは、自動車の組み立て工場を考えてみましょう。当時の組み立て工場は、中央に長いベルトコンベアが延びていて、その上を組み立てかけの自動車が流れていく仕組みでした。ところどころに機械はあっても、基本的には組み立ては手作業です。コンベアの両側に並んだ作業員が、コンベアの速さに合わせて、溶接機や各種工具を使って、自動車のボディーを組み立て、エンジンをはめ込み、装着してゆくのです。これまた、一糸乱れぬ統率のもとに、それぞれが自分の役目を果たしてゆく「立場主義」の能力が要求される作業です。
工場の作業だけではなく、企業全体が、このような「立場」の原理で組織され、統率されていました。たとえば、営業活動なども、同じ原理で、個々の営業員を機械のように見なして評定しつつ行われたがゆえに、日本の企業は効率性が高いという評価を(当時は)受けたのです。
しかも、「立場主義」はある意味で家族主義です。効率一方の冷たい合理性ではなく、一方的なトップダウンでもない。従業員の情緒的な忠誠心と、トップによる家族的配慮が、人間関係を柔軟に調整しているのです。それが、「立場主義」をベースにした日本の企業であり、「日本型経営」であったのです。
『この複雑な工程は、すべての機械が動き続けなければならない、しかも同じタイミングで動かなければいけない。そのためには機械に張り付いている人間が、お互いに心をひとつにして必死に、自分の命を顧みず、ちゃんと動かしてくれないといけないわけです。
たくさんの人間が心を一つにして働かないといけない、というようなことを必要とする、中途半端な機械群みたいなものが経済の中心にあった時代、日本の立場主義者たちは世界で誰も真似のできないパーフォーマンスを見せました。なぜなら、誰も自分の都合でサボったりせず、立場を守って討ち死にする覚悟で、必死に働いたからです。そうして生産された製品がどんどん世界に輸出されて、日本は経済大国になったのです。この時に私たちの心の隅々まで、立場主義は素晴らしい、役を果たして立場さえ守っていれば給料は倍々に増える、という信念が埋めこまれていったわけです。』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, pp.204-205.
「立場主義」の一方の雄――大企業の現場での「黄金時代」の状況は、このようでした。他方の雄――官僚組織は、どうだったでしょうか?
『〔ギトン註――立場主義の〕官僚機構には本質的にブレーキが存在しません。
「立場上やらねばならぬことを猛烈な勢いでこなす」
ことこそが優秀な官僚の証しだからです。』
安冨歩『ジャパン・イズ・バック』,2014,明石書店, pp.78-79.
自分の仕事に疑問を持つなどということは決して許されないのが、日本の「立場主義」官僚制なのです。いちど全体が、一つの方向へ転がりはじめたら、個々の官僚は、地位に関わりなくそれを止める力はないし、自分だけが動きに逆らうこともできません。
『この資質が国民の代弁者である政治家によってうまくコントロールされているうちは、その手足となって国家の日常の運営が滞りなくなされるわけですが、ひとたび歯車が狂いだすと、〔…〕狂った歯車を動かし続けるしかなくなってしまいます。
暴走する性質を持つ立場主義者〔つまり日本の官僚――ギトン註〕は、この自分たちの立場が脅(おびや)かされること、つまりゲームのルールが変わることを極端に嫌います。
官僚機構の力を削ぎ、〔…〕政治家、あるいは〔…〕地方自治体へ権力を移譲しようとした、小沢一郎が、検察にマスコミ、その他ありとあらゆる手段を用いて徹底的に叩かれた裏には、こういう力学があるのです。〔…〕
太平洋戦争のあと、生き残った高級軍人・官僚・政治家の多くが口を揃えて言った言葉は、
「いまさら止められなかった」
です。
しかも太平洋戦争を境に、官僚機構はさらに良くない進化を遂げました。〔…〕今度は官僚出身者が〔ギトン註――国家〕財政と財閥との間に入って(天下りして)、そこから利権を分配する、というシステムの発生です。〔…〕
この結果、「官僚」という権力は細分化され、おのおのの役人は一つ二つの自分のポスト、年間数百万円数千万円という単位の「仕事」を本当に一生懸命にこなす。ただそれだけをひたすらにやる、という状態になりました。誰も全体像が見えておらず、それを調整する人もいません。
これを私は「権力の微分化」と呼んでいますが、こうなると必然的に暴走するしかないのです。』
安冨歩『ジャパン・イズ・バック』,2014,明石書店, pp.79-81.
【32】コンピュータの登場、「立場主義」の崩壊
1960年代までの機械は、人間がそばにいて「運転」や「調整」をしてやってはじめて、まともに「作動」するものでした。
『この・作動だけする機械は中途半端なのです。〔…〕機械に人間がくっついて、結果を見て、調整するということをやらねばならなかった。』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, pp.196-197.
バートランド・ラッセルの弟子でサイバネティックスの開拓者ノーバート・ウィーナー〔1895-1964〕は、機械というものは、「作動」の結果を自分で「観察」し、それに基いて作動のしかたを「修正」することができてはじめて、完結した「機械」といえるのだ、と述べています。事前にすべてを計算して設計し終えて、あとは設計図通りに機械にやらせる、などということは、じっさいには不可能です。“完全に計画した通りの出力” などということはありえません。(3)で見たように、“入力” に紛れ込む微小な不確定性を取り除くことは不可能であり、それは「カオス」によって増幅され、“出力” を必ず不安定にします。
完結した「機械」システムは、出力の一部を入力部に戻して、そこで「観察」と「修正」を行なう「フィードバック」の機構を備えていなければなりません。“予め計画しておいて、あとは実行するだけ” というのは、「はじめに神は天と地を創った」、その後のすべては神の計画通りに進行した、――というキリスト教の間違った考え方です。
第2次大戦中に軍事用(暗号解読、弾道計算など)として出発した電子式計算機は、戦後に “機械を操作する装置” として高度化され、ここにウィーナーの提唱した「完結した機械」が実現することになりました。それが、産業用として実用化されたのは 1980年代のことです。
『ウィーナーの提唱したように、機械の作動を確認するセンサーと、その結果を目標と比較して調整するコンピュータが接続されることで、機械がようやく本物の機械になったのです。〔…〕機械ははじめて人間から独立し、完結した機械となりました。
そしてこういうものが実装されている工場を、かつては「オートメーション工場」と呼びました。〔…〕しかし〔ギトン註――今では〕あらゆる工場が、オートメーション化した』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, p.203.
そのせいで、かつては日本経済の花形だった、工場の生産ラインに並んで一糸乱れぬ統率で機械を運転していた「立場主義者」の群れは、不要になってしまったのです。
そもそも皮肉なことに、「立場主義者」を不要にしたのは、彼らの働きそのものでした。「立場主義」の人びとが一所懸命に知恵を振り絞ってコンピュータ、センサー、自動制御機械を開発し、特許を取って生産し、どんどん作って日本中の工場に普及させたために、コンピュータとセンサーを備えない機械はどこにもないほどになりました。完全な自動制御機械――産業ロボットだけで動いている工場もあります。そういう「ロボット工場」には、↑きょうのトップ写真で見たように、人の姿がありません。その産業ロボットもまた、産業ロボットだけの工場で生産されます。
こうして、「立場主義者」たちは、「立場」を守って必死に働いた結果、みずからの「立場」を失ってしまったのです。
『オートメーションができれば、立場主義者は不要になります。数多くの士気の高い労働者が、心を一つにして、多数の機械から構成される生産過程を統御する必要がなくなるからです。必要になるのは、こういったオートメーション機械のラインを設計運用する経営者・技術者と、あとは機械化するほどの価値がない過程〔倉庫管理、積み込みなど――ギトン註〕を動かす大量の低賃金労働者です。
〔…〕世界中の工場の機械に、センサーとコンピュータとが装着されていく中で、立場主義者は無用の長物になりました。
それ以降、立場主義は桎梏(しっこく)となります。経済活動にとって、必要がないばかりか、邪魔なのです。とはいえ社会構造はそのままですから、立場主義者は人の立場を脅(おびや)かすわけにはいかないので、立場の生態系だけは残っています。
〔…〕しかし、機械が立場主義者抜きで動くようになった以上、この立場でできた生態系は、もはや生産性を持たず、空回りしているのです。日本の社会にある立場主義者たちの形成する組織というのは、もはや経済的基盤を失って 30年以上が経過しています。それを守るために国債が発行され、日銀が膨張してきました。』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, pp.205-206.
自動制御機械(産業ロボット)の普及によって「立場主義」は不要になるが、「立場の生態系」は残る。つまり、居場所を失いたくない「立場主義者」の抵抗によって、「立場」のネットワークがカタチだけ残ってしまう。それが、経済が回っていくのを邪魔するようになる。
もはや生産性のない「立場の生態系」が、そのまま残り続け、そこに生息する人たちの生活を支えるために補助金を注ぎ込むことになるので、国債がどんどん膨れ上がってしまう、ということでしょうか?‥‥安富さんが、具体的にどういうことを言っているのか、「立場の生態系」とは何なのか、いまいちハッキリしません。
このあたりの説明は、『ジャパン・イズ・バック』のほうが、もう少し具体的なので、そちらを引用してみます:
『三千数百人で戦艦大和を動かしていた近代から、数人とコンピュータで巨大タンカーを動かす現代へ。それは、一人ひとりに「立場」があった社会から、「立場のある」わずかな人々と、顔も名前もない「立場のない」多くの人々がひしめき合う社会への変化とも言えます。
ですから本来は産業構造を変え、今までの花形である製造業や建築業で立場がなくなった人々も楽しく働けるような、創造的な職場や仕事を創り出したり、そうした事業を支援したりすることが必要だったのです。
ところが「立場主義者」たちは「立場」を中心に物事を考えてしまうために、あぶれた人々を収納する多くの「立場」をでっち上げる、また必要なくなった「立場」をいつまでも維持する、という方向に突き進みました。役所は特殊法人をたくさん作り、大企業は子会社を作り、立場だけあって仕事はありませんから、人々はそこで仕事をするフリをしています。膨大に刷られたお金はこの「仕事のフリ」に浪費され、社会に何も蓄積せず消えてなくなりました。
この立場主義社会では、アイデアややる気があっても「立場」がなければ相手にされません。〔…〕これでは若い力も生かされませんし、新しい事業も創造されません。こんな非効率極まる社会が持続可能であったり、成長を遂げたりするはずがありません。
日本の近代を引っ張った〔牽引した――ギトン註〕「立場主義」こそが、日本の現代の重い重い足枷になっているのです。』
安冨歩『ジャパン・イズ・バック』,2014,明石書店, pp.195-196.
なるほど、安富さんの指摘するマイナスの面――「立場主義」の組織を無理にも温存しようとして、創造的な活動を阻害する――は、なんとなく分かってきました。しかし、プラスの面が、いまいち分かりません。『「立場のある」わずかな人々と、顔も名前もない「立場のない」多くの人々がひしめき合う社会への変化』――格差の拡大を肯定し、少数のエリートを尊重して、大衆を蔑視するのか?‥という声が聞こえてきます。まぁ、避けられない傾向として、現実にそういうことがある、否定しても仕方ない、ということなのでしょうけれど、それにしても納得できないものが残ります。
『立場がなくなった人々も楽しく働けるような、創造的な職場や仕事を創り出』す――一転して “美しい未来” の提示ですが、現実の「格差拡大」があるのだとしたら、その趨勢をそのままにして、そんな美しい未来が描けるのだろうか? そもそも、「立場のある」少数の人を残そうとする、エリートにしようとする発想に陥ってはいないか? 安富さん自身が、「立場主義」にとらわれていないだろうか?
しかし、これは、「立場主義」崩壊後の社会をどう生きるか?‥という問題と関連するので、それをテーマとする次回の考察に送りたいと思います。
そこで、『生きるための日本史』に戻ります。
『立場主義者のオジサンたちが、早朝から工場に集まって、ラジオ体操して一丸となってなりふり構わず家庭を顧みずに仕事をする、というスタイルが驚くべき繁栄をもたらした時代が終わり、〔…〕
ところが私たちは、立場主義ワールドで生まれ育っているので、他の世界のことを知りません。〔…〕ですから立場主義が崩壊し始めると、何をするかというと、立場主義的な行動の強化を目指します。〔…〕
立場主義が日本を支えている、立場主義の倫理があるから日本は素晴らしいんだ、というようなテレビ番組が毎日垂れ流されています。こんなことは、立場主義の黄金時代には考えられないことでした。
人口構造が変わって経済成長が止まり、立場主義システムを支えるために膨大な国債を発行し、それを支えるために日本銀行を膨張させてしまいました。〔日銀の所有する国債が増え続けるということ――ギトン註〕〔…〕
いずれ限界が来るはずですが、限界がいつ来るのか、あるいは限界が来たらどうなるの〔…〕か、誰も見たことがないので知らないのです。』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, pp.214-216.
このあと安富さんは、社会の桎梏と化した「立場主義」の維持が限界に達した時に起きるであろう “大災害” についても述べているのですが、それはまぁ「ヤストラダムスのハルマゲドン」かもしれないので、通り過ぎておきます。
ともかくこれで、『生きるための日本史』「第3章」の終りまで来ました。
「第4章」は『「ポスト立場主義」への展望――無縁の原理』と題されています。そこでは、日本中世社会にあった、「家」とも「立場」とも異なる原理が明らかにされます。現代の私たちが、崩壊してゆく「家」も「立場」も超えて未来を開いてゆくためには、過去の歴史に遡ってみる必要がある。中世以前の人びとの生き方のなかから、未来のヒントを探してみようじゃないか、というわけです。
そういうわけで、「第4章」はまたガラッと考察の領域が変りますので、今回はここで締めたいと思います。
よかったらギトンのブログへ⇒:
ギトンのあ~いえばこーゆー記