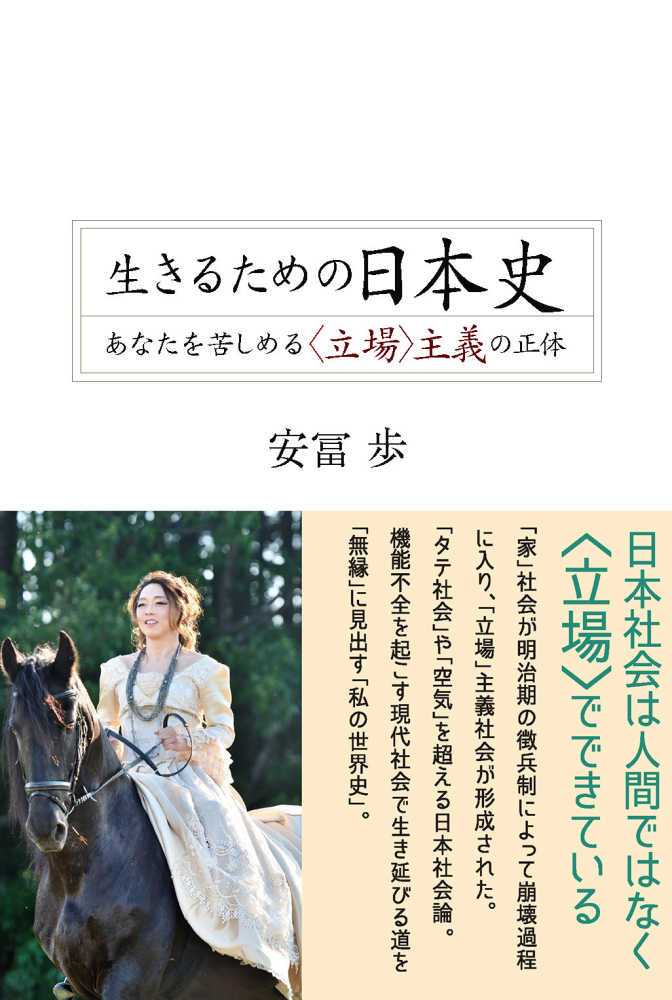ばら星雲 いっかくじゅう座にある発光星雲。
中心部にある高温の恒星群から照射される紫外線
によって星間水素プラズマが発光している。
©NASA/JPL-Caltech/UCLA
【9】「不規則遷移現象」「不安定平衡」「決定論的カオス」
「第1章」の後半。前回の最後にザクッと述べた「決定論的カオス」について、もう少し正確に説明しようと思います。ただ、現時点では、安富さんの本のなかで挙げられている参考文献もまだ読んでいませんし、細かい部分になると、私自身、この説明で果たしてよいのだろうか?‥という疑念が解消しておりません。ですから、最終的には読者みずから研究して、納得できる理解に達していただく、という前提で始めたいと思います。
さて、↑見出しに並べた3つの術語は、ここではほぼ同じ意味だと考えて構いません。
赤いインクを溶かした水と、青いインクを溶かした水を、静かにコップに入れると、はじめは、赤の強い部分と青色の強い部分に分かれていますが、長い時間放置しておくと、水の分子運動によって混じり合い、最後にはコップの水全体が同じ色になって落ち着きます。最終的には、コップの水は、どこをとっても均質になります。
この「拡散」運動を数式で表現すると、一定の「平衡点」に向かって収束してゆく関数式になります。「平衡点」に完全に一致するわけではないが、そこへ向かって無限に近づいてゆく曲線が描かれます。
水とインクの場合には、そうなりますが、赤い水と青い油であったら、両者が分離した状態が「平衡点」になります。
ところが、溶液の成分によっては、「平衡点」に収束しないケースもあります。有名な「ベロウソフ-ジャボチンスキー反応(BZ反応)」では、溶液の色は、青くなったり赤くなったり、周期的に変化します。この場合、系が落ち着く “定常状態” は一定の「平衡点」ではなく、周期的な「振動」なのです。実験のしかたを工夫すると、シャーレに薄く延ばした液面に同心円状の縞もようが現れ、ゆっくりと広がってゆくように見えます:
自然界でも、鳴門の「うずしお」など、「周期的振動」がつくりだすパターンもようが、しばしば観察されます。
ところが、周期的「振動」を行なっている系に対して、さらに条件を変えてゆくと、系はもはや定常状態にはならず、不規則にしか見えない勝手な運動をえんえんと続けるようになってしまいます。つまり、「カオス」のふるまいをするようになるのです。
『電気回路に現れるこういった複雑な動きを調べていて上田先生が発見したのは、決定論的な方程式であるはずなのに、何かわけのわからない動きを延々とやっているようなタイプの運動でした。それを「不規則遷移現象」と名づけたのです。後にそれは「決定論的カオス」という愛称で呼ばれるようになりました〔…〕
たとえば振子(ふりこ)を考えてください。〔…〕振子の先に、さらにもう1個振子のついている、二重振子というものがあります。ふつうの振子はくるくる回るだけですが、途中に関節のついている二重振子を回すと〔…〕突然くるくるくるっと何回転かしてまた元に戻るという、〔…〕非常に複雑な動きをします。これが不規則遷移現象です。完全に決定論的にできてはいるけれど、それがどのように動くかは予測できないのです。』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, p.36.
ここで、ひとつ疑問がわきます。「決定論的にできている」――つまり数式で表すことができるのならば、最初の「初期条件」がどうなっていたかを「正確に」測定することさえできていたならば、そこからどんなに複雑な運動が結果しようとも、その動きと経路は理論的に正確に「予測」できるのではないか? 古典的な考え方では、そう言えるはずです。「予測できない」ように見えるのは、われわれの測定能力に限界があるせいにすぎない――のではないか? 安冨さん自身、別の箇所では、次のように書いています:
『「不規則遷移現象」が、〔…〕最初の刺激の小さな差異が大きな差異に結果する、という「不安定平衡」とも言うべき現象であり、それはまれなことではなく、この世界に普遍的に見られるのだ、ということが今では知られています。』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, p.34.
しかし、それとは異なった・次のような説明も書いています。例として、小麦粉に水を加えてパン生地をこねる場合が述べられます。ひとつひとつの小麦粉の粒を、点として考えます。生地を薄く延ばして、折って重ね、また薄く延ばして重ねる、という操作を繰り返すと、はじめにすぐ隣りにあった2つの点は、何回か後にはまったく離れた場所に移動してしまいます。さらに何度も操作を重ねてゆくと、あるときには偶然に、その2つの点が、すぐ近くに来ることもあるだろう。そうした動きがどうなっていくかは「予測できない」、と言うのです:
『一本一本の経路は非常に不安定で、少しでもそこから外れると全然違う動きをする経路が、すぐ横を走っています。現実の世界では、こんなに不安定な経路を正確にたどることは不可能ですから、必ず、すぐ横の経路へと滑っていってしまいます。滑った先もまた不安定なので、そのすぐ横へと滑ります、こうしてどんどんと滑り続けていってしまう、ということになります。これが不規則遷移現象の本質です。こうして、決定論的な世界に不規則な運動が生じるのです。』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, pp.37-38.
↑この部分は、私には納得できません。安冨さんの説明には、どこか間違えがあるようにさえ思えます。それぞれの小麦粉粒の動き自体は、練り粉全体に加える力の大きさと向き、練り粉の粘性などの特性値、摩擦係数、‥‥などの関係式によって「決定」されているはずです。小麦粉粒の「一本一本の経路」が「不安定」だ――ということの意味は、すぐ隣にある粒どうしが、大きく異なる経路を描く、ということ以上ではないはずです。「一本一本の経路」じたいは、数式によって力学的に確定されており、完全に「予測」可能であるはずです。突然に…、何の原因もなく、粒が「隣りの経路」へ移ってしまう、などということはありえません。
それにもかかわらず、結果的に「予測できない」「不規則な運動が生じる」ということを言うために、安冨さんは、小麦粉粒の点が「すぐ横の経路へと滑って行ってしま」う。その結果、その後の動きは、当初の予測と大きく異なるものになってしまうのだ、と言います。これは詭弁ではないか?…
しかし、詭弁のように見えるのは、古典的な考え方――高校で学んだ19世紀の「決定論」的な物理――で対処しようとしているせいかもしれません。20世紀には、自然科学の「決定論」に綻びが生じています。安冨さんの言う、すぐ隣りの経路への「横すべり」「横ずれ」とは、20世紀に発見された「非決定論」の比喩なのではないか?
古典的な考え方では、あらゆる運動は、(たとえ人間には正確な測定が不可能だとしても)一定の初期条件をもって開始されます。運動の途中で初期値(初期条件)が変わってしまう――隣りの「経路」へ移ってしまう――などということはありえません。捏ねている途中で、パン職人の力の加え方が微妙に変わったとしても、どう変わったかが正確に測定できたとすれば、小麦粉粒の動きは完全に予測可能です。
ところが、20世紀の量子力学は、このことが、原子の内部のようなミクロな世界では成り立たないことを明らかにしました。ハイゼンベルクの「不確定性原理」です。
ウェルナー・カール・ハイゼンベルク(1901-1976)
【10】ミクロの世界は「不確定」
ハイゼンベルクの「不確定性原理」というのは、原子の内部構造のようなミクロの世界では、粒子の存在する位置やエネルギーの大きさが「不確定」になる、という原理です。
極微の粒子――たとえば電子――は、粒子(物質)であると同時に波(エネルギー)です。粒子は、ある瞬間には、空間の・ある場所に存在します。これに対して、波(波動)は、どこか一点にある、というものではありませんが、ある瞬間には、ある一定の運動量(振動数)をもっています。そこで、粒子でもあれば波でもある、粒子かと思うと波のようでもある「電子」は、空間上の位置と運動量とを、同時に確定することができないのです。
このことは、「ボーアの原子模型」との関係で、微妙な問題を引き起こします。
ボーアは、原子核の周りを電子が円軌道を描いて回っている太陽系のような原子模型を考えました。たとえば、水素の場合、電子は1個ですが、軌道はいくつかあって、電子のもっているエネルギーが大きい時には外側の軌道、小さい時には内側の軌道を回ると考えました。縄に錘(おもり)をつけて振り回すと、円が大きいほど大きな力がかかるのがわかりますね。それと同じです。
電子が外側の軌道から内側の軌道に移るときには、エネルギー準位の差に相当するエネルギーを光(光子 フォトン)として放出します。逆に、内側から外側に移るときには、光子を吸収します。光子1個のエネルギーの大きさは決まっていますから、電子のエネルギーは、とびとびの値をとることになります。そのために、電子の軌道は、いくつかに決まっている。好きな場所を飛び回れるわけではない。ボーアは、このように考えました。
このことは、原子の「発光スペクトル」「吸収スペクトル」という現象に対応しています。たとえば、放電管に封入した水素を発光させて、プリズム分光器を通してスクリーンに映すと、下図のようなとびとびの輝線が観測されます。輝線は、ライマン系列(Ly)、バルマー系列(Ba)、パッシェン系列(Pa)などに分類されていますが、バルマー系列とパッシェン系列の一部だけが可視光の範囲です。発光のスペクトルがとびとびなのは、軌道のエネルギー準位の差が、いくつかの決まった値だからです。
ところが、ここに、「位置と運動量(エネルギー)の不確定性」という問題が加わってきます。やっかいなことに、「位置」と「運動量(エネルギー)」は、同時には確定しないのです。
もし、電子の「エネルギー準位」が確定しているなら、位置は不確定になります。したがって、ボーアが考えたような、定軌道の上を電子が回っているモデルは、実際の原子の構造ではないことになります。むしろ、電子は、あいまいに広がった存在確率の雲(ないしエネルギーの広がり)のようなものだと思わなければなりません。「電子雲」は、エネルギー準位ごとにさまざまな形をとります↓。下の各図は、原子核をとりかこむ「電子雲」の断面図を表しています。
水素原子の電子雲
(2,0,0)~(4,3,3)は、エネルギー準位。各図は、明るい部分ほど
電子の存在確率が高い(電子波の強さが大きい)ことを表す。
ところで、これとは逆に、電子の位置が確定する場合には、運動量(エネルギー準位)が不確定になるはずです。たとえば、水素原子の内部に写真フィルムを差し込んで、電子(粒子)と原子核(陽子)の像を撮ったとします。そんなことがどうしてできるか分からないし、たぶん不可能ですが、仮にできたとします。「不確定性原理」によれば、フィルムには2つの点が写るはずです。原子核の位置も、電子の位置も確定します。しかし、運動の速度も向きも「不確定」です。つまり、エネルギー準位が「不確定」です。
原子は、内部の電子が、あるエネルギー準位で運動(振動)しているだけでなく、原子全体としても、(他の原子との引力・斥力による)曲線運動や振動やスピン運動(自転運動)をしています。内部電子の運動(エネルギー準位)は、その原子の「反応活性」であり、他の原子との「結合状態」にほかなりません。ひとつの原子全体のスピン等は、「熱」というものの正体です。
いま、内部電子が、どのエネルギー準位にあるのやら、不確定である!‥原子全体の熱運動も不確定である‥‥のだとすると、原子の「反応活性」も、分子の「結合状態」も、ミクロの熱量も確定しない――ことになります。すなわち、これらミクロの「初期条件」が不確定で、偶然に、ランダムに変化してしまう;“小麦粉粒” の動いてゆく「経路」が不安定で、偶然的に「横ずれ」してしまうということです。
↓つぎの引用文でバートランド・ラッセルが、「所与の一原子が、可能な遷移のうちどれに従うか決定する物理法則は存在しない」と言っているのは、そのような事態を指していると思われます。
『ラッセルは、脳のダイナミクスについて、次のように言います。
〔…〕生き物の一つの特徴は、不安定平衡の状態であり、この状態は人間の脳において、最も高度に発達している。〔…〕わずかな最初の刺激の差異が、巨大な違いを結果として引き起こす。〔…〕脳のなかでは、〔…〕ひとつの原子の二つの可能な事態の差異が、筋肉の巨視的な違いを生み出す、〔…〕量子力学によれば、所与の一原子が、可能な遷移のうちどれに従うか決定する物理法則は存在しない。
それゆえ、脳のなかでは「意志(volition)」とよばれる心理的な要因によって可能な遷移が決定される、ということを想像することができよう。〔…〕 (B. Russel: Human Knowledge, Routledge:Oxford, 2009, p.42)
〔…〕実は、現代の脳科学者には、脳を「不安定平衡」に相当するダイナミクスの観点から理解しようとする人が増えています。
〔…〕「不規則遷移現象」が、まさにここでラッセルが説明している、最初の刺激の小さな差異が大きな差異に結果する、という「不安定平衡」とも言うべき現象であ』る『ことが今では知られています。』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, p.32-34.
つまり、脳のニューロンを構成する一原子に生じた偶然的な「状態遷移」が、「非線形」のダイナミズムによって拡大されて、マクロの動きとなって現出する。それを見て、われわれは、人間は必然によってではなく「意志」によって行動する、と言うのだ。これが、ラッセルの述べている着想です。これ自体は、ラッセルという専門外の学者の着想にすぎません。ラッセル自身、これを述べたあとで即座に否定してもいます。しかし、脳のなか――脳とは限らない!――でのミクロな偶然――非決定論!――の結果が、「非線形システム」によって不規則に拡大されて、「気まぐれ」のような、「意志的挙動」であるかのような、《人間の行為》となって現れる。――この着想は、首肯しうるものだと思います。
人間の「意志」と言われるものは、あたかも論理的思索の結果を実行するかのように見えて、その実つねに「偶然」的な「気まぐれ」な部分が伴います。それを人は、「感性」とか「気分」とか呼んで、そこに「人間らしさ」を感じるのです。実のところは、「偶然」が不規則に拡大して現れたにすぎないものであっても、人はそれを「自分の行為」として認め、責任を取るようにと、社会から期待されています。もし期待に従わなければ、「狂人」「変質者」などとして社会から弾き出されてしまいます。そこで人は、そうしたさまざまな挙動を「自分の行為」として引き受け、正当化し、一貫した論理の糸で結ぶべく努力するのではないでしょうか? ここには、ひとつの人間観が現れています。
【11】人間の「偶然性」と社会の「安定性」
人間の「意志」というものは、一面において「偶然」で気まぐれです。論理的思考によって完全に決定されるわけではなく、環境によって必然的に決定されているのでもありません。しかし、他面において、何らかの「一貫性」がなければ――まったくの気まぐれの連続であったならば――、人はそれを「意志」とは呼べないでしょう。
そこで私は、人間の行為は、①非線形な「偶然性」、②環境に対する自動的な「反応」、③意志的な「一貫性」――という3者のバランスの上に成り立っているのではないかと考えたことがあります。③の「一貫性」のもとは、すでに行なった行為の「記憶」や「習慣」、あるいは他人の行為の「模倣」といったものだと思います。人間の身体が、一度したことのある動作をくりかえすのは、難しいことではないでしょう。「模倣」もまた、人間や動物の身体がもつ基本的な習性です。それらを、みずからの意識的な志向の結果だとして正当化すれば、その人の「意志」だということになります。
ところで、この点――「一貫性」――について、安冨さんは別の見解を述べておられ、興味を惹かれました。安冨さんは、「不安定平衡」から偶然性、不規則性を導出するだけでなく、ある種の「一貫性」をも、同じ「不安定平衡」から導いてくるのです。
『上田先生が最近なさった研究ですが、これほど構造的に不安定で敏感なはずの方程式に、かなり乱暴に微細な項をくっつけたものをシミュレートしても、出てくるカオスの形はあまり変わらないのです。これを上田先生は「実体安定性」と命名しました。〔…〕
初期値に対する不安定性と、係数についての構造不安定性があるにもかかわらず、不規則遷移現象の形そのものは安定であり、大きな歪みを与えてもあまり変わらない、という実体安定性がある。〔…〕
世界がまったく不安定だったら、人は生きていけません。しかし、なにもかもが固定されていても生きていけません。世界は極めて不安定ながら、実体的には安定している、それゆえ我々はかろうじて生きていけるのです。
ここに見られる実体安定性〔…〕は、線形性を前提とするようなタイプの予測可能性とか安定性ではないのです。予測不可能で、構造的にも不安定で、にもかかわらず実体的に安定している。なにか違う安定性です。』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, p.38-39.
「実体安定性」というのが、どういうものなのか、上田睆亮氏の論文を読んでみないと――あるいは読んだらなおさら――わからないのですが、安冨さんが述べておられる「社会」の問題に限っていえば、なんとなく想像はできます。
この世界に、ラッセルの言うような論理的・数学的な「合理性」が通用する科学の領域と、それが通用しない・いわば「神秘」の領域があるとすると、たしかに「神秘」の領域で起こることについては、「合理的」な予測は不可能である。しかし、そういう「神秘」の領域であっても、私たちには真暗で何も見えない、というわけではない。ある種のパターン認識というか、‥これは何々だ、‥これも何々だ、‥けっきょく同じものじゃないか……というような直感的な認識はできる。そういうことだと思います。
たとえば、人の顔を見て、これは誰々さんだ、という識別を、私たちは瞬時に直感的に行ないますが、「どうして誰々さんだと思うのか、コトバで説明しろ」と言われても、うまく言えません。しかも、こういう識別は、コンピューターにさせることも可能なのです。なぜできるかと言えば、人の顔はさまざまな機会に、さまざま異なる “見え” を与えながらも、「実体的」な共通性、安定性があるからだ、ということだと思います。
『ラッセル的な厳密さという観点によって理解の安定を果たそうと思うと、そう簡単にはいかない不安定性がありながら、それでいて別の意味で安定していて見通しが効く。そういう不思議な世界に私たちは住んでいるのです。』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, p.39.
【12】歴史に、社会の「パターン」を発見する。
ところで安冨さんは、この「実体の安定性」――「パターン認識」ということから、日本の社会、日本の社会の歴史というものを考えようとしておられます。
『人間という動物は一人でいるよりも、たくさんの人々と、お互いにコミュニケーションしたほうが幸せになる。これをしないではいられないのです。〔…〕
人間とはそういう動物で、そのコミュニケーションが継続的に再生産され、あるパターンが維持されるなら、そこに社会が生成します。〔…〕
人間の暮らしを支え、コミュニケーションを生成するには、絶対に物質なりエネルギーが投入されて、廃棄物を排出する必要があります。人々がコミュニケーションを展開するなら、そこに物質を投入して廃棄物や熱などが排出されることは避けられない。これが経済の正体です。』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, pp.55-56.
安冨さんの↑この議論のなかで、私がとくに注目したいのは、「廃棄」「排出」を社会の必須の機能として組み込んだ点です。これまで、「生産」や「流通」の意義を力説した人は多くいましたが、「排出」に注目した人はあまりいなかったと思います。
しかし、「排出」のなかでも、私は、エネルギーの「排出」、すなわち「廃熱」が重要だと思います。なぜなら「廃熱」は「創造」の母だからです。
熱力学に「カルノー・サイクル」という計算式があります。蒸気機関のように、熱を力学的な仕事に変換する場合、100%の効率は達成できない。かならず一定量の熱は “ムダに” 排出しなければならない、という原理です。力学的な仕事とは、つまるところ “建設” であり、構造のなかったところに新たな構造を創ることです。この宇宙には、「熱力学第二法則」というのがあって、あらゆる構造は、いつかは崩れてしまって、一様なスープのような混沌世界になってしまう(エントロピーの増大)、という運命に逆らうことができない。しかし、その「崩壊」のまっただなかで、エネルギーが散逸する流れの中途において、逆に新たな構造が創られてもゆく。そこでは、「第二法則」にさからってエントロピーが低下しているのです。
たとえば、雪国の春先の森林で、樹の幹のまわりだけ雪が融けているのを見たことがないでしょうか。樹の中では、いままさに春に向けて、芽や葉や花のもとになる構造が創られています。春になってから起きるのは、すでに創られて小さく折りたたまれていたものが展開してゆくだけです。ほんとうの創造活動は、冬のうちに樹の中で行なわれます。樹の芽の創造も「カルノー・サイクル」ですから、かならず「廃熱」を伴ないます。だから、幹のまわりの雪が融けているのです。
根開き 鹿沢インフォメーションセンター (本文に書いた「根開き」の説明は
詩的なものとお考えください。科学的な説明はリンク先で。)
ただ、ここでちょっと気になるのは、安冨さんの歴史に対する見方は、ちょっと哲学的過ぎやしないか、という点です。批判ということではなく、私の志向との相違として、そういう気がするのです。
哲学的な歴史が悪いなどとは言えません。哲学的な歴史観というものには、多くのすぐれた先例があります。マルクス/エンゲルスがそうですし(⇒:『ドイツ・イデオロギー』ノート)、ホッブズ、ロック、ルソー、ヘーゲルといった人たちの著作も、すぐ頭に浮かびます。こうして並べてみると、哲学的歴史観は、進歩的な著者に多いようです。
これに対して、とくに合理的な原因・根拠がなくとも社会が継承してゆく・伝統的な文化や習慣、法制度や掟といったものを重視する歴史観もあります。こちらは、保守的な著者に多いかもしれません。
私は保守的な思想を喜ぶわけではないのですが、歴史観としては後者のほうに親近感があります。なぜかと言えば、考古学、民俗学のような科学の成果を無視することはできない。それらの成果を見るかぎり、人間の社会はそんなに機能的にはできていない、と思うからです。
たとえば、縄文時代の集落を発掘調査した結果、縄文中期を中心に、住居がドーナツ形に並んだ「環状集落」が多く、規模の大きな「環状集落」もある、ということがわかってきました。
住民の間のコミュニケーション、また、物質的生産と消費、という観点だけで考えれば、集落の形がドーナツ形でなければならない理由はないはずです。直線状に住居を並べても、三角形でも、生活に支障はない。にもかかわらず、数百年~千年以上のあいだ、ずっとドーナツ形の集落が営まれたのはなぜなのか? そこに縄文人の宗教観念を見る人もいます。が、ともかく、何らかの伝統ないし習慣を考えなくては、このことは説明できません。集落の機能といった合理性では、説明がつかないのです。
【13】「合理的な神秘主義」
20世紀に、ラッセルのようなさまざまな合理主義者が、合理性によって世界を征服すべく、涙ぐましいまでの努力を傾けた結果として、…皮肉にも…、この世界を、人間の合理的思考によって理解するには限界がある、ということが明らかになってきました。これに対して、‥
『ウィトゲンシュタインは、最初から、合理性の限界を見ていました。彼は、思考の限界というものに線を引いて、ここまでは思考できる、ここからはできない、というふうに線引きをするべきだと考えていました。〔…〕思考するということは、言語で語れるはずだということです。そして語り得ることには限界がある。だから語り得る世界と語り得ない世界がある〔…〕』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, p.40.
ウィトゲンシュタインが言うのは、「語り得ない世界」について、無理に語ろうとしてはならない、ということです。無理に語ろうとすれば、確実性のないことや、確かめる手段のないようなことまで、ハッタリで言わなければならなくなる。極端な場合には「オカルト」になってしまいます。その結果、「語り得る」世界についての語りまでが、信用できないものになってしまう‥
『ウィトゲンシュタインは、〔…〕ちゃんと線を引かないといけない、線の向こうは「神秘」である、神秘によって〔この世界と私たちの生存が――ギトン註〕支えられているとすればそれでいいのだと考えたのです。』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, p.42.
そこで、安冨さんは「合理的な神秘主義」という考え方を提唱します。世界を、「語り得る」領域と、語り得ない「神秘」の領域に分けて線を引く、という考え方はウィトゲンシュタインに倣います。その一方で、合理的に「語り得る」領域についても、「知識は個人の経験に根差しており、科学的知識さえも、個人の経験という “根” を離れては存在しえない」というラッセルの考えを取り入れるのです。
『私たちは、神秘によって支えられ、神秘的な力によって生きていて、語り得るものには限界があり、神秘について語ってはならない。なぜなら、ナンセンスだ〔語っても、意味をなさない――ギトン註〕からです。〔…〕
しかし同時に、ラッセルの〔…〕、知識が「言語化されない動物の行動のなかに根をおろしている」という考えに賛成します。そして知識が個人の経験に根ざしており、科学的知識でさえも、その根から離れては存在しえない、というラッセルの考えを継承します。』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, p.42.
安冨さんは、ウィトゲンシュタインに倣って、合理的に「語り得る」領域と「神秘」の領域とを分けます。そうは言っても、「神秘」の領域はまったく考察も語りもできない、と見なしているわけではありません。「神秘」領域のうち、ある部分については、慎重に手探りしながら徐々に探究を向けてゆくことができる。さきほど【11】で、ちょっとだけ、そのことに触れました。
そして、安冨さんの見解は、「神秘」が私たちを生かしてくれる力を妨げるもの、阻害するものに関しては、例外的に語り得る、と言うのです。これが、安冨さんの「合理的な神秘主義」です。
「合理的な神秘主義」とは、ほとんど正反対な態度として、「神秘的な合理主義」というものがあります。「科学によって、何でも合理的に理解できる、解決できる」。今できなくとも、いずれは必ずできるようになると固く信じている態度です。この考え方によれば、「科学的予測は万能だ」ということになります。なぜなら、科学で証明できないようなものは、存在しないことにしてしまうからです。
このように考える人は、理系のなかでも「無知蒙昧」で「ダメ」な研究者だ、と安冨さんは言います。
「神秘的な合理主義」とよく似ていて、ただ向いている向きが逆なのが、「オカルト」です。たとえば、ルドルフ・シュタイナーのような人がいます。彼らは、語り得ない「神秘」を、直接に語ってしまいます。彼らの語りは、私たちのふつうの思考では理解できない「オカルト言語」になります。そして、合理的に「語り得る」領域のことがらまでも、「オカルト言語」で語るようになります。すなわち「陰謀論」です。
よかったらギトンのブログへ⇒:
ギトンのあ~いえばこーゆー記