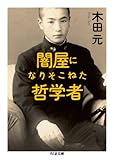私は記憶法というジャンル(あるいは書籍)があまり好きではありません。
記憶法に絞った本はそれほど読んでいませんし、あまり読む気にもなれません。
記憶法の多くは、その話のネタの豊富さに比べて、実行可能性の低いものが多いからです。
エビングハウスの忘却曲線とか、言っていることは分かるのですが、いちいちそんなものに合わせて勉強できるかというと、多くの人には面倒くさすぎて難しいと思います。
そんなこんなで、記憶法にかんしては、よほどシンプルなものでない限り敬遠してきました。
極論すれば、記憶法は、勉強法一般の中で最もどうでもいいことだと思ってきました。
ところが、司法試験のような高難度の試験では逆に記憶の意義が強調されることは少ないのですが、広く巷では、勉強法といえば記憶法のことだ、と半ば理解されているところがあります。
勉強法のブログをみても、そのほとんどが記憶法について書かれたものです。
個人的には、こういうものにはほとんど興味がありませんし、あまり意味がないものだと思います。
なぜなら、司法試験のような、相対的に覚える量が極めて多いとされる試験においてさえ、記憶の仕方に問題があったために受からなかった、なんて例は実際には存在しないからです。
記憶法など駆使しなくても、司法試験程度の知識なら、本気になればどんな人でも覚えられます。
何かが覚えられていないのは、要するに努力をしていないだけです。
司法試験を含むほぼ全ての試験において、このテーゼは成立します。
何かが記憶できていないのは、その人に本気で受かる気がないというだけのことなのです。
本気で受かろうと思って、それでも覚えられないがゆえに受からない試験があるとすれば、(あくまで想像ですが)それはせいぜい司法書士試験くらいではないでしょうか。
また、記憶法は、実行可能性が低いだけでなく、期待されるほど効果が高いものでもないとも思います。
私もいくつかの記憶法を試したことがあります。
その経験から言えるのは、記憶法と呼ばれるものを多少駆使したところで、その効果は微々たるものだということです。
記憶法は、その方法の多彩さ、あるいは労力の高さに比べて、得られるものが少なすぎる。
これが私の率直な感想です。
結局、桜蔭の女の子 で書いた通り、一冊の教材を浮気せずに徹底的に繰り返すことが、それを記憶法と呼ぶのであれば、最もシンプルで実効性の高い記憶法なのではないでしょうか。
特に記憶の仕方など殊更意識しなくても、教材を徹底して“潰す”ことさえ心掛けていれば、通常の試験なら、必要な記憶は自然にできるものなのです。
********************
ここまでは記憶法不要論でした。
もっとも、そんな私にも、ひとつだけおすすめできる記憶法があります。
昨日紹介した『世界最速「超」記憶法』 の方法論です。
この方法論は、人が何かを覚える際、覚える量を意図的に絞って、より少なく覚えるほうが、かえって多くのことを正確に覚えられるというものです。
【再録】
『世界最速超記憶法』の記事から、司法試験受験生にとって重要だと思う部分をそのまま抜き出して再録しておきます。
<再録はじめ>
少し脇に逸れた内容ですが、法律の勉強について触れている部分があります。
法律の条文や会計学の文などの表現を理解し、記憶するためには、「その表現の条件である考え方」を徹底して先に理解していったほうが、記憶と理解はうまくいく・・・(P.206)
↑これは大賛成です。
このブログで再三にわたり、インプットでは条文構造の理解を、アウトプットでは処理手順の習得の重要性を訴えてきました。それは、こういった切り口(方法論)を持っている場合と持っていない場合とでは、勉強の効果に格段の差が生まれてしまうからです。
当ブログの思想を本書の内容に繋げていうと、条文を起点にすることや、論文の処理パターンを用意することが、確実に法全体の理解(※)に寄与したのは、法全体をそのままの形で相手にせず、習得すべき対象を「条文」と「処理パターン」に絞り込んだがゆえの成果であったと説明できると思います。
※ここでの「理解」とは、法を記憶→使用できる状態のことです。
もっと具体的にいえば、法を使って司法試験の問題が解けることです。
漠然とした概念としての“理解”のことを言っているのではないのでご注意ください。
<再録おわり>
この本には具体的には書かれていないことですが、本書の方法を少しだけ応用させてみます。
まず、この本のポイントは、覚えるべき内容を全部覚えようとしないで、覚える“きっかけ”だけを正確に覚えることで、記憶の再現をしやすくする、というものです。
ここで著者の意図を勝手に踏み越えて、私なりに少し大胆に踏み込んで言ってしまいますが、この記憶法には、人間の記憶が実は一切消えていないとの仮説が含意されているように思います。
もっとも、いくら記憶が消えていないといっても、簡単に思い出せないのは事実です。
しかし重要なのは、何かはっきりとした“きっかけ”があれば思い出せるという事実のほうです。
たとえば、10年前、あなたが友人とレストランで相談事を兼ねて食事をしていたとします。そのとき、斜め右のテーブルに座っていた子どもが、ジュースが入ったグラスを思いっきりひっくり返して割ってしまったとします。びっくりしたあなたと友人の会話はいったんそこで途切れ、事態が収まったのち、再び元の相談事に戻った。こういうなんでもない出来事があったとします。
10年の時を経て、今日、あなたは別のレストランで、別の友人と食事をしています。そのとき、斜め右のテーブルに座っている子どもが、またもやグラスを思いっきりひっくり返して割ってしまったとします。10年前のあの時と同じ状況です。このとき、10年前にそのグラスがひっくり返った瞬間に友人と話してした会話の内容が、10年の時を経て不意に甦ってくる・・・こういう経験は誰にでもあると思います。
その日、その場所で、その瞬間に、同じような状況でグラスが割れさえしなければ、その後の人生で死ぬまで思い出すことがなかったであろう記憶が、一つの些細な“きっかけ”によって思い出されてしまう。そんなことがあるかと思います。
このケースでは、「レストランで斜め右のテーブルに座っている子どもが思いっきりグラスをひっくり返す」という“きっかけ”がトリガーとなってあなたの記憶を甦らせたわけです。
具体的な“きっかけ”がタイミングよく介在すると、ほんの小さな記憶すら甦ってしまうことがある。
これが人間の経験や記憶、あるいは脳の不思議だと思います。
ひょっとすると、人間の記憶は、1度経験したら二度と消えることがないのかもしれません。
実際には甦る記憶と甦らない記憶があるわけですが、実は人間は全ての記憶を保持していて、その上で、甦るor甦らないを分ける秘密(鍵)が脳にはあって、先ほどから述べている“きっかけ”が介在した場合に、そのきっかけが鍵となって、記憶が甦るということです。
ということは、もしその“きっかけ”を自覚的にコントロールすることができるようになれば、少なくとも何もしない場合よりはずっと容易に、記憶の再現ができるようになるということです。
ここで述べていることは一種の仮説です。
本当に記憶が一切消えていないのか、本当のところは誰にも分りません。
ただ、容易には甦らないだけで、少なくとも人間が相当に小さな記憶まで保持していられることは経験則から考えてまず間違いありません。
“きっかけ”が記憶喚起の鍵を握っているのも確かでしょう。
記憶法が上手くいくかどうかは、この“きっかけ“をいかに作るかにかかっています。
『世界最速「超」記憶法』では、この“きっかけ”は、漢字や英単語の記憶法として使われています。
ところが、実はこの方法は、もっと長い文章レベルにも応用が可能です。
具体的にいうと、短答問題の解説部分や、論証の理由づけ部分、あるいは論文の解答例の暗記などにも応用することができます。
私自身も、何度か試してみました。
たとえば、ある論文問題の解答例を覚えるとします。
まずは問題文を読み、次に解答例の全文を読みます。
最初は端から端まで、全部をしっかりと読みます。
それが終わったら、解答例の中から、ポイントとなる1つのフレーズだけを完璧に暗記します。
私が最初に試したときは、論証部分のキーとなるフレーズを1個だけ暗記しました。
ここで重要なのは、「完璧に暗記」というところです。
さらに重要なのは、暗記すべき事項を膨らませず、極力絞り込んで覚えることです。
どんなに多くてもキーワード数個程度、少なければキーワード1個で十分です。
つまり、極限まで絞り込み→完璧に暗記する ということです。
絞り込み→暗記法 とでも名付けておきましょうか。
この方法を最初に試したときは、自分でもその効果に驚いてしまいました。
1回きちんと読んだだけなのに、それから1週間も放置したままだったのに、先ほど書いた1個のフレーズを思い出しただけで、問題文の事案の概要や、おおよその答案の構成が甦ってきました。
もちろん、一字一句ではありませんが、答案のおおよその流れは覚えていました。
「うわぁ、全部覚えてる・・・」
人間の記憶力が、自分で自覚する以上に強力であることを知りました。
もっとも、私の中で答案構造の理解および処理パターンの確立が、記憶の定着に寄与したのは間違いありません。
こういった構造(=パターン)の確立はいずれにしても重要です。
上の【再録】でそのことを書いておきました。
ただし、注意していただきたいのは、司法試験は答案の暗記合戦ではないということです。
特に、論文試験においては、このような答案丸暗記の勉強法は絶対におすすめできません。
司法試験で問題と解答をただ読んで覚えるような勉強をしている人は、基本的に司法試験には受かりません。そのことは忘れないでいてください。
一番下の【追記】で、「答案暗記法はなぜダメなのか」を論じています。
もっとも、それを前提に、この方法は、上手に使えば一定の効果は望めるだろうと思います。
私は、肢別本のような暗記系の問題集でこの方法を試しています。
何箇所もマークしたくなる気持ちを極限まで抑制して、
・問題文のポイントに一箇所
・解説のポイントに一箇所
それぞれマークをします。
センテンス単位ではなく、あくまでも単語単位でマークすることが重要です。
それ以上の加工は絶対にしません。
このように、加工したい気持ちを極限まで抑えて、マーク箇所を絞る癖をつけるようにします。
すると、その問題の中で本当に譲れないポイントがどこなのかを考えるようになります。
「とりあえず大事そうだからマークしよ」という感じでやっていると、こういう厳しさが身に付きません。
重要ポイントを見極めるクセをつける意味でも、この 絞り込み→暗記法 は有効です。
多くの受験生は、線引き・マーク・書き込みなど、教材の加工をし過ぎています。
たくさん覚えたいという気持ちや、重要なポイントにはすべてチェックをつけておかなければならないという生真面目さから、教材を線引き・マーク・書き込みだらけにしてしまうのです。
しかし、たくさん線を引いたから覚えられるわけではありません。
『世界最速「超」記憶法』にも書かれているように、線を引けば引くほど覚えにくくなってしまう面のほうが実際には大きいのです。
それに、線引きなどチェックの箇所を増やすと、そのぶん教材を回すスピードが遅くなります。
チェックの箇所で思考がいちいち止まるからです。
そもそも、そこで思考を止めるためにチェックが行われるのですから当然です。
記憶の定着度は、基本的に回した回数に依存します。
記憶を増やすためにチェック箇所を増やしてしまうのは、スピードの観点からも逆効果です。
今回のまとめをします。
①線を引く箇所は極限まで絞り込むべきです。
②その代わり、絞り込んだポイントは完璧に暗記することが必要です。
試験において、1の完璧な暗記は、100の曖昧な理解に勝ります。
また、「スピードぐるぐる勉強法」 の観点からも、教材の加工は最小限に抑えるべきです。
教材を加工しすぎると、スピードが落ちてしまうからです。
そして、何より大事なのは、自分の記憶力を疑わないことです。
実際には、あなたの脳は、あなたが思う以上に覚えています。
この事実を、勇気を持って信じることが大事だと思います。
教材を塗りたくってしまう人は、その意味で、自分の記憶力(=脳)が信じられない人なのです。
(おまけ)
桜蔭の女の子 には書かなかったことですが、実は未だにひとつ気になっていることがあります。
それは、桜蔭の彼女が、速いスピードで教材を回し→潰す「スピードぐるぐる勉強法」だけではなく、今回紹介した「絞り込み→暗記法」についても知っていたのではないか、ということです。
もちろん自覚的にではなく、無意識的なレベルで知っていた、ということです。
実際、彼女は、ほとんど教科書に線を引いていませんでした。
単に速いスピードで教材を何度も回すだけでなく、教材の加工自体が極めてシンプルでした。
普通の受験生がセンテンス単位で線引きをする中、彼女はせいぜい単語レベルでしか線引きをしていませんでした。それも、1ページにせいぜい数個程度。
ひょっとすれば彼女は、この“きっかけ”を使った記憶喚起の方法に、すでに高校生の段階で気づいていたのかもしれません。
恐るべし御三家、という感じですかね・・・。
【追記】 答案暗記法はなぜダメなのか
司法試験受験生で「絞り込み→暗記法」を使う方は、【再録】で書いたような絞り込み方をしてください。
絶対に、答案を繰り返し読むだけの単純暗記はしないようにお願いします。
その他の暗記型の試験では、基本的には本文に書いた暗記法で(たぶん)大丈夫だと思います。
司法試験において、読むだけの答案暗記法がなぜダメなのか。
それをきちんと論じるには、この狭いスペースではとても足りません。
実は、B5用紙で26枚も書いて中村さんにみせたことがあるのですが、今さらそれを整理する気力はありません。
それでも簡単に理由を述べておくと、司法試験における本当の答え(=答案)とは、教材として配布されている解答例や優秀答案のことではないからです。
↑以前、再現答案がゴールであると書いてしまったことがありますが、それは間違いです。
正確には、他人の再現答案は、その人のゴールではありません。
(これは重大な訂正です)
「全ての試験は読むだけで合格できる」と主張する人は、この司法試験の特殊性を知りません。
どうやら彼らにとっての答え(=正しい解答)とは、過去問集に印刷されている客観的な文字列を指しているようです。
普通の試験の答えは、このような高度の客観性を備えているので、過去問集の解答欄に書かれた答えを覚えて、それをそのまま試験会場で書けば、その人は合格することができます。
このような普通の試験であれば、普段の学習で受験生はそれらの「答え」を理解・記憶すればいいということになるのでしょう。
しかし、司法試験の「答え」はそうではありません。
一定の客観性はもちろんありますが、一方で、「これが唯一の解答です」と提示できるような、絶対的客観性をもった答えは、司法試験には存在しません。
もちろん、解答「例」ならいくらでも用意することはできるでしょう(ただし事後的にです←ここも重要です)。
しかしその場合でも、その通りに書かなかったら不合格になるわけではありません。
司法試験に本当の答えがあるとすれば、それは、
あなたが合格する年の論文試験会場で
あなた自身が実際に書くことになる合格答案
です。
その未来の答案こそが、あなたにとっての本当の答え(答案)です。
もちろん、そんな「答案」はまだ手元にありません。
そこで、仕方がないので、それに少しでも迫るものを、自分でコツコツ作っていくしかないのです。
「コツコツ作る」と書きましたが、これは、事前に論証例などを作成することとは違います。
司法試験が他の試験と異なるのは、知識以外の要素が評価に大きく影響するからです。
たとえば、適切な処理ができているか、妥当な結論を導けているか、全体のバランスを欠いていないかなど、具体的な問いに答える形でしか表現できないものを多分に含むのが司法試験です。
こういった諸々の要素全てを、知識としてではなく、経験として用意することが、「コツコツ作っていく」ということです。
司法試験において、
自力で問題を解き→その答案の欠陥を自分の目で確認し→より良い答案に育てていく
・・・という過程(繰り返し)が必要なのはそのためです。
ほとんどの試験では、答えは過去問集を買えばついてきます。
しかし、司法試験では、この育成過程の繰り返しを経なければ、あなたにとっての「本当の答え」は手に入らないのです。
たとえば、勉強1年目のあなたが、条文を片手に短い事例問題を自力で解いたとします。
その結果、なんとか5行の答案を作成することができたとします。
なんとか答案の体だけは成しているその5行答案こそが、あなたにとっての「本当の答え」(あなたが試験会場で書くことになる合格答案)に一番近いものです。
5行答案≒あなたにとっての「本当の答え」 です。
あなたが合格するために必要な合格答案(の姿)に一番近いのは、この5行答案です。
この5行答案以上に近いものは、残念ながら世界のどこにもありません。
優秀答案でもダメです。
優秀答案は、その答案を書いた人にとっての答え(最終解答)にすぎません。
優秀答案≠あなたにとっての「本当の答え」 なのです。
目の前に置かれた5行答案の延長線上にしか、あなたの合格(本当の答え)はありません。
この5行答案こそが、あなたが将来作成することになる、あなた自身の合格答案の“骨格”となってくれるのです。
そこからあなたがすべきことは、解答例を読むことでも優秀答案を覚えることでもありません。
あなたがすべきことは、解答例・優秀答案を参考に、あなたの骨格に肉付けをしていくことです。
5行答案を、その人格的固有性(答案スタイル)を保持したまま成長させることです。
そのためには、あなた自身が、その答案に主体的に関与し続けなければなりません。
あなたが、5行答案を育てるのです。
自分の答案を成長させるためには、この主体的関与が絶対必要です。
覚えるのが×で解かなければならないのは、そうしないと自分の答案が成長しないからです。
司法試験は、人によって答案スタイルがそれぞれ違います。
たとえば、短い文章を繋いでいく人もいれば、分厚い論述を好む人もいます。
ここで、前者のスタイルで答案を書いている人が、論点部分だけ予備校の論証を貼り付けたとしたら、論点部分だけが異様に浮き上がった(いかにもコイツ論証だけ覚えてきやがったなという感じの)極めてバランスの悪い答案が出来上がることになるでしょう。
なぜバランスが悪くなるのかというと、そこだけ他人の言葉(人格)が介在しているからです。
あれだけ長い問題文を相手にして、現場思考しながらあれだけ長い答案を書くのです。
どうやっても、答案の構造・流れ・表現etc…のほとんどは、自前の言葉(構造・流れ・表現)にならざるを得ません。
そこに突然、○○先生の論証例が挟み込まれたら、全体のバランスが崩れるのは当然です。
この「アンバランス」は、論点部分に留まらず、間違いなく答案全体に及ぶと私は確信しています。
答案は、それ自体が一つの纏まりをもったストーリーだからです。
他人の言葉(答案・論証・テキストのフレーズ等)を覚えて、それを自分の答案に貼り付けている限り、このアンバランスは克服できません。
司法試験では、知識的な正解は書けているのに、なぜか毎年不合格になる「実力者」がいます。
司法試験が今よりずっと難しかった頃には、このタイプの受験生が大量に存在していました。
彼らの答案は、ほとんど決まってどこかバランスの悪いものだったように思います。
このバランスの悪さによって、彼ら「実力者」たちは、毎年のように試験委員に「法曹の適格性なし」と判断されていた、というのが私の仮説です。
ここでいう「バランス」とは、論述の量のことだけを言っているのではありません。
より重要な「バランス」とは、条文を起点とした的確な処理手順や、利益衡量(妥当性)感覚などのことです。
これらを仮に「法的センス」と呼びます。
旧司時代は、この「法的センス」が何なのかが盛んに議論されていました。
そういった文字化できないスキルのようなものがなければ最終合格はできない、と多くの受験生が感じていたからです。
現在では、多少バランスの悪い(=法的センスを欠いたような)答案を書いても、多くの人が受かるようになりました。
実際、私の周りにいた旧司組の「実力者」たちも、新司に移行したのち、皆さん比較的すんなりと合格しました。
そのように時代が変化したからでしょうか、法的センスをめぐる議論は、以前に比べてずっと下火になった感があります。
もっとも、それは、法的センスを多少欠いた答案でも、十分に受かる時代になったというだけの話です。
法的センスの有無は、今でも(むしろ今だからこそ)、重大な加点自由になっているはずです。
(法的センスがあまりなくても受かるのですから、それがあれば余裕で受かると考えていいでしょう)
バランスの良い答案を書くのは、それほど難しいことではありません。
自分の骨格に合わせて、自力で答案を育てていけばいいのです。
他人(出題趣旨など)の力を借りるのはいいですが、それは答案を書くとき以外の話です。
たとえば、復習(添削・修正)の際に、優秀答案など他人の力を借りるのは必要なことです。
しかし、自分の答案は、最初から最後まで、自分自身が自力で育てなければなりません。
バランスが悪くなるのは、他人の論証や答案を、自分の答案の中に無理に介在させるからです。
端的にいえば、他人の答案を覚えて吐き出すような勉強をしているからです。
他人の答案を勉強の中心に据えることさえここまでズレているのですから、テキスト学習なんて論外だと分かるでしょう。
そういったマイナス要因から離れて、自力で答案を育てていくという方針をとれば、バランスの良い答案を書くことはそれほど難しいことではないと私は思います。
司法試験を単純知識型試験と同一視し、「答案の暗記で合格答案が書けようになる」と主張することが誤りなのは、これまで述べてきたとおり、司法試験における真の合格答案とは、自分で作成しなければならないものだからなのです。
一方で、単純知識型試験と司法試験を同一視してしまう(2つの試験の差異に気づけない)人たちがいるのは、彼らが、試験(目的そのもの)を見るよりも、対処法(方法論)を主張することを重視してしまっているからです。
言いかえると、目的の試験を見る前に、対処法を先に決めてしまうからです。
彼らは、司法試験の特性を繊細に捉えることなく、すでに築き上げられた単純知識型試験の対処法(方法論)の有効性を誇示することに一生懸命になってしまっています。
このとき、彼らは目的を見ていません。
手元(方法論)を必死に凝視(誇示)するとき、彼らの目は目的から逸れてしまっています。
突然ですが、私は自分の方法論を、過去問主義という言い方以上に広げたくないと思っています。
それは、まずは目的をしっかりと見ることが大事だと思うからです。
目的をしっかりと見る前に、具体的な方法を先に決めてしまうと、人は必ず目的を見なくなります。
過去問主義とは、目的をよく見ることです。
具体的な方法をどうするかは、目的をよく見たあとで、その目的に則して考えます。
これが本当の意味での過去問主義です。
したがって、たとえばある方法論が、過去問の暗記を謳い文句にしているのであれば、その方法論は過去問主義ではなく、正しく暗記主義と呼ばれるべきでしょう。
過去問の取り扱い方法が最初から「暗記」と決まっているのなら、それは過去問主義の最も美味しい核の部分を食べずに捨ててしまっているという意味で、どうやっても「過去問主義」とは呼べないからです。
そのような方法論の本旨は、あくまでも暗記のほうにある、といえるでしょう。
このように、たとえ過去問を使用するのだとしても、その使い方があらかじめ
「過去問を○○すること」
と決まっているのだとしたら、その方法論は本質的には過去問主義ではありません。
つまり、
 過去問を読めば合格します
過去問を読めば合格します
 過去問を理解すれば合格します
過去問を理解すれば合格します
 過去問を真似すれば合格します
過去問を真似すれば合格します
 過去問を覚えれば合格します etc…
過去問を覚えれば合格します etc…
↑このような「方法論」は、本当の意味での過去問主義とは呼べないのです。
過去問主義もまた一つの方法論ですが、その他のあらゆる方法論とは、何もかもが違います。
・本当の過去問主義は、あらかじめ何も決めません。
・過去問をどう扱うかさえ、あらかじめ何も決めません。
・すべては、相手を見てから決めるのです。
この、相手(目的)を繊細に見ようとする態度をこそ、皆さんには大切にしてもらいたいです。