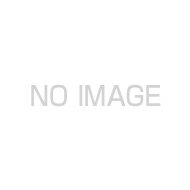ザンデルリンクと
スイトナーの共演
曲目/
A面
録音/1960/12/12-16 ルカ教会、ドレスデン
P:ヴォルフガング・ローゼ
E:ハインリヒ・カイルホルツ
B面
録音/1968/11/7 ルカ教会、ドレスデン
P:ゲルハルト・ディーター・ヴォルム
E:クラウス・シュトリーベン
DGG MGW 5254 (原盤 東独エテルナ)
多分ほとんど市場に出回らなかった一枚ではないでしょうか。グラモフォンは市場に廉価版が溢れていた時期の1981年の4月にこれらのレコードを発売しています。フリッチャイやクーベリックの初期の録音なんかを投入していたり、1970年台のティルソン・トーマスの「春の祭典」スタインバーグの「ツァラトゥストラはかく語りき」、さらにはデュトワの「ペトルーシカ」なんかも含まれてはいましたが、一方ではアーサー・フィードラー/ボストン・ポップスのポピュラーものも含んでいるなど内容はバラバラのシリーズでした。そんな中にこの一枚が含まれていました。
ザンデルリンクとスイトナーが一枚のLPに混載されているのはこの日本盤しかありません。もともとのザンデルリンクはA面のボロディンの「中央アジアの草原にて」とチャイコフスキーの「ロメオとジュリエット」それにB面にポロディンの交響曲第2番がオリジナルでした。それがこのレコードではスイトナーの「弦楽セレナード」に差し替えられて収録されています。
最初はポロディンの「中央アジアの草原にて」です。作曲者のアレクサンドル・ボロディン(1833~1887)は、モスクワあたりの生粋のロシア人ではなく、グルジア(ジョージア)あたりの中央アジアの血筋を引いていたとのことです。中世以前から、農業中心のウクライナあたりでは、騎馬民族がしばしばやってきて穀物を略奪していきました。その最大のものがモンゴル帝国の支配です。そんなわけで中央アジアはボロディンにとっては自分のルーツなのです。実はそういうロシア人は沢山います。この曲は中央アジアに対するエキゾチックな魅力と共に、哀愁に満ちています。この曲は、1880年にサンクト・ペテルブルグで初演されました。
ザンデルリンクはこの時代まだSKDとは緊密な仕事をしていたわけではないのですが、曲調に呼応するかのようにエネルギッシュな音が眼前に迫ってきます、まさに迫真の演奏を感じられると思います。ドイツのオケ、しかもどちらかと言えば繊細な音色で定評があるSKDからここまでの音色を引き出すザンデルリングの手腕は見事で、むしろ現代では失われたロシアの響きが聴こえるのは驚きです。演奏はインテンポで揺るぎない音楽の足取りが中央アジアの広大さを表現していて、ロシア的な強靭さと爆発力、ドイツのオケの重心の低さとレベルの高さを今更ながら実感することができるでしょう。近代的なオーケストラ配置の録音でホルンの響きはやや左手奥から朗々と響きます。
2曲目はチャイコフスキーの「ロメオとジュリエット」です。幻想序曲と題されているようにチャイコフスキーはシェイクスピアの作品による作品はすべて幻想序曲というタイトルがついています。「ハムレット」然り、「テンペスト」然りです。
ザンデルリンクはドイツの指揮者ですが、1937年にモスクワでモーツァルトの歌劇『後宮からの誘拐』を指揮してデビューし、1939年にはハリコフ・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者に就任、1941年にレニングラート・フィルハーモニー交響楽団の第一指揮者に就き、エフゲニー・ムラヴィンスキーの弟子になっています。そのためか、自らの美意識を貫き、演奏に関して妥協を許さない、エネルギーの凝縮感があります。個人的にはどっしりとしたフィルハーモニア管弦楽団とのベートーヴェンの交響曲全集はデジタル初期の名演と思っています。
ただ、ザンデルリンクはムラヴィンスキーより旋律に対してより大きな呼吸を持って、たっぷり歌おうとしますので、音楽が大きく感じられますよね。ただこの演奏録音がイマイチなのが残念なところです。
これに対してB面の水トナーの弦楽セレナーデは録音も8年ほど新しいこともあり、実にみずみずしい音と分厚いフルオーケストラの左右角が火匹渡ります。同じ会場での録音ですが録音スタッフも違うこともあり、素晴らしいサウンドがホール一杯に響きわたています。録音は名技師クラウス・シュトリューベン(Claus Struben)氏で、非常に高音質です。エテルナのトーンエンジニアではホルスト・クンツェ(Horst Kunze)氏もなかなか良い録音をしますが、シュトリューベン氏の録音はピントがバツグンにはっきりとしています。ルカ教会&シュトリューベン氏の録音にはハズレなし!と言う印象すら受けます。
そして肝心の演奏ですが、美しい!美しすぎます!シュターツカペレ・ドレスデンの弦楽セクションの奏でる音色のあまりの美しさ、一糸乱れぬ音と音の交差を前に、この演奏を前にして、ただただ耳と心で流れる音楽を聴くことに集中するしかできませんでした。スイトナーのチャイコフスキーはオリジナルはフォルクマンの弦楽セレナードとのカップリングでした。ただ、こちらはほとんど知られていませんからこういうカップリングになったのでしょう。不思議なことにすいとなーのチャイコフスキーはこの弦楽セレナーデしか見つかりません。もったいないことです。スイトナーと言えばやはりモーツァルトの録音が有名ですが、音の美しさではこちらに分があると思います。