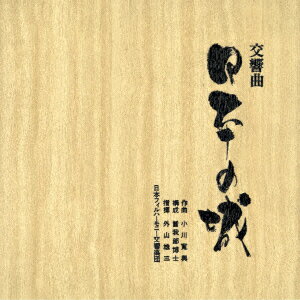現代日本の音楽名盤1300
交響曲「日本の城」
曲目/
小川寛興/交響曲「日本の城」
1.第1楽章 き(築城) 7:30
2.第2楽章 天守の城 8:13
3.第3楽章 戦いの城 4:53
4.第4楽章 炎の城 7:25
5.第5楽章 不滅の城 7:53
指揮/外山雄三
演奏/日本フィルハーモニー交響楽団、和楽合奏団
キング混声合唱団
龍笛:薗武史(独奏)、東儀文隆ほか、
雅楽琵琶:薗広茂、薩摩琵琶:水藤錦穣、
尺八:横山勝也、箏:後藤すみ子、矢崎明子、十七弦箏:菊池悌子、
小鼓:堅田喜三久、大鼓:堅田啓光、法螺貝:園田芳龍、胡弓:荒川マリ子
録音/1968.07 東京厚生年金ホール
キング GT−9331
元盤 SKLB-12317-1
SKLB-12318-2
1970年代、廉価版に最も力を入れていたのは日本コロムビアとキングレコードでした。両社とも自社の契約するレーベルをフル動員してユニークな企画をどんどん廉価版に投入していました。この「現代日本の音楽名盤1300シリーズ」はそんなキングが投入したトンがった規格のものでした。全20枚のシリーズで限定盤でしたからあっという間に市場からは消えてしまいました。小生もかなり集めたのですが、1990年代にほとんどオークションで処分してしまいました。ただ、この一枚だけは「城」をテーマにした交響曲ということもあり手元に残しておきました。
この作品は明治百年記念芸術祭参加作品として昭和43年にキングレコードの企画により委嘱されたものです。キングレコードには名物プロデューサーの長田 暁二さんがいてこういう企画の陣頭指揮をしていたのを思い出します。ただね発売された当時現代音楽と言いながら歌謡長のテーマが仇となり、評論家からは酷評されたのを覚えています。このレコードは1980年の1月から2月にかけて発売されたものですが、この時のレコ芸の批評でもシリーズの他のレコードは絶賛されていたのにこの曲だけは批評の対象にも登らず無視されたのを今でも覚えています。そういう、アカデミックな狭い心しか持たない批評家連中に唖然としたのを覚えています。
ところで、この曲を作曲した「小川寛興」という名前をご存知の方はどれくらいいるでしょう。ある年代(以上)の日本人の多くが、知らず知らずのうちに、小川氏の作品に親しんでいたという事実は、その名を検索にかけて調べてみればすぐにわかる。昭和40年代前半を中心に、TV番組の主題歌や当時の歌謡曲の分野で、かなりの数の有名作を放っておられるからだ。簡単に確認できるものとして、実写ドラマからは『月光仮面』『快傑ハリマオ』『仮面の忍者・赤影』、そしてNHKの『おはなはん』等。アニメでは『花のぴゅんぴゅん丸』の主題歌が、小川先生によって書かれている。歌謡曲のヒット作としては、倍賞千恵子が歌った「さよならはダンスの後に」や、中村晃子が歌った「虹色の湖」などがあります。特に『快傑ハリマオ』などはテーマ曲を三橋道也が歌っており、びっくりしたものです。
そんな日本のメロディメーカーが作曲したこの曲、親しみやすく日本情緒がたっぷり楽しめる。素晴らしい和楽器コンチェルトに仕上がっています。昨今のお城ブームの波には乗り切っていない曲ですが、もっと知られてもいい作品ですし、調べてみても「城」を描いたクラシックの作品はほとんどないことに驚愕します。
キングレコードといえばレーベルは濃いエンジ色が特徴ですが、このシリーズは独自のブルーが使われていて当時は新鮮に感じたものです。
演奏人もすごいメンバーが集まっています。そして、自らも作曲家であった外山雄三氏もこの作品の価値を認めて指揮を務めたのでしょう。これだけのメンバーを必要としますからそうそう簡単にコンサートの演目にも上がらないでしょうから幻の作品と言われてもしょうがないのかもしれません。企画に際しては、外国人が日本のクラシック音楽に何を期待するかに配慮しつつ、日本的素材を用いながら前衛性を避け、しかも芸術性は失わないようにすることに腐心したといいます。それだけのことはあって、管弦楽に編入された邦楽器のオンパレードに加え、城の誕生から落城を物語風に描き最後は城への賛歌で終わるという、真に標題から期待される通りの音楽となっています。作品は交響曲の形をとりながら第1~4楽章はそれぞれ異なる邦楽器をソリスティックに扱い、協奏曲風に仕立てられています。
第1楽章 「き(築城)」(箏)
城の建築と町の人々の高揚感を描く意気揚揚とした音楽です。出だしは竜笛の渋い音色で開始されますが、やがて筝(琴ではありません)が飛び跳ねるように景気の良いリズムを奏で始めると、もうノリノリ。まさに箏協奏曲という風情です。ただ、曲は唐突に終わってしまうのにはちょっとびっくりです。
第2楽章 「天守の城」
城に暗雲が立ち込めるかのような尺八に導かれる不安気な音楽です。城下町を見下ろす天守閣。―というのだが、曲はむしろ「はかなさ」とか「もののあはれ」みたいな情趣を漂わせるものになっています。後半に活用される尺八の“むら息”が印象的です。
第3楽章 「戦いの城」
スケルツォを思わせるせわしない弦の運動を中心とした急速なテンポで描かれます。ここでは戦(いくさ)の開始でが描かれます。竜笛が歌う第2主題は、いかにもTVや映画の音楽を手がけてきた小川氏らしい、非常に分かりやすい音楽です。そのまんま大河風の時代劇にも使えそうです。まあ、NHKは権威主義の塊ですから小川氏が使われることはなかったでしょうなぁ。まここでは、能楽等で使われる鼓(つづみ)も登場して城を巡る攻防戦を法螺貝まで登場してなかなかドラマチックな音楽なっています。
第4楽章 「炎の城」(琵琶・胡弓)
続く楽章では炎に包まれ落城していく城の無常感を描く語り物のような音楽になっています。薩摩琵琶が激しく乱れてかき鳴らされ、本丸の炎上を告げるかのように描かれます。さらに、焼け落ちた城跡に鳴り響く胡弓のわびしい音色も聴きものです。非常にドラマチックで、この後に荘重な合唱がヴォカリーズで歌われます。
第5楽章 「不滅の城」
最後はやはりポジティヴに締めくくる、ということであろう。力強いファンファーレから、前の楽章よりもさらに充実した合唱が続き、弦が広々とした主題を歌います。胡弓や筝が登場した後は、行進曲風の楽想に入って盛り上がる。「日本人の心の城は、永遠に不滅です」というところか。そして最後は、竜笛と筝が静かに“わび・さび”の境地を歌って静かに終わっていきます。西洋の作品のようにコーダで壮大に締めくくるのではなく侘び寂びの世界で締めくくるあたりはとても日本的でいいですなぁ。
これからはCDの時代だと言ってレコードを処分しましたが全部処分せずに残しておいてよかったと感じる一枚です。