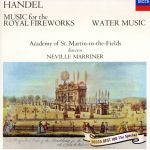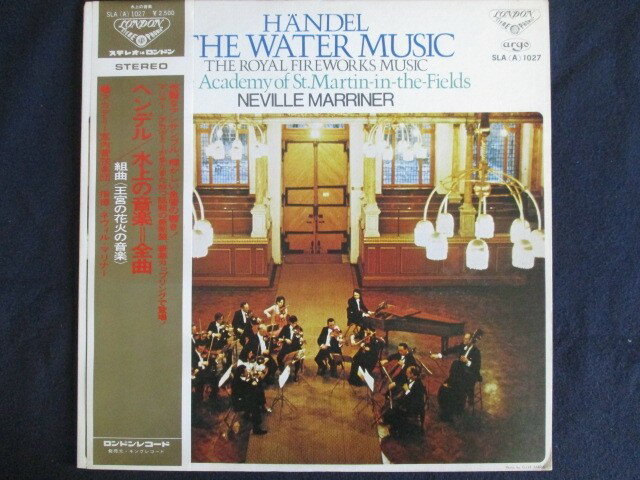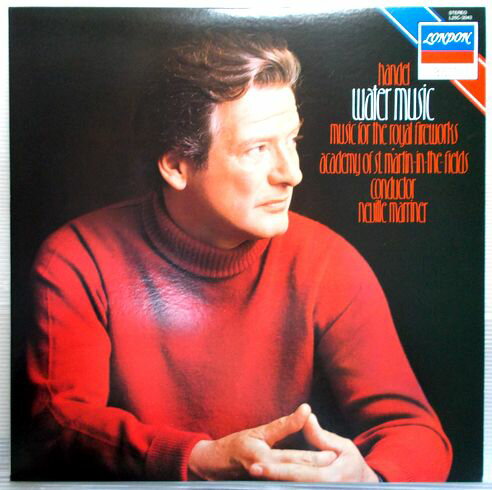マリナー最初の水上の音楽、王宮の花火の音楽
曲目/ヘンデル
1.組曲「王宮の花火の音楽」 17:07
水上の音楽 全曲
2.組曲ト長調 8:29
3.組曲ニ長調 9:28
4.組曲へ長調 26:10
ハープシコード・コンテイヌオ コーリン・ティルニー
指揮/ネヴィル・マリナー
演奏/アカデミー室内管弦楽団
録音/1971/05 キングスウェイ・ホール
P:マイケル・ブレムナー
E:スタンレー・グッダール
LONDON L25C−0343 (原盤ARGO)
zrg3583A 50ED DCA3162 ZRG3584
これはマリナー/アカデミーの1971年の最初の録音です。1今回このレコードをとりあげるにあたり調べてみて初めて分かったことですが、マリナーはこの後このコンビで1979年にフィリップスに、そしてデジタル時代になった1988年に今度はEMIにも録音しています。さらに1993年にもヘンスラーにも録音しています。古楽器による演奏が台頭していた中で同一曲をレーベルを横断して4度も録音したのはマリナー、アカデミー以外は無いでしょう。まさに引く手数多の活躍で4レーベルに録音を残していることになります。
最初は有名な、バロック音楽の定番曲、ヘンデルの「王宮の花火の音楽」です。歴史と密接な関係がありますからちょいと背景を探ります。時代は、ジョージ1世の息子、ジョージ2世の御代です。スチュアート朝がアン女王で断絶し、女系の血縁によってドイツから迎えられたハノーヴァー朝の国王たちは、もともとがドイツ人で、英語もろくに話せませんでした。政治にも無関心だったため、英国で議会制民主主義が発達した、というのは有名な話です。そんな国王には国民も無関心でした。当時の国民にとっては、国王など誰でもよかったのです。女系継承で君主が国民の支持を得るのは、歴史的には並大抵のことではないのです。
そんな折、英国は、これも国民のほとんど関心のない戦争を戦っていました。これまでも何回か触れたオーストリア継承戦争(1740-48)です。ほとんどの国民は、国が誰を相手に、何のために戦っているのか、理解していませんでした。そんな中、自ら出陣したジョージ2世が、大砲の音に驚いた乗馬が敵中に走りこんだお陰で、戦いに勝利します。デッティンゲンの戦いです。これには英国民は狂喜し、ジョージ2世は初めて、人気者となることができました。それもあって一大イベントを開催することにし、グリーン・パークに建設された建物で盛大に祝うことにします。その式典で演奏されたのがこの「王宮の花火の音楽」ということになります。野外ですから管楽器中心の編成での演奏会となり、リハーサルでは12,000人もの聴衆を集めて大盛況だったようです。
曲は、
序曲(Ouverture, ニ長調)
ブレー(Bourée, ニ短調)
平和(La paix, ニ長調)
歓喜(La réjouissance, ニ長調)
メヌエットI(Minuet, ニ短調) - メヌエットII(ニ長調
で構成され、100名程度で演奏されたようですが、ここでは通常のオーケストラ程度の編成で演奏されています。まあ、アカデミー室内管弦楽団は日本では室内管弦楽団と呼ばれていますが、実際は「Academy of St Martin in the Fields」ということで室内楽を標榜しているわけではありません。曲によって十何二編成を変えることができるのもこのオーケストラの特徴とも言えます。そんなことで、この「王宮の花火の音楽無の方が編成が大きく聴き映えがします。第1曲はフランス風の序曲の形をとっていて、荘厳な序奏からはまりますがマリナーの演奏は奇を衒わず中庸なテンポで演奏していきます。そこにはピリオド楽器の鮮烈な響きはありませんからイギリスの聴衆には受け入れられやすかったのでしょうなぁ。
ヘンデルはドイツのハレで生まれ、若くしてイタリアに留学、名声を得て、ドイツのハノーヴァー選帝侯の宮廷楽長となりました。しかし、実際にはイギリスに帰化した国際人であり、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルではなく、ジョージ・フリデリック・ハンデルと呼んだ方が正しいのでしょう。そんなことで、英国人として亡くなり、栄光のうちにウェストミンスター寺院に葬られています。
さて、「水上の音楽」はそれよりも古い時代の音楽です。こちらは1715年のテムズ川でのイギリス国王の舟遊びの際にこの曲を演奏した、というエピソードが一般的には有名です。つまりはジョージ2世の前のジョージ1世の時代ということになります。
ヘンデルは、1710年にドイツのハノーファー選帝侯の宮廷楽長に就いていたが、1712年以降、帰国命令に従わず外遊先のロンドンに定住していました。ところが、1714年にそのハノーファー選帝侯がイギリス王ジョージ1世として迎えられることになります。ということで、ヘンデルが王との和解を図るため、1715年のテムズ川での王の舟遊びの際にこの曲を演奏した、というエピソードになるわけですが、今では否定されているようです。まあ、舟遊びで演奏されたというのは間違い無いでしょう。
この71年録音はライナーにマリナーの言葉が掲載されていて、ケンブリッジの図書館の協力を得て独自の考察を経た解釈を行なっていることが書かれています。3つの組曲からなることに変わりはないのですが、曲の配列は第3組曲が最初に演奏されています。入れ替えがなされていハレ版をベースにマリナー独自のものを採用したと書かれています。マリナーの指揮する小型のノーブルなスタイルは壮麗な屋外音楽である「水上の音楽」の力感とは趣きが違います。レコードではA面に「王宮の花火の音楽」に続き「水上の音楽」の組曲を小さい第3組曲が収録されていて、組曲ト長調から開始されています。
オリジナルの管弦楽曲は一旦遺失していますが、新ヘンデル全集のハレ版(25曲)は、これらを元に管弦楽に復元したものです。他にも管弦楽復元版が数種類存在し、20曲からなるF.クリュザンダー版、6曲からなるH.ハーティ版が知られています。
マリナーの演奏は当然に現代楽器による通常の奏法ではあり、打楽器が使われずシンプルで小気味よいサウンドになっていて、文字通りさわやかさの極地と言ってもいいでしょう。ジャケットにはわざわざコンティヌオ奏者としてコーリン・ティルニーの名前がクレジットされています。1970年代という時代を読んだ堅実な演奏なんでしょうなぁ。当時はパイヤールもこういうスタイルでしたから時代のニーズでもあったわけです。ただ、イギリスではホグウッとやピノック、ガーディナーなどが鎬を削っていた中でマリナー/アカデミーの演奏が繰り返し録音されていたとは今回一番驚いた点です。
この最初の録音がビートルズ末期のイギリスに受け入れられたということは、イギリスの伝統を感じさせざるを得ません。