オランダで最初に安楽死の世論を動かしたのは、1971年の『ポストマ事件』です。これは女性医師のヘルトルイダ・ポストマが、脳出血に苦しむ78歳の母親に、致死量のモルヒネを注射して安楽死させた事件です。ポストマ医師は、母親の死の求めを再三拒否していましたが、母親がベットから転落して自殺を試みたり、食事を床に投げ捨てたりして死を求める姿にいたたまれなくなり、ついに安楽死を決意したのです。彼女は殺人罪で起訴されましたが、マスコミがこの事件を報じると、自分も安楽死を行ったと告白する医師や、安楽死の容認を訴える法律家が現れ、また彼女の診療を受けていた地元の住民が、ポストマ医師の救援活動を活発に行なった結果、判決は執行猶予付きの懲役1週間という無罪同然のものになったのです。
この事件をきっかけに、73年、オランダに『自発的安楽死協会』が発足します。連立政権の安楽死反対派は、政府判断を先送りする狙いで、見解の異なる委員による『国家安楽死委員会』を設置しますが、思わぬ事件が起こって、逆にこの委員会が、安楽死の合法化を加速させることになってしまいます。それが82年の『スホーンヘイム裁判』です。
(中略)
この事件は、開業医のスホーンヘイムが、95歳の女性を安楽死させたものです。この医師もやはり起訴されましたが、地裁、高裁、最高裁で判決が二転三転し、国民注視の中、最終的に無罪判決が出ました。これで世論はさらに安楽死肯定に傾き、『国家安楽死委員会』は85年、安楽死の法制化を求める報告書を政府に提出せざるを得なくなるのです。同年、司法省は要件を満たす安楽死は不起訴にする方針を発表し、90年には政府が王立医師会と協力して、安楽死の届出制度を開始します。これらの動きにより、安楽死はオランダの社会に定着していったのです。
(中略)
94年、さらに新たな事件が起こります。それまで肉体的な苦痛にしか認められなかった安楽死を、精神的苦痛にも認めることになる『シャボット事件』です。これは二人の息子に先立たれ、生きる望みを失った50歳の女性を、シャボット医師が安楽死させた事件ですが、最高裁はシャボット医師に有罪ながら刑罰なしの判決を下します。これにより、安楽死は病気の有無を問わず、本人の自発的意思のみで認められる空気が高まったのです。98年、安楽死の合法化を掲げる与党が選挙で圧勝し、翌年、政府は安楽死法案を国会に提出しました。そして2001年4月、ついに国として世界初の安楽死法が、オランダ国会で成立するのです。
久坂部羊「神の手」
スイス住民投票で安楽死の維持決定、「自殺ツーリズム」も継続へ
>安楽死の禁止に賛成票を投じたのはわずか15.5%。外国人の安楽死受け入れを禁止すべきとした人も約22%にとどまった。スイスでは1941年、医師以外で利害関係のない人の手による自殺ほう助を認めており、チューリヒでは毎年200人近くが自らの意思で命を絶っている。世界で最も進歩的とされるスイスの安楽死制度を利用するため、外国人の末期患者がスイスを訪れる「自殺ツーリズム」が多く行われている。(2011年 05月 16日 12:32 JST)
「進歩的」という言葉が使用されていることに違和感を感じるか否かがこの問題に対するスタンスをも決めることでしょう(ツーリズムというのも皮肉といえば皮肉か)。始まりは決められずとも終わりについては「自由」があるべきと考えるか、一定の規制や制限があってしかるべきと考えるか、共同体的あるいは宗教的な考えから禁忌とすべきか…ね。
ワタミ介護、2年で40施設新設
>13年2月末までに100施設を超える見通しだ。現在は首都圏を中心に展開しているが、今年度は住宅型有料老人ホームしかない大阪府と、未開設の愛知県にも1施設ずつ開設する。また、入居一時金を300万円台に抑えた有料老人ホームを開設する方針を明らかにした。
スイスの安楽死とワタミの介護を並べたのはどちらがましかという選択を迫るような意図的なものではないのですよ(苦笑)
>同社が同日発表した今年3月期通期の連結決算によると、介護事業の売上高は222億円(前期比27.4%増)、営業利益は37億8000万円(同40.9%増)だった。来年3月期の業績は、売上高290億円(同30.2%増)、営業利益46億6000万円(同23.3%増)を計画している。
コスト=ほぼ人件費という構図の介護事業で、これだけの利益をあげられるなんてきっとワタミでは夢のようなビジネスモデルを築いたんですね(一時金の先食いだけでは決して無いはず><)。
>高齢者向けの弁当宅配事業の業績は、売上高が154億円(同53.3%増)、営業利益が14億1000万円(同76.6%増)だった。今年2月末時点の1日当たり配食数は11万
8000食で、前年の6万1000食から倍増した。
>来年2月末時点の1日当たり配食数は、1.6倍の19万4000食を目指す。来年3月期の業績は、売上高248億円(同60.1%増)、営業利益18億7000万円(同32.9%増)を見込んでいる。(医療介護CBニュース 5月10日)
以前、テレビでこの事業の従事者を「まごころさん」と呼んでいるのを見てそのあまりの麗しい光景に身震いがとまりませんでしたよ。
武田薬品:スイス大手買収へ 1兆円超で最終調整
>国内製薬会社による企業買収では過去最大で、日本企業による外国企業の合併・買収(M&A)では3位に入る規模となる。武田薬品の売上高は世界の製薬メーカーで13位、ナイコメッドは28位で、今回の買収で武田薬品は世界10位前後に浮上するとみられる。ナイコメッドは1874年の創業で、欧州はじめ世界100カ国で胃腸薬や骨粗しょう症薬などの医薬品を販売。近年はロシア、ブラジル、アジアなど新興国市場に積極参入している。10年12月期の売上高は約32億ユーロ(約3700億円)。
アステラス製薬のインド製薬会社5000億で買収とか見ると、三角合併の際に製薬業界がよく例に出されて外資との時価総額の差から買収される脅威を煽っていたのは何だったのかと。
>調査会社「レコフ」によると、1兆円を超える日本企業の外資買収は、日本たばこ産業の英ギャラハー買収(07年、2兆2530億円)、ソフトバンクによるボーダフォン日本法人の買収(06年、1兆9172億円)に次ぐ規模になる。武田薬品の11年3月期の売上高は1兆4193億円。今回は自己資金や社債発行などで資金調達する見込み。円高の進行で、買収額を抑えられることも今回の買収を後押ししたとみられる。(毎日新聞 2011年5月12日)
このうち最大の日本たばこの買収の成果はどうなっているんでしょうね。JTについては全く情報を照覧していないのでわかりまへん。
ムーディーズとS&P、武田薬品の格下げ検討
>格付け会社のムーディーズ・ジャパンとスタンダード&プアーズ(S&P)は19日、武田薬品工業の格付けを引き下げる方向で見直す、と発表した。武田がスイス製薬大手ナイコメッドの買収で6千億~7千億円程度を借り入れることにより、財務の健全性が低下する、としている。現在の格付けは、ムーディーズが「Aa1」(上から2番目)、S&Pが「AA」(上から3番目)。(朝日新聞 2011年5月19日)
財務の健全性が低下って…これまでが無借金に近かったわけですから投資活動に積極的にうってでるのはむしろ高評価すべきでしょう。格付け会社の評価基準は相変わらずうさんくさいね。
イスラエルの製薬会社、大洋薬品を買収…後発薬最大手
>ジェネリック医薬品(後発薬)の世界最大手、イスラエルのテバファーマスーティカル・インダストリーズは16日、国内3位の大洋薬品工業(名古屋市)の株式の約57%を約370億円で取得し買収することで合意したと発表した。最終的には全株式の取得を目指す。
武田薬品にしても国内市場の少子高齢化による行き詰まりが目に見えている以上(人口減少というだけでなく、高齢化による医療費抑制のためのジェネリック推奨)、海外に積極的に打って出ざるをえないだけのこと。
>テバ社は世界の60カ国に拠点があり、2010年の売上高は約161億ドル(約1兆3千億円)。日本では医薬品の興和(名古屋市)と合弁会社を設立している。[東京新聞 11/05/16]
と言いつつも国内でのジェネリック医薬品の普及はあまり加速しませんね。厚労省が鞭を振るうのは間違いないと見ているのですが。
オランダの安楽死法成立の過程には、節目節目に大きな事件が発生しています。それによって世論が喚起され、政治が動いて、法制化へと収束していったのです。オランダはパイオニアですから、時間がかかりましたが、日本が同じような過程をたどる必要はありません。オランダという成功モデルがあるのですから、やりようによっては一気呵成に法制定までもっていくことも可能だと思います。
久坂部羊「神の手」
- 神の手(上)/久坂部 羊

- ¥1,890
- Amazon.co.jp
- 神の手(下)/久坂部 羊
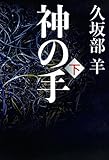
- ¥1,890
- Amazon.co.jp
- ▲これぞ久坂部医師と読みながら両手叩いて大喜びしながら最後まで一挙に読み上げました。Amazonレビューも既に書いてますが、久坂部医師の日本国を蝕む病魔に対する悪魔の処方箋については是非とも参照あれ。政治家、官僚、医師、マスコミ、患者、医薬品メーカーと彼らの間でかわされる虚々実々のやりとりは少なくとも厚労官僚は必読と思われます(笑)。