133 名前:山師さん@トレード中[] 投稿日:2010/01/19(火) 18:44:49 ID:9PZF3P8k0
今日のJAL機内のNHKニュースどうするんだ?
JAL機内でJALの会社更生法申請のニュース流すとかいうギャグを実行するのか?
しかし、民主党はアホだね~普通に可視化、検察審査会、判検交流、国賠法などなど司法制度改革を通して検察と対決すればいいのに。しかし、二大政党制の下、民主党と検察の間で緊張感溢れるやりとりが交わされていますってあれ???
2009-01-18
は伝説のEVAで温暖化を騙った朝日新聞渾身の社説。その破壊力たるや、未だ未読の方は是非一読あれかし。
2009-01-19 は気が付けば結構メモしている混雑ネタ。フレックスタイム制度っていまや死語?
「温室ガス削減もう無理」鉄鋼・電力業界が予防線
>鉄鋼連盟が11月下旬、20年時点で500万トン減らすという独自の二酸化炭素(CO2)削減目標を発表。500万トンは日本の鉄鋼業界が排出するCO2約1億8千万トン(08年度)のわずか2.8%で、鳩山政権に対して「削減できない」と宣言した形だ。さらに鉄鋼連盟や電事連など9団体で、京都議定書の暫定延長などに反対する文書を作り、政官界への働きかけを強めていた。
まあ、めでたく中国様の奮闘でCOP微塵になったからいいけれど…。
>COP15開催中の今月15日には日本経団連として、20年のCO2削減目標を各業種自らが公表・実施するとした「低炭素社会実行計画」を発表。「最大限の目標水準であることを対外的に説明する」としているが、従来の自主行動計画の延長に近い。日本のCO2排出量の約8割は企業・公共部門で、家庭からは約2割にすぎない。環境NGO「気候ネットワーク」は電力・鉄鋼を中心にした161の発電所・工場が日本の排出の5割を占めるとし、「経団連の『自主行動』まかせでは25%削減はおろか、50年までの目標の80%削減につながらない。強制参加の排出量取引制度の導入が不可欠だ」とする。 (朝日新聞2009年12月24日1時1分)
渡辺正教授が再三再四指摘していた通り、企業活動が鈍ればCO2排出量が減ることも、今回の不況で実証できたし(しかも稲作もだめとなると)、原発推進論者か、ディープエコロジストでもない限り、少なくとも現時点で温暖化言説へのスタンスなんて答えは一つじゃないのかね?
温暖化コストはハウマッチ?
>温室効果ガスの排出を規制しなければ、温暖化のコストは国民1人当たり年間収入の2割に達する可能性がある。そう主張するのはイギリスの経済学者で、英政府の支援の下、温暖化が世界経済に与える影響を考察した報告書「スターン・レビュー」(06年)を手掛けたニコラス・スターンだ。実に恐ろしい予測ではないか。生活水準がそこまで下がるのは歴史上例がない。しかし、パニックに陥るのはまだ早い。
温暖化対策に勤しんだ結果、経済が壊滅した時の社会コストはHow much?
>米エール大学の経済学教授ウィリアム・ノードハウスによれば、温暖化コストは世界の年間GDP(国内総生産)総額の2.5%という線が有力。大変な数字ではあるが、破滅的とはいえない。オランダの経済学者リシャルト・トルに至っては、100年分の気候変動が経済に与える影響は「比較的小規模」で、「1~2年分の経済成長の規模と同等」と言う。三者三様の予測の数字はあまりに異なる。
そもそもがシミュレーションが千差万別で何度上がるのかすら、分からないのですが、そのコストについての試算も割引率によってこんだけ異なりますよと。
>06年のスターン・レビューでは割引率を0.1%に設定しているが、多くの専門家に言わせれば、これはあまりに低過ぎる。この数字のとおりなら、私たちは遠い未来に生まれるかもしれない孫の孫の生活を、わが子の将来と同じくらい気に掛けていることになる。スターン・レビューは、トルの言葉を借りれば「疑似科学の誇張の最たるもの」。スターンは科学ではなく、環境問題を重視するトニー・ブレア英首相(当時)の意向に基づいて割引率を決めたという批判の声も上がっている。意図的に数字を選んでいる点では、反対陣営も変わらない。自称「懐疑的環境保護主義者」であるデンマークの統計学者ビョルン・ロンボルグが率いるシンクタンクは、複数の著名な気候変動専門家に温暖化コストの算定を委託。その1つを手掛けたある研究チームは、割引率を5%に設定した。[NEWSWEEK 2009年12月16日]
割引率0.1%と5%のいずれが常識的な数字と考えるかは皆様でお考えくださいというと、日本の場合、ゼロ金利社会なので普通に銀行預金程度でしか運用していないとピンと来ないかもね。
ビョルン・ロンボルグ 特別寄稿 「意志の力」と「政治的合意」で気候変動と戦えるという“誤解”
>恐ろしく馬鹿げた事実なのだが、CO2削減という大義を推進していくための根拠とされている研究は、「技術的なブレークスルーが自然に起きる」と素朴に想定している経済モデルを利用しているのだ。現在、いわゆる「グリーンエネルギー」源の開発に注がれる資金は、世界全体で年間わずか20億ドル。こんな自己満足なやり方では、必要なブレークスルーはとうてい間に合わないだろう。その場合、各国政府は効果的な代替エネルギーもないまま、課税・排出権取引制度を利用して、CO2排出量の削減に努めることになる。これでは将来の気候変動に対して実質的になんの効果もない。その一方で、短期的には経済成長に大きなダメージが生じ、貧困に苦しむ人びとは増え、この地球は、本来は可能であったよりもはるかに暗い場所になってしまうだろう。(ダイヤモンド・オンライン 2010年01月13日)
以前メモしたように温暖化懐疑論者に対して、いざそうなったらどう責任とるんだみたいな批判をする温暖化論者もいるわけですが、逆に経済が悪化した場合の責任についてどうとるかという言説はないです罠。
環境汚染「ワースト1」の街は今――中国・山西省
>山西省南部の臨汾(りんふん)市は、06年に世界銀行が発表した報告書で、世界一環境汚染の深刻な街と名指しされた。その後、当局が大規模な汚染防止対策を進めてきたものの、スモッグに包まれた住民の暮らしは相変わらずのようだ。同省は中国の石炭産業の拠点。その中核となる臨汾には、多くの炭鉱や製鋼所が集中している。
かつては日本も光化学スモッグが頻繁に発生していたように大気汚染は当たり前でした。
>環境汚染の「ワースト1」という汚名を返上しようと、当局は過去数年間、環境浄化事業に力を入れてきた。市環境当局者らによると、数百カ所の炭坑や工場が閉鎖された結果、07年の市内総生産(GDP)は約270億円も減少した。 残った工場にも厳格な環境基準が課せられた。近郊のある製鋼所では、約1億8000万円の費用をかけて、汚染物質の排出を抑えるシステムを導入した。(2009.12.26 Web posted at: 19:04 JST Updated - CNN)
ただ、その対策あって徐々に改善されているという記事になっております。ある程度豊かになればこそ環境対策、コストがかけられるようになると。
「ゲーム脳」など脳研究で俗説、倫理指針を改定…神経科学学会
>指針は2001年に策定、昨年12月、大幅に改定した。近赤外光脳計測装置(NIRS)など、人体を傷つけない装置の開発で、工学、文学など異分野の研究者が脳科学に参入した。しかし、ゲームに熱中すると、脳の前頭前野の働きが低下する「ゲーム脳」になるといった研究などが、科学的検証を受けずに流布。発表時には科学的根拠を明確にするよう求めた。また、実験で被験者へのインフォームド・コンセント(説明と同意)が十分ではない研究者が目立つとして、人権への配慮を徹底すべきだと指摘した。指針は、学会のホームページ(http://www.jnss.org/)で公表している。(2010年1月9日 読売新聞)
このニュース本当は別カテゴリーでメモしたかったけれど、いい加減賞味期限切れになりそうなのでさっさとメモしておきます。先日、はなまる幼稚園で「ゲーム脳」論についてまっとうな批判を幼稚園児が滔滔と述べていて爆笑した!
あと、関係ないですが電車内広告で目についたネタ↓(今年4月開校らしいですよ)
ロイヤル・アカデミー・オブ・ホメオパシー ホメオパシー医学を追究する名門校
以下 アニメ感想
「ひだまりスケッチ」第2話
ふつー。
「おおかみかくし」第2話・「おまもりひまり」第2話
ふつー。
「とある科学の超電磁砲」第15話
今回からまた新たな展開が始まるのかな?一瞬新キャラがインデックスに登場した魔術師かと思ったよ。
「鋼の錬金術師」第40話
ファーガスンとキルバンは、2009年にもっと洗練されたメタ分析を行った。1998年から2008年に行われた暴力映像関係の文献をデータベースで検索した。彼らは古い研究は妥当性の低い方法を利用しているので、除外して新しい妥当性の高い研究に限定したほうがよいと考えた。また、攻撃性を肯定する論文の発表数が多くなる出版バイアスを調整した。それで、メタ分析は、25の研究、被験者総数12,436名に限定して行われた。
研究の妥当性は、どのような攻撃性の指標を用いたかによって左右される。25の研究の内訳を見ると、18の研究では標準化された指標を用いていたが、残りの9つの研究では用いていなかった。また、11の研究のみが、他人に対する暴力行為や凶悪犯罪と直接的に関連した指標を用いていたが、その他の研究は、暴力行為に直接関係しない指標や、教師や同胞による攻撃性の評価を用いていた。
全体のメタ分析では、効果量は0.08と、統計的には有意であるが、非常に小さな値であった。影響力に換算すると、0.64%にすぎない。標準化されていない指標を用いた研究では効果量が0.24ともっとも高かった。また、妥当性の低い指標を用いた研究では効果量は0.09、妥当性の高い指標を用いた研究では効果量が0.25と大きく、暴力行為と直接的に関係する指標を用いた研究では効果量は0.02と極めて小さく、影響力に換算すると0.04%と無視しうる値であった。
結論はノーである。暴力的映像は暴力行為を助長しない。暴力行為と直接的に関係する指標を使った研究では、効果量がほとんどゼロであり、妥当性の低い研究でのみ効果量が大きい。まだ、論争は続くかもしれないが、半世紀にわたる数百の研究は何だったのだろうか。エビデンスの高い研究以外は無価値であるということではないか。
村上宣寛「心理学で何がわかるか」
- 地球と一緒に頭も冷やせ! 温暖化問題を問い直す/ビョルン・ロンボルグ
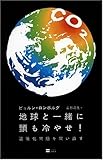
- ¥2,100
- Amazon.co.jp