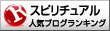ちょっと遅くなったが、日本の民俗学的な狐の歴史についての本をレビューしたい。
狐付きと狐落とし
狐付きと狐落とし | 中村禎里 |本 | 通販 | Amazon
こちらは、前回紹介した【書籍レビュー】狐の日本史の続編です。
前作は、日本の古代から中世までの民俗学的な狐についてでしたが、
今作は、中世から江戸時代までが対象になっています。
前作は、民俗学の文献を総当たりしたような本でしたが、
近世に入り参考文献数も増えたため、章ごとにまとまりが出て読みやすくなりました。
前回はさらっと読んだのですが、今作はしっかりメモをとりながら読みました。
そうしたら、メモ数と掛かった時間は膨大なものになりました😅
1つの点がメモです。
第一部中世
- 玉藻前、女化稲荷
- 葛の葉
- 源九郎狐
- 長壁(おさかべ)さまと富姫様
- ものぐさ太郎
- 祐天と狐僧・狸僧
第一部では、各地の民話やお話の中で”狐”が登場する話を、文献を読み込んでまとめてある。
私としてはほとんど知らない話が多かったので非常に参考になった😄
個々の話として、それだけで記事になるような内容なので個々の話はここでは取り上げられない。
第一部、そして本書を読んで知った点として、
関東において、狐はとても友好的で良いものとしてとらえられていたということだ。
古代からの関東では、狐が地主神や、その使いとして敬われていた。
一方、西日本では、狐は荒っぽいやっかいな存在であることが多い。
それは、西日本では荒神様や蛇などが既に信仰の対象として存在しており、狐が信仰の対象とはならなかったのだろうと著者は推測している。
私はこの本を読むまでは、狐、特に白狐は宇迦之御魂神様のお使いであると思っていたのだが、関東で古くから人が住んでいる場所では必ずしもそうではなかった。
宇迦之御魂神様は渡来系の秦氏が信仰していた神であり、宇迦之御魂神様が信仰されるより前は、狐が神そのものであったのだ。
(ただし、宇迦之御魂神様について、この本ではほぼ触れられていない。それは、宇迦之御魂神さまが”狐”ではないからだろう。著者の関心は、本書では狐のみに集中されている。)
また、著者は狐にまつわる話を大変興味深く思っているようだが、その力を一切信じてはいないので、スピリチュアル的な記述には欠けている。
その点は、前作で十分わかっていたことなので、取り上げられた狐や神さまとチェネリングすることで、スピリチュアル面での話を補えたので個人的には問題なかった。
第二部江戸
江戸初期の流行語に
「江戸名物、伊勢屋、稲荷に犬の糞」
という言葉がある。
大阪、西国と比べて、江戸には稲荷が遥かに多かったのだ。
要因として以下のような要素が上げられている。
- 元々関東の地主神として、鎮守・農耕神としての狐信仰があった。
- 屋敷の稲荷。戦国大名は、鎮守の為にダキニ天を信仰していた。
- 西国などから人々が導入。(数は少ない)
- 鎌倉からの到来。(街道沿いに多い)
- 江戸の人口増加。
稲荷社は、特に許可を得ることなく自由に建てることができた。
その為、武家屋敷では本国から稲荷社を呼び寄せた。
近くに稲荷が無い地域では町人達が自分達の稲荷を建てた。
寺院も収益化の為に稲荷社を境内に建てた。
このようにして江戸の稲荷は、人口増加ととともに急激に増えていったのだ。
本書では、その中でも特に、宇迦之御魂神様を祀っているというよりは、狐がご本尊になっている『狐稲荷』を多数紹介している。
ネットを使って調べてみると、本書で取り上げられている『狐稲荷』は、現在でも半分ほどは残っている。なので私も東京へ行くついでにちょくちょく回っている。
それについても機会があれば紹介したい。
第三部狐付き
まず本書では、『狐憑き』ではなく、『狐付き』で統一されている。
憑きという言葉は、神が憑く場合に使われるものであり、
昔は狐に関しては、『付き』の方が妥当なのだそうだ。
この憑き/付きの言葉の表現についても、本書では文献を並べて統計を取っている。いやはやこだわりっぷりはたいしたものである😅
本書の表を、エクセルに落としたもの。
著者はこれを全部まとめたのであるからたいしたものである。
狐付きとは、文字通り、狐が人間に取り付くことである。
最古は『日本霊異記』(820年、下巻)であり、日本では古くから狐が人間に取り付くことが知られていた。
狐付きのタイプ、その落とし方。狐落としに使う薬の統計まで表にされている。
薬の表には思わず爆笑してしまった😆
狐を落とすのに大事なのは成分ではないでしょうに![]()
著者
中村 禎里(なかむら ていり、1932年(昭和7年)1月7日[1] - 2014年(平成26年)3月13日)は、日本の生物学・生物史学者、立正大学名誉教授。専攻は科学史、民族生物学。日本科学史学会会員、日本医史学会会員[2]。
経歴・人物
東京生まれ。1958年東京都立大学 (1949-2011)生物学科卒業。同大大学院理学研究科生物学専攻博士課程修了[2]。早稲田実業学校教諭を経て、1967年立正大学教養部講師。助教授、教授、1995年仏教学部教授。2002年定年退任、名誉教授。
生物学を中心に社会現象としての科学のあり方を研究。生物学周辺の歴史・民俗について多くの著書を著す。
引用:中村禎里 - Wikipedia
まとめ
古くから最近の研究まで、狐にまつわる多くの文献をまとめてあり、非常に読み応えのある本である。
ただ、何回も読むことでようやく意味がわかったり、情報が詰め込まれているので、平易な文章ではあるが読みやすいとは言えない。(少し読み飛ばすとすぐに話がわからなくなる。)
また文献(極一部は著者が直接神主などの話)が情報源であり、フィールドワークが不足している感はいなめない。
そして著者が、狐の話は大好きだが、怪異などや不思議なことを信じてはいないので、ときたま著者自身のトンチンカンな解釈が入る。
とは言え、日本の古代から最近までの”狐”に関する文献情報がまとまっている本が手軽に買えるのは、非常に素晴らしい。
個人的にもとても役に立った。
いずれ、東京の稲荷事情など、実際に訪れたり狐さん達から話を伺った話などをその内取り上げられたらと思っている。
評価
読みやすさ:★★☆☆☆2(平易な文章だが分厚く情報量が多い)
民俗学度:★★★★★5(マックス)
スピ度:★☆☆☆☆1(語られていない)
(前作と評価変わらず)