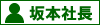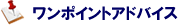こんにちは。
文書作成日:2024/07/25
進む高年齢者雇用と求められる企業の対応
人手不足解消の観点から定年の引き上げや定年再雇用時の賃金水準の見直しなど、企業において高年齢者の積極活用を進める動きがみられます。今回の旬の特集では、こうした動きに対応し、高年齢雇用に関する動きについてとり上げます。
[ 1 ]
継続雇用にかかる経過措置の廃止
定年年齢を65歳未満としている企業は、65歳まで希望者全員を雇用する高年齢者雇用確保措置を講じる義務があります。ただし、一定の要件を満たした企業は、2025年3月31日まで、労使協定において継続雇用の対象者を限定する基準を設け、一定の年齢以上の人に対して、その基準を適用することができるとされてきました。
この経過措置を適用している企業では、労使協定を締結した上で、就業規則において、以下のように経過措置の対象となる年齢を段階的に定めています。
|
この経過措置は、2025年3月31日で終了するため、2025年4月1日以降は原則どおり、定年退職となる本人が希望し、解雇事由または退職事由に該当しない限り、65歳までの継続雇用が求められることになります。
[ 2 ]
70歳までの就業機会確保
企業が従業員の定年を定めるときは、60歳を下回ってはならないとされており、65歳未満の定年年齢を定めたときは、原則希望者全員を65歳まで雇用することが必要です(高年齢者雇用確保措置)。これに加え、2021年4月からは70歳までの就業機会の確保が努力義務となりました。
これは、個々の従業員の多様な特性やニーズを踏まえ、多様な選択肢から、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けたものです。そのため、65歳までの高年齢者雇用確保措置が雇用によるものであるところ、70歳までの高年齢者雇用確保措置では、「継続的に業務委託契約を締結する制度の導入」や、「事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業への従事」も選択肢として挙げられています。
今後は、企業における65歳以降の高年齢者の活用も本格化してくるため、企業としてどのように働いてもらうか、努力義務ではあるものの、制度構築が重要な場面になってきます。
[ 3 ]
高年齢雇用継続給付の見直し
高年齢雇用継続給付は、原則として60歳以上の従業員の給与が、60歳時点よりも一定割合を超えて低下したときに支給されるものです。現在の給付率の上限は15%ですが、2025年4月1日以降は、給付率の上限が10%に引き下げられます。
この変更の対象は、2025年4月1日以降に60歳となる従業員とされていることから、高年齢雇用継続給付の受給対象者が複数人いるような場合、同じ会社の中に給付率の上限が15%になる人と10%になる人が混在する可能性があります。
また、定年再雇用時の賃金を決定する際、高年齢雇用継続給付の支給額を考慮するようなケースがありますが、その際には今回の給付率の引き下げを勘案する必要があります。これを機に、定年再雇用時の賃金の決定方法に、雇用保険から受けられる給付額を加味することが妥当なのかの議論も必要となるのかも知れません。
[ 4 ]
高年齢者を対象とした助成金
60歳以上の労働者の雇用状況について、令和5年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果(21人以上の規模企業)をみてみると、常用労働者数(約3,525万人)のうち、60歳以上の常用労働者数は約486万人で、全体の13.8%を占めています。つまり、8人に1人以上の割合で60歳以上の従業員がいるという状況になります。
今後も、企業において60歳以上の従業員が増加することが予想されます。その際に活用できる助成金として、65歳以上への定年引上げや定年の定めの廃止等を行った場合に対象となる「65歳超雇用推進助成金」や、高年齢者を含む労働者が安心して安全に働くことができるよう高年齢者の労働災害防止対策等を行った場合に対象となる「エイジフレンドリー補助金」があります。高年齢者の雇用の取組みを行う中で、活用できる助成金・補助金があれば、機会損失がないようにしたいものです。
今回とり上げた動きを押さえつつ、60歳以降の雇用のあり方や賃金の設定、65歳以降の人材の活用などを検討される際に、お困りごと等ございましたら、当事務所までお気軽にご連絡ください。
■参考リンク
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止~」
厚生労働省「高年齢雇用継続給付の見直し(雇用保険法関係)」
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」
厚生労働省「令和5年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します」
厚生労働省「65歳超雇用推進助成金」
厚生労働省「エイジフレンドリー補助金について」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
ホームページはこちら ⇒ 古谷労務経営事務所