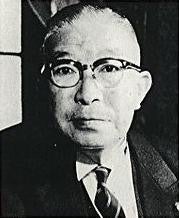日本の歴史 現代史編
1954年12月10日
第5次吉田内閣総辞職
第52代内閣総理大臣 鳩山一郎 日本民主党
1955年2月27日 第27回衆議院議員総選挙(鳩山ブームが発生)

第53代内閣総理大臣 鳩山一郎 日本民主党総裁
(1955年3月19日~1955年11月22日)
第2次鳩山内閣=日本民主党政権
1955年10月13日
1955年11月15日
→55年体制が出来上がる
1955年11月22日
第2次鳩山内閣総辞職
第54代内閣総理大臣 鳩山一郎 自民党総裁
(1955年11月22日~1956年12月23日)
第3次鳩山内閣=自民党政権
[1955年11月15日に自由党と民主党による保守合同によって自由民主党が結成され、内閣総理大臣鳩山一郎が自由民主党筆頭総裁代行委員に就任した。
それを受けて与党の基盤が変更になったとして第23回臨時国会の冒頭で第2次鳩山一郎内閣が総辞職し、首班指名選挙で再度、鳩山一郎が内閣総理大臣に指名されて組閣した内閣である。
日本国憲法下で、衆議院議員総選挙による内閣総辞職を経ずに内閣総理大臣に連続再選された例は、この時の鳩山一郎の3度目の首班指名ただ一度だけである](出典:ウィキペディア)
1956年7月 経済白書「もはや戦後ではない」
1956年10月19日 日ソ共同宣言
[日ソ共同宣言は、1956年10月19日に日本国とソビエト連邦がモスクワで署名し、国会承認をへて、同年12月12日に発効した外交文書(条約)のこと。これにより両国の国交が回復、関係も正常化したが、国境確定問題は先送りされた]
(出典:ウィキペディア)
1956年12月18日
日本が80番目の加盟国として国際連合に加盟する
1956年12月23日
第3次鳩山内閣総辞職
(1956年12月23日~1957年2月25日)
石橋内閣=自民党政権
[1956年10月19日に日本とソビエト連邦が日ソ共同宣言により国交正常化するも、同年12月、鳩山首相が引退。これを受けてアメリカ追従を主張する岸信介が自民党総裁選に立候補、これに対し石橋は社会主義圏とも国交正常化することを主張、鳩山派の一部を石橋派として率いて立候補した。総裁選の当初は岸優位で、1回投票では岸が1位であったが、石井光次郎と2位・3位連合を組んだ決選投票では石橋派参謀の石田博英の功績もあって、岸に7票差で競り勝って総裁に当選、12月23日に内閣総理大臣に指名された。しかし、前述のような総裁選であったため岸支持派とのしこりが残り、更に石橋支持派内部においても閣僚や党役員ポストの空手形乱発が行われ、組閣が難航したため、石橋自身が一時的に多くの閣僚の臨時代理・事務取扱を兼務して発足した(一人内閣)。親中派でもある石橋政権の樹立によって日本を反共の砦とするために岸を望んでいたアメリカ大統領ドワイト・D・アイゼンハワーは狼狽したという。「党内融和の為に決選投票で対立した岸を石橋内閣の副総理として処遇すべき」との意見が強かったため、石橋内閣成立の立役者だった石井の副総理が無くなり、副総理は岸が就任した。
内閣発足直後に石橋は全国10ヵ所を9日間でまわるという遊説行脚を敢行、自らの信念を語るとともに有権者の意見を積極的に聞いてまわった。しかし帰京した直後に自宅の風呂場で倒れた。軽い脳梗塞だったが、報道には「遊説中にひいた風邪をこじらせて肺炎を起こした上に、脳梗塞の兆候もある」と発表した。副総理格の外相として閣内に迎えられていた岸信介がただちに総理臨時代理となったが、2ヵ月の絶対安静が必要との医師の診断を受けて、石橋は「私の政治的良心に従う」と潔く退陣した。1957年度予算審議という重大案件の中で行政府最高責任者である首相が病気療養を理由に自ら国会に出席して答弁できない状況での辞任表明には、野党でさえ好意的であり、岸の代読による石橋の退陣表明を聞いた日本社会党の浅沼稲次郎書記長は石橋の潔さに感銘を受け、「政治家はかくありたい」と述べたと言う。石橋の首相在任期間は65日で、東久邇宮稔彦王・羽田孜に次ぐ歴代で3番目の短さである。日本国憲法下において、国会で一度も演説や答弁をしないまま退任した唯一の首相となった。後任の首相には岸が任命された。
石橋はかつて『東洋経済新報』で、暴漢に狙撃されて帝国議会への出席ができなくなった当時の濱口雄幸首相に対して退陣を勧告する社説を書いたことがあった。もし国会に出ることができない自分が首相を続投すれば、当時の社説を読んだ読者を欺く事態になると考えたのである](出典:ウィキペディア)
1957年2月25日
石橋内閣総辞職
第56代内閣総理大臣 岸信介 自民党総裁
(1957年2月25日~1957年7月10日)
第1次岸内閣=自民党政権
[内閣総理大臣:石橋湛山が総理就任間もない1957年の年明けに体調を崩し、脳軟化症と診断されて療養に入り、通常国会の審議に出席不能となったことを受けて石橋内閣が総辞職したことに伴い、後継総理に外務大臣:岸信介が首班指名を受けて組閣した。
国務大臣として1956年の自由民主党総裁選挙第3位であった石井光次郎を新たに入閣させたことを除き、石橋内閣の閣僚をそのまま引き継いだ居抜き内閣である](出典:ウィキペディア)
第56代内閣総理大臣 岸信介 自民党総裁
(1957年4月10日~1958年6月12日)
第1次岸内閣(改造)=自民党政権
[前の第1次岸内閣の改造内閣である](出典:ウィキペディア)
1958年4月25日 話し合い解散
[1958年4月18日に岸信介内閣総理大臣と鈴木茂三郎日本社会党委員長による党首会談で、野党が内閣不信任決議案を上程した時点で衆議院を解散することで合意する。
4月25日に衆議院に内閣不信任決議が上程される。社会党議員の河上丈太郎が内閣不信任の趣旨説明を行った後で採決を経ずに衆議院解散となった。
1955年の社会党再統一と保守合同による55年体制後の初の総選挙となった](出典:ウィキペディア)
1958年5月22日 第28回衆議院議員総選挙
第57代内閣総理大臣 岸信介 自民党総裁
(958年6月12日~1959年6月18日)
第2次岸内閣=自民党政権
[第2次岸信介内閣は1958年5月に施行された第28回衆議院議員総選挙での自民党の勝利を受け、その後の第29回特別国会で岸信介が首班指名を受けて内閣総理大臣に再任された後に組閣されたものである](出典:ウィキペディア)
第57代内閣総理大臣 岸信介 自民党総裁
(1959年6月18日~1960年7月19日)
第2次岸内閣=自民党政権
[第2次岸改造内閣は、岸信介が第57代内閣総理大臣に任命され、1959年6月18日から1960年7月19日まで続いた、前の第2次岸内閣の改造内閣である。
新安保条約の批准書交換の日の6月23日に岸信介が辞意を表明して7月15日に総辞職した](出典:ウィキペディア)
1960年1月19日
岸信介が新日米安全保障条約を調印
1960年6月19日
新日米安全保障条約が参議院の議決がないまま自然成立
1960年6月23日
岸内閣は安保闘争による混乱を収拾するため、新安保条約の批准書交換の日である6月23日に総辞職を表明
1960年7月15日 第2次岸内閣(改造)総辞職