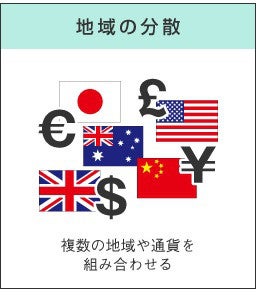いわゆる地域分散とは、「海外の国の株式や債券にも投資する」という意味です。
地域分散のテーマを挙げると、大抵、「海外の方が、経済が成長するよね」というリアクションがありますが。さて、そもそも「経済の成長」が何かという話は後日にするとして。
地域分散をするのは、何も「海外の成長」だけではありません。
例えば、「災害に対するリスクヘッジ」。余り、考えたくはないですが、日本が大震災に見舞われ、経済的な混乱が生じても、海外は普段と変わらなかったり。
あるいは、海外の株式や債券に投資をするこということは、全て現地通貨での取り引きになります。いわゆる為替差益を得るチャンスにもなりますが、逆に為替差損が生じることもあります。
地域分散とは、要は「投資で利益を得る機会を増やす」のが目的なのです。投資をしなければ、損も無いですが、「利益を得る機会(チャンス」も無いですからね。