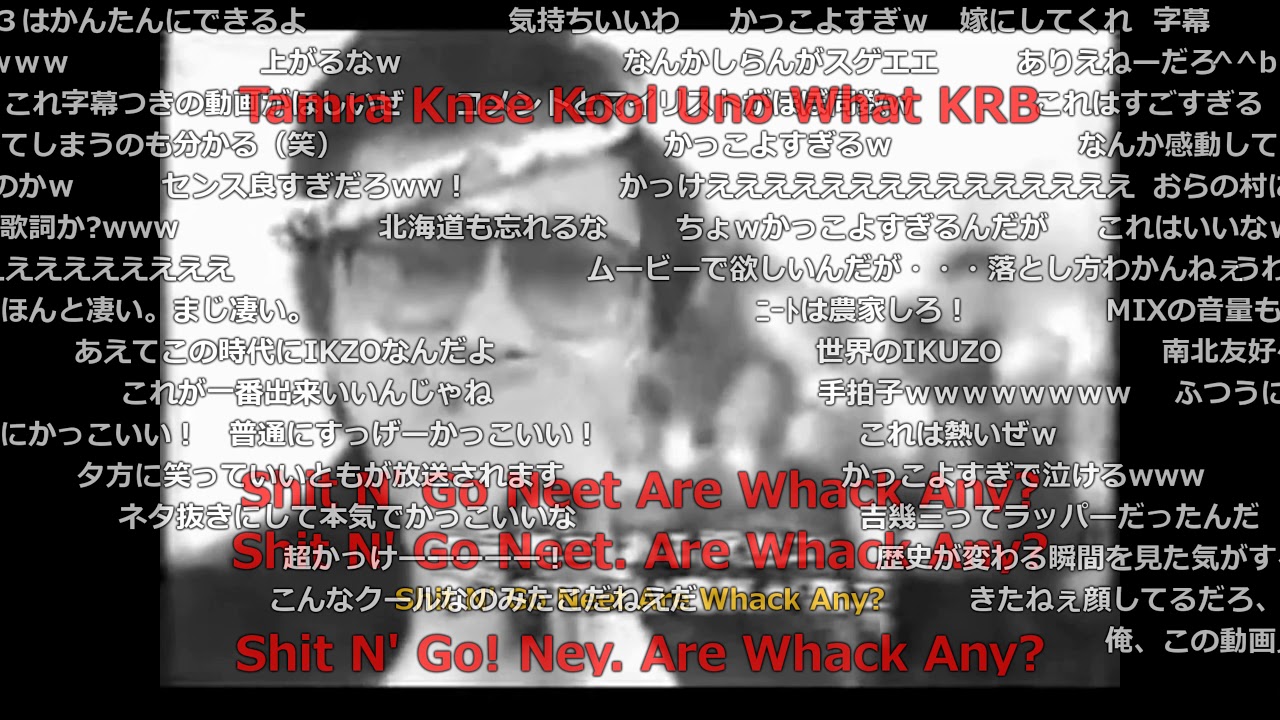昨日はYoutubeで2000年代後半のニコニコ動画全盛期にアップロードされたMAD動画やら音楽作品を眺めて懐かしさに浸っていました。
90年代まではパソコンと言えばヲタク御用達のツールでしたが、2000年代初頭に今で言うところのガラケーが登場し、インターネットへの敷居がグッと低くなった事で、老若男女あらゆる層が手軽に自分のインターネットサイトやブログや動画を発信出来る時代となりました。
自分も2000年代初頭に今は亡き「さるさる日記」というサイトで携帯小説()をガラケーでポチポチと打ち込んでアップロードしていた時代もありましたが、当時のブログにはコメント欄というものが無かったので、代わりに利用していたのが「teacup掲示板」という掲示板サイトでありました。
https://9329.teacup.com/taueinekari/bbs
程なくして、アメブロやライブドアブログの登場によって、teacup掲示板のような独立してコメントを書き込める個人掲示板を利用する人は急激に減少してきました。
それでもteacup掲示板は同窓会の告知等で一部のオールドユーザーには長く愛されるコンテンツとして利用されていたようですが、どうやら今年8月を持ってサービスが終了するとの事のようです。
インターネットサイトの流行り廃りの変遍を観ていると、故郷の街並みの景色が都市開発によって移り変わっていく様を見ているかのようです。魔法のiランド、前略プロフィール、mixiと、今となっては消滅したり過疎化の一途を辿るサイトへの憧憬を辿りながら、その当時ネット上で仲良くしてた人達は今何をやっているんだろう、と、今となっては消息が分からず完全に疎遠になってしまった人達に想いを馳せるわけであります。
そういえば青木真也はDREAMに出ていた頃に「専務」というハンドルネームでこっそりとmixiをやっていて、マイミクで当時結婚前だった奥さんと相互でラブラブな紹介文をアップしていましたが、今となっては離婚してしまいました。
人との関係も時と共に移り変わっていきます。Twitterの9年間を振り返っても割と仲の良かったフォロワーでも少しのボタンの掛け違いや考え方の違いによってブロックしたりされたりしたケースが少なからずあったので、ネットの関係で長くお付き合いしていくのって難しいなぁって思います。今の自分はインスタがメインでフォロワーの中にはTwitter時代やそれ以前のアンチ魔裟斗ブログ()時代からのお付き合いの人も居たりするので、改めてその人達には感謝したいです。ありがとうございます。
ニコニコ動画に話は戻りますが、未だにこの動画を超えるマッシュアップは聴いた事がないよなぁという事で、まさにあの時代(2000年代後半)だからこそ出来た奇跡の作品がコレです。
知っている人も多いかと思います。Perfumeのプロデューサーとしても知られている中田ヤスタカが手掛けるデジタルテクノユニット、Capsuleの曲に、世界的音楽ユニットのdaft punkとBeasty Boysのラップをマッシュアップさせて、更に当時ニコニコのMAD動画で流行っていた吉幾三の「おら東京さいくだ」を掛け合わせた事で、それぞれジャンルが違う音楽ながらも見事な音楽的調和を生み出し、当時のニコニコユーザー達から絶大な人気を博しました。
元々はCapsule×daft punk×Beasty Boysのマッシュアップ作品として投稿されていて、それを別の投稿者が吉幾三の曲を掛け合わせて再アップした作品ではありますが、こういうプロでは出来ないような二次創作、三次創作における独創的で、コンプライアンス規制のギリギリを突いていて、自由で面白い作品が数多くアップロードされていたのが当時のニコニコ動画でした。
コメント欄で歌詞職人や弾幕職人とかが居て、それが四次、五次創作となってみんなで盛り上げていたのも懐かしいですね。
思えばあの頃のニコニコは既存のメディア(芸能界)におけるカウンターアタックとして存在していて、インターネットの素人と応援する視聴者が文化を作り上げるという先駆けだったように思います。歌手の米津玄師、やなぎなぎ、声優の花江夏樹は元々ニコニコ動画出身で、創作活動を認められて人気を博してそのままプロの世界へと飛び込んだ例ではありますが、昔だったら上京してオーディションに合格しなければプロとしての第一歩を踏み出せなかったのが、ニコニコ動画の存在によって埋もれたダイヤの原石が発掘された例は数多かったです。
ただそのニコニコ動画も、2010年代に突入すると動画規制の問題やサービスの不備等でYouTubeに遅れを取り、有能なクリエイター達が次々と離れていきました。自分もその一人ですが、その頃を境にニコニコ動画をあまり見なくなった、という人もかなり多いです。
ニコニコ動画衰退の理由はこの記事を読めば分かると思います。
https://note.com/wattyoi/n/ne29331ab8ec9
一言で言えば「人が居なくなった」という事ですね。
有能なクリエイターが去っていく、そうすると視聴者であるユーザーも離れていって、熱やブームが生み出せなくなっていく、やがてクリエイターを志して動画を投稿する人も、他の巨大プラットホームを選択する。ネットに限らずあらゆる産業に言える事なのかもしれません。
純国産ブランドのニコニコ動画よりも、世界的なプラットホームであり、多くの著名人がユーザーとして愛用しているYouTube、Twitter、instagram、tiktokに流れていくのは、まさに必然だったというわけです。
今のニコニコ動画で全盛期のような優れたMAD作品やマッシュアップ作品はあまり見当たらなくなってしまいましたが、YouTubeで全盛期の動画を見る度にニコ動であの熱をもう一度、なんて想いを巡らせる瞬間がふと芽生える元ニコ動ユーザーも多いかと思います。
とはいえ、あの頃の熱狂はあの時代特有の空気や文化でしか創り出せないというのもあったでしょうし、受け取るユーザー側の年齢層がそうさせていた部分があったと思います。特に音楽が顕著だとは思いますが10代~20代前半に聴いていた大衆ソングのほうが、当時の思春期、青年期特有の思い出補正込みで心に残る、っていうのはあるかと思います。
過去は戻らない。時々は思い出に浸ってもいいでしょうけど、前に進んでいきましょう。
🌲追記🌲
最近ニコニコ動画も地味に黒字化しているなんて記事も目にしました。
要はYouTubeが巨大化し過ぎて一握りの有名人しか稼げなくなってしまったので、逆にオワコンと思われていたニコニコ動画が穴場のプラットフォームとなって、そこそこ稼げるメディアとなったわけですね。
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2205/26/news138.html
YouTubeがUFCだとすると、ニコニコ動画はネイション(地域)団体やフィーダーショー団体的な位置付けを目指していくという形でしょうか。