ここ最近続くドル安の流れを受け、東京タイムでもドルが売られる展開となりました。
ドル円はついに109円を割り込み、一時は昨年9月以来となる108円74銭まで下落しました。
ユーロドルは1.24台を堅持しており、こちらは2014年12月以来の水準。
ポンドに関しても2016年にはブレグジット騒動がありましたが、対ドルでも円でも同水準を回復。
人民元も2015年10月以来の水準です。
ドルが売られ、クロス通貨が買われる動きとなっています。
株式市場では、欧米勢は史上最高値をばく進中、日本株も1991年9月来水準となっています。
商品相場に目を向けると、NY原油は2014年11月、NY銅は同年7月以来の水準です。
我々が認識しているかどうかは別として、今ほぼすべての資産価格が上がってきています。
特に年初から当サイトでも「おかしい」と指摘していた中国株にいたっては、昨年12月28日から今年1月12日まで11連騰し、1月16日の1営業日だけ休憩をはさみ、再び昨日まで7連騰。
19営業日で約8.7%とハイペースで上昇しています。
上昇著しい上海総合指数とNY銅、NY金を比べてみましょう。
(左軸は上海総合、NY銅、右軸はNY金)
NY銅とNY金は分かりやすいように倍率や目盛を合わせましたが、順調に上がってきました。
なんだかQE中の動きそっくりですが、決定的に異なるのが金利です。
今月11日記事「どこまで引き締めるのか」にて上記チャートを掲載して、NY金と米長期債利回りの逆相関をご覧いただきました。
そして引き締めの限界に関する意見を次のようにご紹介いたしました。
ひとつの例として利上げの限界点を短期債利回りから推測する方法が挙げられ、限界水準は3年物利回りの2.00~2.20%とされています。
米3年物利回りは今週月曜日2.21%まで上昇し、上限に到達いたしました(同日2年物2.08、10年物2.66)。
想像を逞しくすると、金利が限界点に到達したことからの高官によるドル安誘導発言かもしれません。
最近の金利上昇はおそらくバランスシート縮小によるものと考えますが、一部では期待インフレ率の上昇によるものではとの指摘もあります。
トランプ政権による政策運営が財政出動型でありますので、金利上昇は致命傷となります。
昨年10月5日記事「上には上がある」で次のように書きました。
クルーグマンが双子の赤字が維持不可能となる条件として、「長期金利が名目成長率を上回る」と警告したことは有名です。
2017年で約2.2%ですから、金利は危険水域に入ってきたと言えそうです。
経済政策はトランプ政権の生命線ですので、金利上昇には敏感になっていると考えるべきでしょう。
補足:本日の上海総合指数は0.31%下落いたしました。
お詫び
トランプ大統領がダボス会議に登壇するのは明日かもしれません。
申し訳ありません。
お問い合わせ Tel:0120-448-520
(平日8:00~17:00)
日本フィナンシャルセキュリティーズ㈱
谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定(貴金属、石油、オプション)、証券一種外務員
![]()
![]()
![]()
![]() 皆様の貴重な1票が励みです。
皆様の貴重な1票が励みです。
にほんブログ村
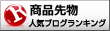
![]()
![]()
![]() 皆様の貴重な1票が励みです。
皆様の貴重な1票が励みです。
商品先物ランキング

