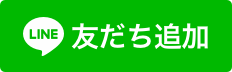「子どもたちのインナードリームを見つけよう」
スポーツと音楽のプロに学ぶ子育て【前編】
ラグビーをはじめとするスポーツ界ではコーチのコーチとして、またビジネスの分野ではリーダー育成でも定評のある中竹竜二さん。今年、エッセンシャル出版から、子育てについての見解をまとめた、『どんな個性も活きるスポーツ・ラグビーに学ぶ オフ・ザ・フィールドの子育て』を出版しました。
その出版記念第2弾として中竹竜二さんと、「本物」の芸術に触れ、楽しみながら音楽を学び豊かな感性を育む「アノネ音楽教室」代表・笹森壮大さんのyoutubeで公開対談を行いました。
テーマは、「子どもたちのインナードリームを見つけよう~折れない心、くじけない心を育てる」です。
スポーツと音楽のプロの視点から、「子育て・人育て」について、
3回にわたり、対談の内容をお伝えしていきます!
―本日は、「子どもたちのインナードリームを見つけよう 〜折れない心、くじけない心を育てる~」をご視聴くださり、ありがとうございます。
今回は、小さいころにラグビーを始め、名門・早稲田大学ラグビー部の主将・監督、ラグビー20歳以下(U20)日本代表の監督を務め、今は「監督を教えるコーチ」として活躍されている中竹竜二さんと、小さいころにチェロを始め、音大を卒業後チェリストとして活躍する一方、音楽教育と音楽家の人生をよりよくしたいとの思いから、アノネ音楽教室を設立された笹森壮大さんによる対談を行います。モデレーターは、エッセンシャル出版社の小林が務めます。コメントはできるだけ拾っていきたいと思いますので、質問等がありましたらどんどん投稿していただけると幸いです。それではよろしくお願いいたします。
中竹さん:みなさん、こんばんは。中竹竜二です。ご存知ない方もいらっしゃると思いますが、僕はスポーツの分野で選手や指導者を育ててきた経験がありますので、それを踏まえて「人を育てる」ことについてのアイディアを皆さんと共有できればと思っています。よろしくお願いします。
笹森さん:こんばんは。アノネ音楽教室の笹森です。都内で音楽教室をやっております。中竹さんの書かれた書籍や動画を拝見しているのですが、明瞭に言語化がされているといるなと思っています。また、自分が大切にしてきたことに花マルをつけてもらったような気もしています。中竹さんと私の考えには、共通する部分も多いなとも思っています。今日は音楽の現場から、活かすことのできる知見を披露できればと思います。よろしくお願いします。
■インナードリームとは?
―今回は、スポーツ界と音楽界各々の特色を活かしつつ、多様な考え方を知ることが出来ればと思っております。本質的には同じことを言っていても、言葉としては異なることもあるでしょうし、その逆もあると思います。どんなコラボになるか楽しみです。それでは早速、今回のテーマ「インナードリーム」について、中竹さんにお聞きしたいと思います。中竹さんが何故、インナードリームを大事と思うようになったのでしょうか。
中竹さん:皆さんは、夢やドリームという言葉をたくさん聞いてこられたと思いますし、「夢を持ちましょう」などもよく言われてきたと思います。僕が言うドリームには、2つの種類があります。「インナードリーム」と「アウタードリーム」です。
いわゆるアメリカンドリームのようもの、例えば「将来サッカー選手になりたい」「音楽家になりたい」「社長になって稼ぎたい」といった、その人の外側に形としてある一般的なドリームが「アウタードリーム」または「エクストラドリーム」です。
一方、インナードリームは、「これをしている瞬間が大好きだ!」というような、自分のなかにあって自分にしかわからない感覚のようなものです。スポーツ選手でも、世界で勝っていくような人は、インナードリームをちゃんと見つけていますが、一方で、活躍している選手のなかにも、インナードリームに気づいていない人が多く見受けられます。
インナードリーム…「これをしている瞬間が大好きだ!」というような、自分のなかにあって自分にしかわからない感覚のようなもの。勝利などの外的要因に左右されるものではなく、自分の中で完結できることがポイント。
アウタードリーム…その人の外側に形としてある一般的なドリーム
スポーツ選手だけでなくビジネスマンも、インナードリームを見つけることで、競技を長く続けたり人生を長く幸せに生きることができるようになります。
スポーツでいえば、優勝できるのは1チームまたは1人ですし「スポーツ選手になる」と言っても、プロの枠は決まっています。アウタードリームは、結果パイの取り合いになります。
一方、インナードリームは、陸上選手で例えると「走りだす瞬間の足の裏の快感」などの、日々の練習のなかで受け取ることができるもののことです。勝利などの外的要因に左右されるものではないわけですね。
昔、清宮監督の息子さんが高校野球で活躍していたときに、「ホームランを打った瞬間の感触がとても好き」とインタビューで答えていて、印象的だったのですが、彼はこの時すでにインナードリームを持っていたのですね。
「走りだす瞬間の足の裏の快感」「ホームランを打った瞬間の感触」で分かると思いますが、インナードリームには再現性があるのが特徴です。これがあれば、辛いことでも超えられますし、スポーツに限らず、どの分野でも、また大人にとっても子どもにとっても、本当に大事なことだと思います。ついつい「勝利」や「テストの点数」などに視点がいきがちですが、早い段階で、「なにがあってもこれさえあれば復活できる!」というインナードリームを見つけておくことが大切です。
笹森さん:私の分野で言いますと、音楽は毎日練習をしなければならないものでモチベーションに左右されますから、このインナードリームはやはり大事です。中竹さん、インナードリームは行動というか、何かフィジカルなことに特化された概念なのでしょうか。
中竹さん:どちらかというと、結果に頼らず自分のなかで何度も繰り返すことができる「瞬間」や「動作」のことです。これは小さなことでもよくて、相手によらずに自分の中で完結できることがポイントです。
■ストレスに向き合うことと、インナードリーム
笹森さん:ありがとうございます。僕の所属する花まるグループでは、 「子どもたちが学んでいることに対して、どのような価値感を持つことができるか」という「学習観」を、音楽技術と同様に大事にしています。
習い事は、3~4年経つとレベルが上がり、楽しいだけではなくなってきますよね。勉強も高学年になると大変になったり、水泳もクロールは楽しかったけれど、背泳ぎになるとやめてしまうということが起こります。楽しいという思う気持ちを継続させることは、なかなか難しいと思います。僕の教室では、「綺麗で楽しくて、アンサンブルは気持ちいいのだよ」という価値観をまずは掴み取ってもらい、ポジティブに捉えてもらえるようにしています。
中竹さん:僕は、笹森さんのご著書『幼児期だからこそ始めたい 一生ものの音楽教育』に書かれている「ストレスと向き合うこと」についての考え方にとても興味を持ちました。インナードリームがあって楽しかったのに、高いレベルになって面倒になったり、ストレスになったりする。このような時は、どんな指導をしているのでしょうか。
笹森さん:僕は指導者として、質のよいストレスを与えることが大事だと思っていています。頭ごなしに否定したり、子どもにとって有益ではないプレッシャーを与えることは意味がないですよね。ただ、子どもには質のよいストレスに向き合うことが、ひとつの課題としてあると思います。
僕はクラシックを教えていますが、クラシックは子どもにとって、一番ストレスのかかる習い事です。僕は、花まるグループに所属してから、幼児は「振り返り」や「やり直し」といった、時間軸を遡ることが嫌いと習いましが、音楽はその「やり直し」しかしないので、そもそも子どもに向いていないのです。
同じ芸術でも絵画なら、子どもが好きに描いていいのだと思います。スポーツも時間軸としては、前に進んでいる感覚はありますよね。
音楽は、絵で例えると「モナリザと全く同じ絵を描いてください」という課題を与え、ダヴィンチが描いた通りでないと合格ではない、ということになるのです。その通りになるまで、描き続けなければならないのですから、これは子どもにストレスがかかります。
そこで僕は、この解決策となる「4つの言葉」をお母さんたちに伝え、実践してもらっています。
ひとつは、「やり直しをさせながら、次に進む感覚を子どもたちに与える」ために、「次は」という言葉を使うことです。「じぁあ」や「そしたらね」でもいいので、なにか場面展開を感じさせるような言葉をかけるようにします。
また「レベルアップしようか」でレベルアップしていく…これらの言葉を掛け合わせると、反復しているけど、前に進んでいるのかなという気持ちを持つことができます。
練習中の子どもにかけるべき「四つの言葉」
「次は」「じぁあ」「そしたらね」「レベルアップしようか」
…子どもは反復が苦手。そこで、実際は反復しているだけのところを「前に進んでいる」と思ってもらうために、場面展開を感じさせるこの4つの言葉を使う。
ただそれでも、低学年の子が3~4回同じことを繰り返すとなると、やはりイライラしてきます。でも僕は「イライラしてきたら、うまくなるチャンスだよ。」「先生でも、できないことをするのは、イライラするんだよ」と伝えます。それ聞いた子どもたちは「大人もそうなんだ」と驚きますけれどね。それから、「でも、これをもう一回すると上手くなると分かっているから、先生は練習するよ」と続けます。
子どもたちは、面倒くさいと思うことを、悪いことだと思いがちです。大人も「面倒くさいって言わないの」と言いますしね。でも、面倒な気持ちは大人になってからも生涯、自然と心から湧き上がってくるもののはずです。
ですから、子どもたちと「面倒だと思っていいのだ」ということを共有して、その上で、「そう思ったということは、上手くなるチャンスだよ」と伝えます。小学校3年生くらいになると、「イラッとしたらチャンスなんだ」という言葉にして反復する子もいます。これがストレスに向き合うことかなと思います。また、この言葉のように、「言語化して覚えさせる」ことを大事にしています。
中竹さん:本当は振り返っているのに、前に進んでいる感を出すというのは、相当いい方法ですね。
笹森さん:そうですね。言葉というのは基本的に反射なので、何でその言葉を発したのか、分からなかったりしますよね。
僕は、レッスンで自分が言ったことを全て文字に起こして「この時、このワードを選んでおけばよかったな」などと反省したりします。要は、先生が言葉の選択をしっかりできるようにするのです。アノネ音楽教室は、先生になるまでの長い研修のなかで、こういう訓練もしてます。ただ、これを保護者の方がするのは大変なので、先ほどの4つの言葉を伝えています。
中竹さん:僕と全く一緒ですね。これは選手にもコーチにも言うことですが、人は、uncomfortable(快適ではない)な状態を通過しないと成長しません。最初は、たったの50回が辛い筋トレでも、筋肉がついてくればなんともなくなるのです。ですから、この「辛いな」という思いは、笹森さんのおっしゃる「質のよいストレス」と同じだなと思います。
笹森さん:そうですね。僕は、まさに今おっしゃられた内容を小学校3,4年生に伝えています。このくらいの年齢になると、論理的な話が分かるようになりますから、一切楽器に触れない時間を設けて「努力にも正しい努力と正しくない努力がある」ということを伝えるのです。アンダースエリクソンの『超一流になるのは才能か努力か?』という本にも書いてあるような、comfortableゾーンでは人は成長しないことや、「限界的練習」についてですね。僕は、それを野球の素振りに例えながら説明します。「角度を意識せずに素振りをして、もし10回に1回ずれてしまったら、1,000回目には角度は大分違ってしまっているよね。それが50回でいいから、一回一回角度に気を付けて素振りをしたら、正しいフォームで素振りができるから、角度もそんなにずれないよね。」という感じです。このような話をすると、子どもたちも「限界的練習をしなきゃ」というように、とりあえず、言葉は覚えてくれます。また、仮にストレスを受けなくても、目的や注意するべきことを考えながら練習するのが大事だと思います。
中竹さん:僕はコーチを指導する際、「大人の学びは痛みを伴うものなので、皆さんしっかり痛みを受けてください。僕は皆さんを痛みつけるのが役目なので、皆さんに恨まれても仕方ありません。」と、にこやかに伝えます。私の指導によって、コーチはunomfortableな状況に追い込まれますが、だからこそ、成長していきます。
笹森さん:ストレスは向き合わざるを得ないもので、子どもたちには、段階に応じてちゃんとストレスを乗り越えていくなと感じています。
中竹さん:このストレスを受けているときなど、インナードリームの存在が大事ですね。インナードリームは、意識しないとなかなか見つけ出すことができないものなので、選手たちにもよく問いかけるようにしています。
笹森さん:そうですね。音楽の練習というのは基本的に孤独ですから、他の楽器などとアンサンブルをする機会を設けています。子どもたちは、習っている楽器そのものより、過ごした時間が楽しかったかどうかが、好き嫌いの判断基準になったりもします。
例えば、ピアノの先生が好きなら結果ピアノが好きになりますし、レッスンでもらえるシールがモチベーションになったりもします。仮に、レッスンは課題だらけであったとしても、その日の最後に「過ごした時間が楽しかった」と総括できるようにしてあげたいと思っています。これが子どもたちの学習観を育むために、大事だと思います。
中竹さん:本当に共通点が多いですね。
― 中竹さんに質問をいただいています。「高校生でスポーツをしている子どもがいるのですが、子どものインナードリームを見つけるために、親ができる声かけはありますか?」
中竹さん:これは「問いかけ」が大切だと思います。試合の結果よりも「今日はどのプレーが一番好きだと思った?」「どの瞬間が一番好きだと思った?」などと聞くことですね。スポーツをやっていると、小さい頃から「結果がでないとだめ」と言われ続けますが、それ抜きの「問いかけ」である必要があります。
僕がラグビー日本代表の監督代行になったとき、ミーティングで、選手たちにインナードリームは何かを尋ねたことがありました。ところが、即答できる選手はほどとんどいませんでした。日本代表でもそうなのです。こうなったら、インナードリーム探しの持ち越しです。その場で答えられたとしても、実は違うという可能性もあるので、とにかく、自分のインナードリームを明確にすることを課題にしました。
プロでもそうなのですから、高校生ではより難しいと思います。見つかったらとてもラッキーなことです。
また、インナードリームはどんなに小さいことでもいいですし、「味方同士で目が合う」といった「プレーには意味がない」と思えることでもいいのです。この場合は、「共感する力」がその子のインナードリームになる可能性があるということになります。子どもが示したインナードリームには、「素晴らしいね!」と言ってあげてください。
子どものインナードリーム探し…親などの指導する側が、対等な気持ちで、勝敗とは関係なく「楽しかったこと」を問いかける。どんなに小さなことでも、プレーに直接関係ない事柄でもいいもの。子どもの答えには、肯定的な言葉をかけましょう。
笹森さん:インナードリームは、問いかけを続ければ見つけられるものなのでしょうか。
中竹さん:そうですね。見つけることができるものだと思います。僕はその人が示したインナードリームについて「本当に好き?」「皆に褒められるから好きだと思っているだけなのでは?」と、わざといじわるな聞き方をしたりします。これには理由があります。
足が速い僕の教え子に、「パスが好きなんですよね」と言った選手がいました。これには周りも僕も驚きました。その選手は足が速くて前進することで評価を受けてきたのに、本当は、自分に向かってきた敵を引き寄せながらパスをする、という瞬間が好きだったのですね。周りからの期待に応えようとするなどして、本当のインナードリームをそれまで言えなかったりするので、「それが本当のインナードリームか?」と問かけるのです。
笹森さん:いま、世の中でも「自分の関心を見つける」などとよく言われますが、実際には、好きなことを見つけるのは難しいですよね。
中竹さん:そうですね。僕はこのインナードリーム探しを、ビジネスのトップにいるようなマネジメント層にもしてもらっていて、「子どものころに夢中になったパズル並のインナードリームを見つけてください」と言うのですが、なかなか見つからず大変ですよ。大人が本気で探しても半年はかかります。また経験によっても変化していくので、その辺も分かってくると、いいと思います。
笹森さん:インナードリームは、意味付けによるものでもいいのでしょうか。
中竹さん:意味づけは「やりがい」のためにはとても重要です。「やりがい」は、ほうっておいても夢中になったり没頭できるインナードリームと、「嫌いだけど、やることに意味がある」というような後から意味づけするもの、この2つか支えになります。何かを成すときには、この2つが揃うのがベストですし、もっと言えば、この意味づけとインナードリームが一体化するのがいいと思います。ただ、この2つを一致させるべきだとは思いません。嫌なことでも、意味づけしながら好きになっていくプロセスも、人の成長にとって大切なことです。ストレスを克服することに意義を感じるのも一つのやりがいですよね。
■挫折 ― 自分のちっぽけさと向き合い、活かす
― 笹森さんは、子どもから大人まで、中竹さんは中高生も教えていると思いますが、幼少時と中高生になってからでは、挫折の頻度というか、その大きさが違うのではと思います。今回のサブタイトルは、「折れない心、くじけない心を育てる」ですが、そのようなご経験はありますか?
中竹さん:僕はもともと優秀ではなかったので、挫折はつきもので、それがデフォルトだという認識があり、小学生くらいの時にはそう悟っていました。挫折がスタートと言ったらいいのでしょうか。僕はラグビーだけが例外でしたね。
ラグビーにはたくさんのポジションがあり、足が遅くても、体が大きくなくても、うまくなくても、とりあえず気合いと根性さえあればなんとかなるのです。そいういう選手ばかりが集まるポジションもあるくらいです。僕は他のスポーツではだめだったかもしれないですけど、ラグビーにはそういう性質の方もたくさんいたことから、仲間意識を持ちながら続けることができました。
笹森さん: 僕も、そもそも自分に期待していないところがありました。「僕は優秀だ」などと思ったこともなく、ダメな人間だと思っています。今もそうです。ですから、ダメな人間から脱却するために何が必要かを考え、それに早く気づくことができたのがよかったと思います。
僕はよく、「音に芯が欲しい」と精神面のことを指摘された、音楽高校1年生か2年生のときの実技試験の経験を話します。今なら「地に足がついていないような、浮ついたような音なのだろう」などと分かるのですが、当時は何を言われているのかまったく分かりませんでした。
僕はもちろん練習はしていましたが、生きるという点では親のスネをかじっていたのです。それで、「芯を求めるためにどうするべきか」と考え、留学することに決めました。音楽の技術のこともありましたが、それよりも、外部との接触を断ち、本当に一人で生活することが目的でした。優秀だから留学したわけではありません。低時限にいる自分を成長させたかったのです。
会社でもそういう環境に恵まれました。いろいろな年代の人がいるなかで、入社したての20代というのは小学校1年生のようなものですし、自分はちっぽけなんだという事実に向き合う環境があったのはラッキーでした。僕の所属している花まるグループには、高濱正伸先生という教育界の巨人のような人がいますし、「教育という同じフィールドの高濱さんがこんなに頑張っているのだから」と自分を省みています。高濱さんの社長室の本は、1週間で10冊、20冊と変わっていきます。僕はそれを勝手にお借りして読んだりして、「読みました」と報告したりしていますが…。こういうスピード感で物事を進めている人がいることは、モチベーションになっていきます。
―中竹竜二( Nakatake Ryuji )

株式会社チームボックス代表取締役
日本ラグビーフットボール協会理事
1973年福岡県生まれ。早稲田大学卒業、レスター大学大学院修了。三菱総合研究所を経て、早稲田大学ラグビー蹴球部監督に就任し、自律支援型の指導法で大学選手権二連覇を果たす。2010年、日本ラグビーフットボール協会「コーチのコーチ」、指導者を指導する立場であるコーチングディレクターに就任。2012年より3期にわたりU20日本代表ヘッドコーチを経て、2016年には日本代表ヘッドコーチ代行も兼務。2014年、企業のリーダー育成トレーニングを行う株式会社チームボックス設立。2018年、コーチの学びの場を創出し促進するための団体、スポーツコーチングJapanを設立、代表理事を務める。
ほかに、一般社団法人日本ウィルチェアーラグビー連盟 副理事長 など。
著書に『新版リーダーシップからフォロワーシップへ カリスマリーダー不要の組織づくりとは』(CCCメディアハウス)など多数。
2020年、初の育児書『どんな個性も活きるスポーツ・ラグビーに学ぶ オフ・ザ・フィールドの子育て』を執筆。
― 笹森 壮大(Sasamori Sota )
桐朋学園女子高等学校音楽科(男女共学)を経て、桐朋学園大学音楽学部に入学し、2008年よりフランスへ留学。チェロを臼井洋治、倉田澄子、ほか、各氏に師事。2015 年、花まる学習会にて音楽教育部門「花まるメソッド音の森」を立ち上げる。また保護者向けの講演会も多数行っている。著書に『感性と知能を育てる 音楽教育革命』『幼児期だからこそ始めたい 一生ものの音楽教育』がある。
2019年、花まるグループから独立し、「株式会社グランドメソッド」「株式会社国際音楽教育研究所」を設立。2020年1月、音楽教室の事業名を「アノネ音楽教室」に変更。
◆『オフ・ザ・フィールドの子育て』の紹介◆
本書では、「多様性」というキーワードに着目し、それを独自に育んできたラグビーに学ぶことで、子どもたちに多様性を身につけてもらい、子育てをよりよくするヒントにできるのではないかと考えました。
教えてくれるのは、「コーチのコーチ」をしてきた“教え方のプロ"である中竹竜二氏。
さらに、花まる学習会を主宰する高濱正伸先生から、著者の考えに対して、
「子育て」や「学び」の観点から、適宜コメントを入れていただきました。
また、巻末にはお二人の対談を掲載し、ラグビーに学ぶことの意義についてご紹介しています。
あらためて「ワンチーム」という言葉の意味や、ラグビーが大事にしてきた「オフ・ザ・フィールド」という考え方を知ることで、わが子の個性をどのように活かしたらよいかを考えるきっかけとし、わが子が実際に輝ける場所を親子で一緒に見つけてほしいと思います!
✴︎ラグビー大好き芸人・サンドウィッチマンさんにご推薦いただきました。
「ラグビーがなかったら、いまの俺たちはいなかったと思う。
いろんなことを、ラグビーに教えてもらった。
もし、俺たちの存在が誰かの励みになっているとしたら、それはラグビーのおかげなんだと思う。中竹さん、ラグビーから学んだことは、今に活きています!」
✴︎サンドウイッチマン・富澤たけしさんには、アメブロでもご紹介いただきました。
◆『幼児期だからこそ始めたい 一生ものの音楽教育』の紹介◆
「音楽を通してより豊かな人生を」
「本物の音楽を楽しく学ぶ」
これまでの音楽教育に疑問を投げかけつつ、子どもたちの音楽教育に情熱を注ぐ、笹森壮大氏の著作。
□練習で「もう一回」って言っていませんか?
□練習が質の良いストレスになっていますか?
□回数を基準にした練習をしていませんか?
□お子さんは無意識に弾いていませんか?
□「弾けるようになったら終わり」だと思っていませんか?
ご家庭の練習にも参考になるヒントがいっぱいです!
“ジャズピアニスト・数学教育者 中島さち子氏推薦”
「魅力的な人を育てる」花まる学習会が始めた、とっても面白くて革命的な音楽教室「音の森」。代表笹森さんの、音楽・教育・人間に対する深くてまっすぐな視点は、これからの時代の人生や教育のヒントに満ち満ちています!
■エッセンシャル出版社LINE公式のご案内
エッセンシャル出版社の公式LINEです。
今、エッセンシャル出版社のLINE公式に登録していただくと、
「風の時代を先取りする生き方」を実践しているギフトを生きるアーティスト・石丸弘さんの電子書籍をプレゼントしています。
その他、無料プレゼントや、オススメの情報、イベント情報などを配信しております。
是非、ご登録くださいませ。