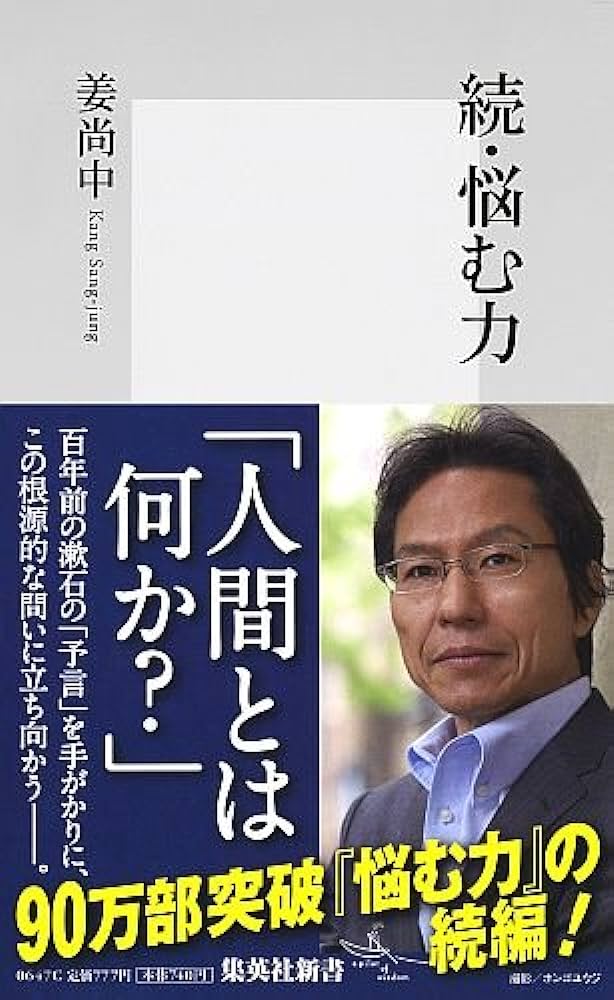【書名】続・悩む力
【著者】姜尚中
【発行日】2012年6月20日
【出版社等】発行:集英社
【学んだ所】
・自我や自意識は、共同体や社会との関係のなかではじめて「自分が自分である」という意識として成り立つ。⇒自意識の苦悩も、逆に幸福感も、社会の問題と密接に関係せざるをえない。
・いまの社会が病んでいる病気のタネはほとんど、近代のはじまりであった漱石たちのあの時代に蒔かれていた。=漱石が描いた五つの悩みのタネ
①お金
- 「道草」:縁を切ったはずの養父たちにつきまとわれ、かつての恩をネタに金をせびり取られる。
- 「心」:先生が深い人間不信に陥ったのは、田舎の親戚に両親の遺産をだまし取られたことがそもそものはじまり。
- 金銭の貸し借りのシーンは、程度の差こそあれ、漱石作品にほぼ例外なく登場する。⇒「三四郎」や「行人」では、それらはあってもなくても物語自体にはたいして影響はない。⇒にもかかわらず、そういう細かな話がわざわざ埋め込まれているということは、お金の問題が漱石にとっては衣食住に近いほど日常茶飯事であったからか、持病のように二六時中頭を去らない存在だったからか、いずれにしても、よほどの問題意識をもっていた。
- 漱石のころの資本主義は、現在のような金融資本を中心とするグローバル資本主義とは違っていたが、経営と所有の分離が進み、組織資本主義への移行にともなうさまざまな矛盾が露骨に現れてきていた。⇒漱石はロンドンに留学して、すでに世界の資本主義の中枢であった当時のシティを見ていたから、お金をめぐって人の心がどうなるかは、想像にかたくなかった。
- 同じころ、ウェーバーも、ドイツで市民的英雄の時代が終わり、資本主義はいかなる倫理的な支えも必要としない、強欲な賤民資本主義に変貌しつつあると見ていた。
②愛
- 漱石が考えていた悩みとしての愛を眺めると、単なる愛の問題というよりは、これまたお金と結びついたところで、いわく言いがたい苦悩のタネになっている。
- 「それから」:代助と三千代の恋愛は、代助に経済力さえあれば、はるかに単純なものだったはずだが、お金の問題がからんだために、物語は複雑になってしまった。
- 「明暗」:お延は、おのれの存在感をアピールしたい一心で、父親から金を引き出せない夫に代わって自分でお金を調達してきたりするが、「良人に絶対に必要なものは、あたしがちゃんと拵える丈なのよ」などと言い放つあたりは、金で愛(歓心)を買っているとしかいいようがない。
- 漱石の描く男女の関係というのは、江戸以前の心中文学に見るような惚れたはれたの世界ではなく、また、のちの四畳半的な純愛物語でもなく、ある意味、きわめて高度に現代的な「金と愛のある情景」。
- そのような側面は、ウェーバーにもあって、彼は目の前に展開されている近代合理主義のなかで、人間に残された魂を突き動かす崇高なる存在として、宗教と芸術と愛を幻視した。=愛なりエロスなりといったものは、単独で魅力を放つものではなく、作用と反作用のように、経済的なものと背中合わせで存在すると考えた。
③家族
- 漱石の主人公たちはたいてい独身か、子供のいない夫婦で、いる場合でも子供の存在感はなかった。⇒漱石の描く彼らは、いつまでも子供として親に相対している。
- 夫婦と子供からなる家族が最も基本的な共同体だとすれば、漱石の描く夫婦はそうなる前の段階であり、それゆえ「行人」の一郎とお直や、「心」の先生と奥さんや、「明暗」の津田とお延のように、緊張して張りきった糸のような不信劇が二人の間に展開される。
- 家庭というのは、ある時代まで、きびしい外界から身を守る避難所のようなものであり、共同体のなかで、ささやかながら、最も濃密で温かな団欒の場であったはずが、いつしかそうではなくなり、かすがいをもたない二つの個体が神経戦的バトルを繰り広げる、畳のリングになってしまった。⇒これはかなり今日的な現象であり、現代の夫婦にとってはさほど珍しくない、むしろリアルな悩みといってよい。⇒漱石はこの点においても先見の明があった。⇒核家族という言葉もない時代に、社会で最小単位の共同体である家庭を、社会で最小単位の修羅場としてとらえた漱石は、かなり先駆的であったといえる。
④自我の放出
- 自分らしくありたい、自分をアピールしたいと、きわめて強い自己顕示欲を抱いているにもかかわらず、実は自分が何者なのかよくわからない。
- そのため、自分は自分として超然としていることができず、他者のまなざしが異常に気になり、その結果、神経過敏症に陥ってしまう。
⑤世界への絶望
- パスカル「この無限の空間の永遠の沈黙は私を戦慄させる」=この宇宙のなかに、自分一人、ぽつねんと取り残されていることに気づいたときの心もとなさを表している。
- 実存的な空虚感に陥り、自分の人生に意味が見いだしえず、世界からその精神的な輪郭が失われて、自分が無へと滑り落ちていくような恐怖に苛まれることになる。⇒なぜ人はそのような恐怖や不安に陥るのかといえば、自分というものと、外の世界とのつながりが断ち切られているから。=つながりが切れているから、自分が何者であるかもわからないし、自分が目にしている相手やそのまわりのものの意味もわからない。
- 漱石の描いた人物のなかで、その最たるキャラクターをあげるとすれば、「行人」の一郎。⇒彼はまさに自分と自分以外のものとの関係がわからない。⇒彼は、時には自然の森や谷を自分の所有物のように感じたり、時には自分自身が神だと言い出したりする。=自我が突出して世界のなかでの自分の位置を見失うと、このような感じになる。⇒にもかかわらず、本人は、大学教授としての社会生活はいちおう営めていて、そのように外聞を繕うことができているだけに、なおのこと苦しい。
・漱石の時代に蒔かれた悩みのタネは、その後どれも大きく育って、いまの現代を取り巻いている。
①文明化(合理化)と、その延長線上に発展した経済のシステム
- ウェーバーは合理化を脱魔術化と呼び、この世界の秩序のなかから呪術や神を中心とする宗教的・形而上学的な意味が失われ、世界が科学的な因果律によって説明される、それ自体としては意味のない世界へと移り変わっていくことととらえた。⇒この脱魔術化によって、人間と人間の関係から成り立つ社会の秩序も、神意や自然の秩序を反映したものではなく、自由な人間の意思や作為によって無から形成されるべきものとなった。
- バラバラに存在する自由な個人が、社会の秩序を形成していくうえで新たな紐帯となったのは、社会契約論だった。⇒個人はみな自由なのだから、互いに権利を認めあい、互いに恩恵を与えあう関係を結ぼうという取り決め(約束ごと)をした。⇒それによって、社会の基本的なデザインが作りあげられた。⇒このとき、人と人を結びつける人為的な契約のモデルとなったのが、市場経済における交換関係。=だからこそ、お金は19世紀以降、圧倒的な意味をもつようになった。
- アダム・スミスは、「見えざる手」という言葉を使って、孤立した個人の利己心が、市場のメカニズムを通じて人と人とを結びつけることを明らかにした。
- ところが、経済のシステムは営利追求とともにどんどん膨張して変形していき、19世紀末から20世紀初めの漱石とウェーバーのころには、初期の形態からかなり逸脱していた。⇒人と人とが相互の便益のために貢献しあい、モノやサービスを公正に交換しあうような関係ではなくなり、もてる者ともたざる者の差がとてつもなく開いて、あなたの幸福は私の不幸、あなたの不幸は私の幸福といったゼロ・サム・ゲームが、大っぴらに繰り広げられるようになった。
- 逸脱、変形した経済のシステムはその後もさらに拡大を続け、現代には、マネーがマネーを呼ぶマネー経済となり、カジノ資本主義の様相を呈するようになった。⇒そして、不信が利益を生み、利益が不信を助長するという、いわば悪魔的なスパイラルが、金融中心のグローバルな資本主義のなかで形成されていくことになった。
②近代の到来とともに人間同士のつながりが切れ、バラバラの存在になった。
- これは「原子化」や「群衆の誕生」といえる事態を指している。⇒この現象が加速し、人間の孤独化が進み、むき出しの自我という悩みのタネが一足飛びに育っていくことになった。
- 名もなく顔もなく互いに何の関係もない匿名の個人の群れが力をもつ特異な現象が、漱石やウェーバーのころ、社会現象として現れた。⇒ウェーバーは社会学者なので、当然、そのような匿名の群衆の台頭に注目したが、漱石も興味深く観察していた。
- 「坊っちゃん」は日露戦争の戦勝後の明治39年(1906年)に発表されていて、最後のあたりに日露戦争の祝勝会の場面が出てくる。⇒物語ではこのとき乱闘が起こり、坊っちゃんも巻き込まれて大暴れして新聞に書かれ、四国を去る遠因になるが、これは、その前年9月に東京で起こった日比谷焼打ち事件を念頭に置いている。⇒これは、日露戦争の講和の内容に不満をもった人びとが起こした暴動で、まさしく群衆の誕生を意味していた。⇒日本では、日比谷焼打ち事件を最初の大きなきっかけとして、いわゆる烏合の衆である群衆が大きな力をもつ事態が頻発することになるが、漱石はその萌芽の光景を、いち早く小説のなかに表現していた。
- そのようにして生まれた不特定多数のバラバラの個人は、その後の社会のなかで、変動期になると急進化し、安定期になるとその多くが「私の世界」に閉じこもる傾向を見せた。⇒こうした現象は、現代のネット社会において、より急速に増殖しつつあるといえる。
- ネット社会では、形状としては、すべての個人が水平的に平等で、どこかに中心があるわけでもなく、しかも、みながどこにも固定されない形で横につながっている状態。そしてみなが直接目標にアクセスできる形。⇒そうした状況は、カナダの哲学者として高名なチャールズ・テイラーの言葉を借りれば、直接アクセス型社会が到来したといってもいいかもしれない。⇒このような社会で最も危惧される点は、人と人のつながりにおいて一切の仲立ちが必要とされないということ。
- 直接アクセス型社会が個人にとってよいのかといえば、必ずしもそうではない。⇒なぜなら、何物をも介さない以上、その人がすべて自分で判断し選択しなければならないから。⇒これは、ある意味で非常にしんどい。そのようなことは、普通、個人一人では背負いきれない。⇒だから、いきおい他人の動向を気にすることになる。
- 個人志向型でありながら、実はきわめて他人志向。⇒そこでは、相手がどのような反応をするかということを常に考えながら、自分も意思を決定していかなければならない。⇒相手のほうも同じことをするから、互いが互いのことをあらかじめ想定しながら、同時に相互に評価しあい、しかも間には反省作用も緩衝作用もないという、非常にシビアな状況にならざるをえない。
③公共領域が大きな歪みをきたしつつある。
- 平たくいうと、公共領域が有名無実化しつつある。もっというと、消滅しかけている。
- 本来、公共領域というのは経済の世界以上に、政治の世界において重要な意味をもってきていた。⇒デモクラシーの社会では、人びとはそこで議論し、意見が集約され、それらが政党によって媒介されて、国民全体の意志になると想定されてきた。⇒ところが、直接アクセス型社会となって、個人が匿名で直接公的な空間にアクセスするとなれば、極端な話、政党の役割や存在価値はますます小さくなってこざるをえない。
- これまで、政党というものは、社会のなかの部分的な利害を集約・媒介し、政治全体の意志決定に入力する役割があるとみなされてきた。⇒しかし、個人が直接目標にアクセスしていくなら、そのようなまどろっこしいことを中抜きする動きが出てきても不思議ではない。⇒その結果、匿名の不特定多数の個人の自由意思が民主的な総意を決定することになる。
- 匿名の不特定多数の個人の意思とは、市場と同義語。=つまり、市場が、政党による民主的な代表制に代わって、政治を動かすことになる。⇒市場が政治を動かす。=それは、デモクラシーの危機につながるをえない。
- 国民(人民)主権のデモクラシーの社会では、まがりなりにも、国民の総意(具体的には世論によって形成される国民の意思)に基づいて政治が行われ、それを集約して政府ができあがり、具体的な政策が実行される。⇒ところが、直接アクセス型社会では、匿名の、しかも主権とは無関係の市場がノーといえば、政府はお払い箱。⇒そして、ノーと叫ぶその市場の正体は何かといえば、かつて焼打ちや市電襲撃という騒動を起こした烏合の衆とさほど変わらない。⇒少なくとも、いく度となく繰り返されたバブルとその崩壊の歴史を見れば、市場こそ何よりも合理的であるなどという理屈はもはや成り立ちえない。