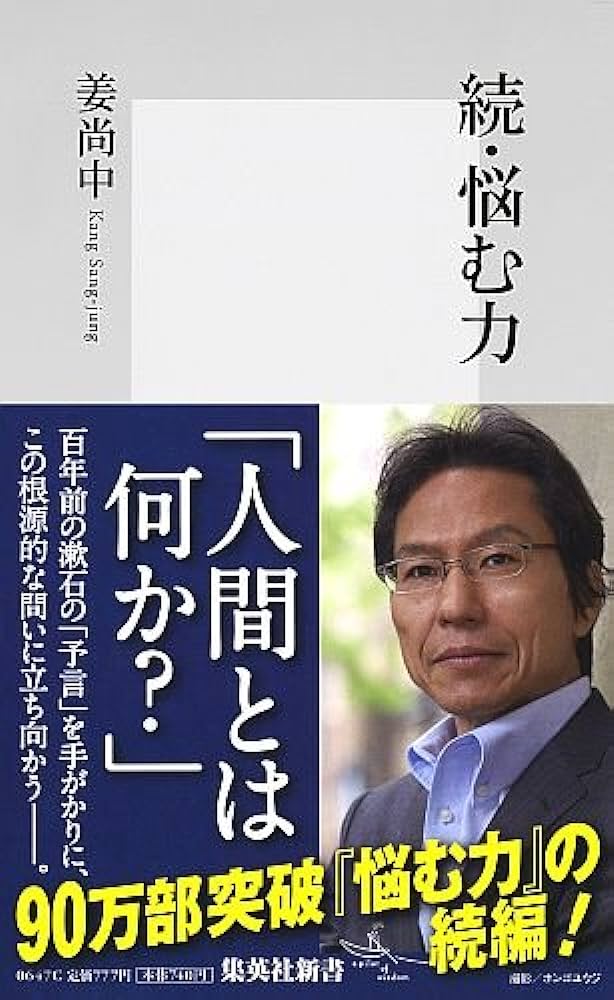【書名】続・悩む力
【著者】姜尚中
【発行日】2012年6月20日
【出版社等】発行:集英社
【学んだ所】
・漱石が最もこだわって、それこそ死ぬまで悩みつづけたのは、人間の自意識の問題。⇒漱石が、自我、自己本位、自覚心、self-consciousness、個人主義、時には己れという言葉で言い表すこともあった自意識は、人間が文明のなかで獲得した叡智ではあるが、諸刃の剣であって、同時に、人間に大きな不幸ももたらした。⇒これを手にすることによって、人は人類史上最も生きづらい生を生きなければならなくなった。
・漱石の主人公たちはみな自意識の犠牲者といえる。⇒どう見ても楽しそうでない人生を送る彼らのその苦悩の源は、みな自意識。
・人と人との関係は、土俵上で進退きわまった相撲取りの腹がハアハア波打っているのと同じ。
・人智、学問、百般の事物の進歩する=すなわち人間の知性が進歩するほど、人間は衰弱して滅亡への道をたどっていく。⇒この皮肉な逆説を、漱石は明治33年(1900年)にイギリスに留学したときに悟った。
・イギリスは当時、世界最先端の文明を誇る一等国であり、同時に世界最先端を誇る個人主義の国だったが、そこに生きる人びとは、漱石の目には明らかに、幸せそうには見えなかった。⇒みな紳士的、淑女的にスマートに交際しているのだが、打ち解けた信頼感や団居や情愛といったものは乏しく、自意識過剰による緊張と、孤独と、殺伐の感じばかりがある。それを見て、漱石は暗澹たる心持ちになった。⇒自分たちはこの彼らを手本にしようとしているのだ。=これと同じ道をたどるのだ。⇒そして、危惧した通り、実際、日本人はそれほど間をおかずして、西洋人と同じ自意識過剰の病にかかってしまう。
・漱石の主人公たちはみな、自意識の牢獄のなかに閉じ込められている。=漱石自身が迷宮のようになって、そのなかでさまよっている。⇒ものをよく考える知識人ほどそうなってしまうという悲喜劇も、そこにはある。⇒漱石は、近代という時代が選び取ってしまったそんな不幸な精神を、執拗に描きつづけた。
・近代という時代に、これほど自意識が突出したのは、自由というものは、基本的な原理になったから。=この世界に存在するありとあらゆるものは、すべて個人の意思と個人の叡智をもって自由に作られ、それによって立つ社会がよい社会なのだという観念が、人びとの上を覆っていたから。⇒これを逆にいえば、それ以前は、個人は自由ではなかったということ。⇒最大の違いは神との関係で、かつては、人は神と結ばれ、神を前提とし、その下に、ある秩序をもって形成されている世界の一員だった。⇒しかし、近代になると、そのつながりが切れて、個人は自由放免となり、自由な意思で生きてよいことになった。=宗教から切り離されることによって自由な個人というものが誕生した。⇒同時に、神によって定義されていたこの世のいろいろな出来事の先験的な意味も失われ、人間がその空白を埋めるように自由に意味を与えていくことができるようになった。
・それまでは、自然や神といった実体を反映していると考えられた秩序に慣習的に従っていれば、よくも悪くも人生をまっとうできていたのに、近代以降の人びとは、自分は何者なのかとか、自分は何のために生きているのか、といった自我にかかわることを、いちいち自分で考えて、自分で意味づけしていかなければならなくなった。⇒このような状況のなかで、人間の自意識というものが限りなく肥大化していく。
・しかも、一人ひとりがブツブツと切り離されていて、つながりがなく、共通の理解もない状態だから、互いに何を考えているのかわからない。⇒そのために、それぞれが内面的には妄想肥大になり、対人的には疑心暗鬼となり、神経をすり減らしていくことになる。⇒あの「心」の先生の有名な言葉、「自由と独立と己れとに充ちた現代に生れた我々は、其犠牲としてみんな此淋しみを味わわなくてはならないでしょう」の通りの世の中になる。
・アメリカの心理学者でプラグマティズムを世に知らしめたウィリアムズ・ジェイムズは近代的合理主義精神のもとで、多くの人びとが深刻な精神不安に陥り、心のよりどころとなるものを熱烈に求めていることに注目した。⇒ジェイムズは、科学万能主義によって、宗教がいかに過去の遺物の烙印を押されようとも、宗教は人間の深層の部分に根を下ろした核のようなものであり、絶対に駆逐することはできないと考えた。⇒近代文明のなかで個人主義が進行し、人びとの孤独が強まり、また自意識がどんどん肥大していくからこそ、逆説的に、宗教は昔よりも自覚的に、かつ熱烈に求められるようになると考えた。
・近代という時代のなかで個人主義が進んでいく以上は、個人の信仰心というものも、徹底して個人化せざるをえない。=宗教はかつてのように人びとを結びあわせる共通項として働くよりも、限りなく個人の感情にかかわる個人の問題として立ち現れるようになった。⇒すると、近代においては、個人の感情というものこそが、人間の本質を探究するための非常に重要な要素であるということになってくる。⇒それはまた、人が自分が何者であるかを考えたり、自分が生きるうえでの望みや喜びを考えたりする際にも大きな手掛かりとなる。そこのところをジェイムズは追求している。
・ユダヤ人の精神医学者のV・E・フランクルは「ホモ・パティエンス」(悩む人)という人間の定義を提唱した。⇒この言葉には、生きている限り悩まずにはおられない人のほうが、人間性の位階においてより高い、という意味がこめられている。⇒第二次世界大戦中はナチスによって強制収容所に入れられ、想像を絶する迫害を受けた。⇒しかし、彼はそれをくぐり抜けて生き残り、大戦後は、自らの過酷な経験を生かして、人の心の闇と、生きることの意味を解き明かす仕事に、死力を尽くす。⇒つまり、「ホモ・パティエンス」とは、収容所のなかで、「死んだほうがましだ」「生きている意味などない」という絶望に駆られつづけた環境で、それでも「人間的に悩みたい」という願望をもちつづけた果てにたどり着いた言葉。
・悲劇に見舞われて不幸な状態にある人ほど、宇宙に存在する深い真理を垣間見ることができる。⇒ジェイムズとフランクルも人が苦悩することに大きな価値を置いている。
・ジェイムズもフランクルも漱石もウェーバーも、悩める人の心や感情が、他者との出会いのなかで揺らぎ、いろいろな方向に動き、変化する、そのありようを、それぞれの分野、それぞれの立場からとらえ、つづっていった。⇒ジェイムズが人びとの宗教的体験のなかに人間性の本質を探ろうとしたこと、ウェーバーが社会学でやろうとしたこと、文学の世界で漱石が試みたこと、そして、精神医学の世界でフランクルが試みたこと。これらの目的はみな同じだったといえる。=近代という時代における人間の苦悩とその意味を探究しつづけた。⇒彼らはみな、自らが「悩む人」だった。
・4人とも、「人間とは何か」という根本的なテーマを見失うことはなかった。⇒自我や自意識、さらに悩みや苦悩が問題になるのも、そのような普遍的なテーマとかかわっている。
・ジェイムズによると、人はギリギリ何かの瀬戸際に立たされたとき、宗教人になるか芸術人になるか、どちらかに分かれるという。
- 徹底的に自己否定して、地獄のような苦悶のなかに落ち込むタイプは宗教型。
- 絶対的に自己肯定して、それを作品表現として昇華するタイプは芸術家。
・ジェイムズとフランクルは宗教型だが、意外にも漱石もウェーバーも宗教型だった。⇒彼ら二人とも自分以外のものを信じられないところに悩みのもとがあって、それゆえ宗教の門に入れず七転八倒することになった。⇒でも、信じるものを求めつづけたという点では、逆説的に宗教人といえる。
・いちばん重要なことは、求める気持ちにある。=求めることが、宗教心に通じている。⇒人間の深い苦悩は、門に入ってしまいたいという苦しみよりも、宗助や漱石やウェーバーのように、門に入ってしまいたいのに入れないという苦しみなのではないか。⇒門に入ることができさえすれば、苦しみは軽くなる。では、なぜ入れないのかと考えると、やはり自意識の肥大というところにもどってこざるをえない。
・「悩む人」(ホモ・パティエンス)という人間の類型は、世俗化された近代という時代における最も本質的な人間のあり方を指している。⇒いまでは、痛みや苦しみをうまくごまかしてくれる「発明された幸福の方程式」も、もう通用しなくなった。