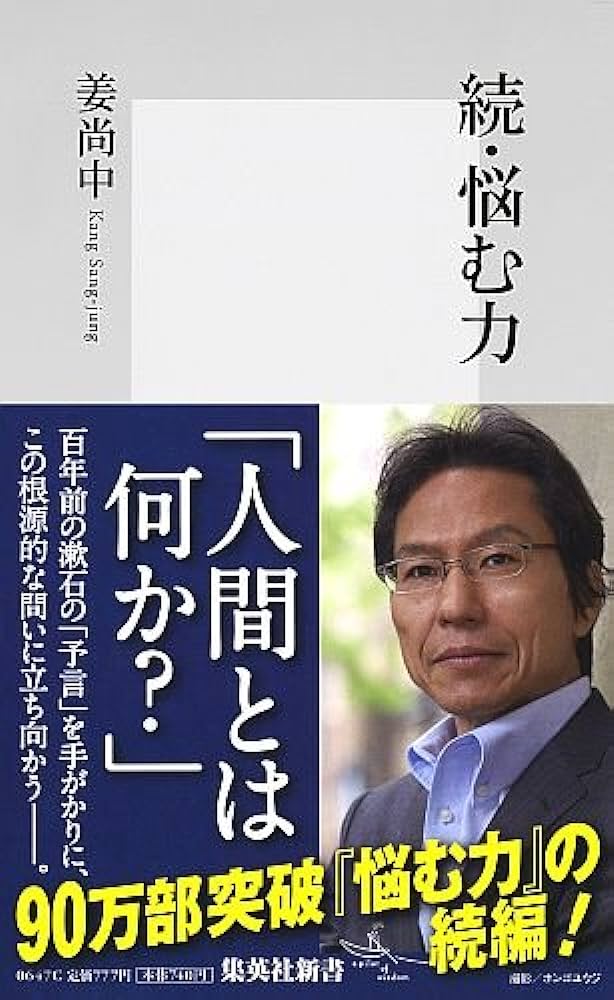【書名】続・悩む力
【著者】姜尚中
【発行日】2012年6月20日
【出版社等】発行:集英社
【学んだ所】
・人間はどこかに、いまの私はホンモノの私ではなく、どこかにあるはずのホンモノの私を探し求めたいという欲求がある。⇒自分らしくありたい、自分に忠実な人生を歩みたい。ベスト・ワンでなくともいいけれど、オンリー・ワンでありたい。⇒こうした切実な願いは、自己実現の欲求の現れ。
・重要なのは、自分の真価(自分らしさ)が発揮できるスペシャルな何かを見つけ、それに打ち込むこと。⇒人との競争に勝つことよりも、自分の世界で自分らしく生きるほうがよっぽどカッコいいということ。=ベスト・ワンよりオンリー・ワンの生き方。⇒しかし、そのようなホンモノ探しには複雑な気持ちにさせられてしまう。⇒ホンモノの自分、自分らしさを見つけ出すことは至難の業だから。
・うつの人、引きこもっている人、自殺未遂の人、隘路に迷い込んでいる人びとを、ただ何となく時代の病理として扱うのではなく、自己実現に失敗した凡人の群れと見るのでもなく、精神的な弱さとして切って捨てるのでもなく、彼らをむやみに自分らしさの探求に駆り立てるものをしっかりと見つめ直しておく必要がある。
・ホンモノ探し文化から浮かびあがってくるのは、人とは違う自分らしさを求める願望は、絶対に自分だけではかなえることができないということ。⇒なぜならば、いくら自分を鏡に映して自分だけのナルシシスティックな世界に浸ってみても、人が「いいね!」と評価してくれなければ、ホンモノをアピールしたとはいえないから。⇒独我論とコミュニケーションとの間で宙吊りになっている状態で、そのような矛盾した努力を全員が必死になってやってるのが、ホンモノ探しの文化。
・ホンモノ、自分らしさの探求から生まれる悩みのタネもやはり漱石たちのころに蒔かれ、その芽を萌していた。⇒漱石の物語を見ると、あちこちで、登場人物たちが自分探しレースに参加している姿に出くわす。
- 「三四郎」の三四郎:九州から大都会東京に出てきて、右往左往する。⇒彼のキーワードは、「迷える子(ストレイ・シープ)」⇒漱石の子供たちのなかでは穏健で善良なタイプ。⇒彼は自分の目の前にいくつか世界を並べてみて、あれでもない、これでもない、そちらはどうか、どれがいちばんよかろうかと、一生懸命に考えてみたりする。⇒あるいは、何か無性に満ち足りないので、友人の与次郎のすすめに従って市電であちこち行ってみたり、寄席に行ったりする。⇒しかし、答えはなかなか見つからない。
- 「それから」の代助:彼のキーワードは、「虚無」⇒都会の高等遊民として世の中をニヒルに見切っているが、不敵に構えているというよりは神経質なたちで、周囲の人間とは違う自分だけの世界を懸命に模索している。⇒舶来の香水を購入したり、鏡に映る自分の姿にうっとりしたり、花を買って自分の部屋のなかにいけてみたり、ずいぶん洒落たことをやっている。これは、いわゆる顕示的な消費で、ハイソサエティで洗練された自分を演出している。
- 「行人」の一郎:究極の自分探しの人。⇒キーワードは、「自我の牢獄」⇒彼の場合はあまりに自己実現願望が強すぎて、結局どうなりたいのかわからない。⇒超弩級の人間不信と、超弩級に他者を求める気持ちが拮抗している。
・同じような孤独な都会人のホンモノ探しは、ウェーバーのドイツでも、ジェイムズのアメリカでも、イギリスでも社会現象になっていた。⇒ジェイムズは、当時のアメリカで起きていた、「いまのあなたはホンモノではない」「もっと素晴らしいあなたを発見しましょう」というスピリチュアルブームに触れている。⇒それは、新思潮と呼ばれ、人間の勇気や希望には無敵の力がある、だからその力を養って、不安や取り越し苦労をなくせば幸福になれますよといった、マインドコントロールのような運動だった。
・19世紀末は、それまで特権階級のなかだけで享受されていた文化が大衆化していくとば口にあたっており、大衆消費社会のなかで、ヴァルター・ベンヤミン言うところの「複製文化」がはじまろうとしていた。⇒日本の漱石も、時代が移り変わってさまざまな複製が増えはじめたなかで、自分だけはホンモノでありたいと望んだ人びとを、自分も含めて描こうとした。
・ホンモノ、自分らしさを探究する文化は、さらに18世紀末ヨーロッパのロマン主義にまでさかのぼる。⇒合理主義や資本主義の功利性や無味乾燥な計算の世界、道具主義的な世界に自分たちの社会が占領されていくなかで、人間というものは、本来、そのような機械的なものでは測れない、純粋無垢な自然として存在していたと考える人びとが増えた。⇒彼らは、そうした無垢な世界から汲めども尽きぬ力を取りもどすことができるに違いないと考えた。⇒その大きな流れのなかに、ホンモノの自分探しの最初の一滴がある。
・ウェーバーのころ、ドイツでは第一次世界大戦(1914~18年)のあとの混乱のなかで時代を変えようとする若者たちのうねりが起こる。⇒ウェーバーはそれをカーニバルと喝破し、ローザ・ルクセンブルクやカール・リープクネヒトといった人びとをこんなお遊びをやって、必ず反動の時代が来るのがわからないのか、と徹底的にこきおろした。⇒彼はロマン主義的な犯行は、結局、資本主義の巌のような盤石さにぶつかって粉砕されるだけだと見抜いていた。=そして、実際にその通りになる。
・革命への狂騒を醒めた目で見ていたという点では、漱石も同じ。⇒日本でも、当時一部で社会主義らしい動きが出てくるが、漱石もまた、そのような反体制的な思想や潮流からは、まったく距離を置いていた。⇒かといって、現況に巻かれるのがよいと思っていたわけではなく、怒涛の勢いで流れ込んでくる西洋的合理主義や資本主義の潮流を、覚悟して受け入れるという立場だった。
・今は、自分はどう生きていくかという、せっぱつまった自分探しをしている。⇒先の見えない暗いトンネルのなかをてさぐりでさまよいつづけるのか、それとも、何とか自分はうまく抜け出して未来を天皇できるところに浮上できるのか、ぎりぎりの闘いを強いられている。
・現在の自分探しは、いよいよ末期的な現象が頻発する社会のシステムと、いろいろな局面で密接に関係している。
- 究極までに発達したグローバル資本主義のなかでは、ホンモノ(自分らしさという唯一無二のもの)は殺がれる方向に向かわざるをえない。⇒人間はどこでも誰でも代替可能、入れ替え可能な、等質な商品になることを求められている。⇒すると、それに必死に抗おうとして、自分だけの個性やオリジナリティを求める気持ちが強く出てこざるをえない。⇒それが、切実なホンモノ探しの背景になっている。
- 「ホンモノを探せ!」という、キャッチコピーのような言説が巷に満ちあふれていることがあげられる。
・漱石の創作メモ「断片」のなかの言葉「天下に何が薬になると云うて己を忘るるより鷹揚なる事なし無我の境より歓喜なし。カノ芸術の作品の尚きは一瞬の間なりとも恍惚として己れを遺失して、自他の区別を忘れしむるが故なり。」⇒ホンモノ探しの親分のような漱石が、ホンモノの自分を探せとは言わず、反対に、自分を忘れろと言っている。
・同じく「断片」のなかの言葉「此弊を救うにはたとい千の耶蘇あり。万の孔子あり。億兆の釈迦ありとも如何ともする能わず。只全世界を二十四時間の間海底に沈めて往来の自覚心を滅却したる後日光に曝して乾かす外に良法なし。」⇒自分というものを滅するためには、24時間、全世界を海の底に沈めろとまで言っている。
・もし、ホンモノの自分というものに本当にこだわるならば、むしろそれを忘れたほうがいいかもしれない。⇒心ある人は、「自分を探せ」とは、決して言わない。⇒漱石だけではなく、「幸福論」を書いたアランやイギリスの思想家バートランド・ラッセルたちだって、自分だけに興味をもつなと言っている。
・その真反対に、「ホンモノを探せ」と叫び、あおっているのは資本主義。⇒このスキのない魔物のようなシステムは、商品となるものを見つけ出して利用するのが、とてもうまい。⇒ことに不安の匂いのするものを利用するのが、とてもうまい。⇒ホンモノ探し、自分らしくありたいという願いが、自分に忠実であろうとする近代的な自我の一つの徳性を示しているとしても、それが時にはナルシシズムや神経症的な病を作り出しかねないことにもっと注意を払うべき。