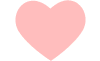グレゴリー・ベイトソンが、コージプスキーの、The Map Is Not the Territory, and the Name Is Not the Thing Named.を引用したのは、『精神と自然:Mind and Nature』のII章「誰もが学校で習うこと」のなかでのことでした。
- 精神と自然―生きた世界の認識論/グレゴリー ベイトソン

- ¥2,100
- Amazon.co.jp
そこでベイトソンは、
コージプスキーは、哲学者としての立場から、人間の思考に規律を持たせたいと願って、あの言葉を述べたものと思われる。しかしそれは成功することのない企てである。彼の言葉を、人間の精神過程の自然史という視点から見てみると、事情はさほど単純ではないのだ。
また、次のようにも述べています。
コージプスキーの使った”地図”のメタファーは実に便利なもので、事実多くの人間に役立ってきたわけだが、最後まで煮詰めてみれば、結局彼は、結果は原因に非ず、と主張したにすぎない。
ここで「結果」は、わたしたちの五感と神経回路を介して、取り込まれた「土地」が「地図」に変換されたことを指します。「原因」はインプットされた「土地」の情報です。
変換された「地図」と、元の情報「土地」は、当然同じものではありません。で、すでにお気づきの方もいらっしゃると思いますが、「地図は、書き換えることができる」とやれば、NLPです。
ベイトソンは、変換された「地図」と「土地」との「差異」からスタートしようと述べているわけです。名前が、そう名付けられたモノとは別物であることなど、当然であると言っているのです。
「差異」の発生を「予防」しようとするかのような「科学と正気」の論法こそ、不健全です。というより、それを言葉で伝えようとしているところにすでに大きな自己矛盾があって、ハナから破綻している。
そもそもが、飼っているネコの名前を呼べば、そのネコの顔が浮かんだりしますが、どこかに遊びに行っていて呼んでも姿を現さないとき、名前をそのネコの代替物にして「名前を撫でてやる」なんてことはありえないわけで。
今さら、あんたに言われるまでもないよって感じです(爆)
「ドイツ人は○○だ」とか、「日本人ってやつは」、といった全称命題での物言いにはヴィトゲンシュタインも、注意を促していますが、そこから生まれる間違いを、リテラルな言葉の語用レベルで防ぐなんていう「衛生論」が有効であるわけがありません。
ずいぶんムダな寄り道をしたような気もしますが、お陰でベイトソンにガチンコ再会することができたわけです^^
シンプルマッピング・サイクルにも十二分に役立てていくことができます。
「学習とコミュニケーションの階型論」についても、これから第3弾と合わせて紹介していきます。
ベイトソンも「サイクル」に注目した科学者です。