明かりを考えてみる
こんにちは、kuwayamaです。
今日は「照明」のお話。
皆さん、室内の「明かり」を考えるとき、
何を思いつきますか?
照明器具そのものもあれば、光の色味、
明るさ、間接照明、スポットライトなどなど。
照明を計画するときに主に指標となるのが、
「色温度(K)」「演色性(Ra)」「光束(lm)」
今回は「色温度(K/ケルビン)」に関してのお話です。
明かりの色は、主に「電球色」と「昼白色」があり、
それぞれ「オレンジ掛かった色」と「白っぽい色」です。
どちらの方が色温度が高いかご存知ですか?
色温度が高ければ高い程赤(オレンジ)くなりそうなイメージが
ありますが、実は色温度が高い程、白っぽい(青白い)光に
なるのです!
(そういえば、理科の実験でガスバーナーの青い部分の方が
赤い部分より熱い、って習ったことをふと思い出しました笑)
先日、現在設計中のお客様とのお打ち合わせで
実際に照明メーカーからLEDの照明器具を借りて実験しました☆

左の明かりが3000K、右が2700Kです。
かなり印象が違いますよね。
塗装サンプル6色(どれも白系)に当ててみると…
<3000Kの照明を当てた場合>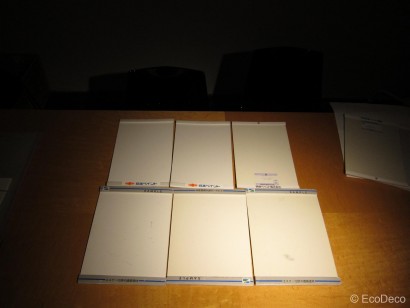
<2700Kの照明を当てた場合>
照明の色温度と光が当たる面の色によって、こんなに印象の違いが。。。
今回は「2700K」の照明に決まりました!
今回お話しした「色温度/K」だけでなく、照明器具のデザイン、
配灯の仕方、光の当て方など、いろんな角度から検討し、
なかなか悩むところではありますが、同じ内装の部屋でも
照明が違うだけでがらっと雰囲気が変わるので非常に大事なポイントです!
落ち着くカフェの照明が間接照明なのか、何色なのかとか、
まぶしいor暗いと感じる空間には照明が何個付いているのか、
などなど、明かりに目をむけてみると新しい発見がありますよ◎
EcoDecoの事例もそんな視点で見てみると面白いかも、です!
EcoDecoの事例紹介はこちら▼
kuwayama

播磨坂のリノベーション 床下に配管が通る

>>>>>>>>>>これまでの播磨坂沿いのリノベーション<<<<<<<<<<
①重要事項に関わる調査報告書は、その名の通り重要です。
②リノベーションがスタート!
③現場に墨を出す
④コンクリートブロックを積む
本日も播磨坂のお話。
現在床を作っている最中なのですが、
その前にしなければ行けない事があります。
それは、設備配管。
水栓や排水のある所まで、
排水管や給水管、給湯管を設置しておくのです。

ということは、着工してから解体が完了するまでに、
設備機器の位置や仕様を決めておかないといけないという訳です。
ですので、この写真の状態から変更するとなると、
やり直しとなり、増額や工期延長となってしまうのです。
注意しないといけません。
とくに排水管は、勾配を取る必要がありますので、
シビアです。

ちなみに、青い配管が給水。
赤い配管が給湯。
グレーの配管が排水。
分かり易くして、現場での間違いも出ない様になっています。

こうして見て行くと、当たり前の事なのですが、作り方には順序があって、
これをしてからじゃないと、あれができない。
という、順序を守って作っていいくのです。
この順序を考えて作られたものが「工程表」という訳です。
という訳で、現場に行くたびに、工程に遅れは無いか?
遅れているとしたら、どうしてなのか?
遅れを取り戻す事は出来るか?
と、施工会社と話をするわけです。
(okada)









