というのは冗談です。これから書くことぐらい「とっくに知っているよ」と言われてしまうかも知れません。
AERAでしたかどこかの雑誌に「Wikiばか」という言葉があると書いてありました。
「ウィキペディアに書いてありましたから」と言って平然としている人のことです。
取引先へ提出する企画書にウィキペディアのコピーを使っているとか。
ウィキペディアは一次情報として調べるにはたしかに重宝します。
その事柄についての外観がまとまっているので、全体像を把握するのに役立ちます。
しかしながら正確性や真実性と言ったところでは不安が残ります。
ウィキペディアに限らず、インターネット情報というのは真贋混じり合っているのが実際のところ。
偽情報をつかまないようにするには、どうしたら良いでしょうか。
その1 ソースに当たる
「内閣府の発表によると」「文部科学省では」とあれば、まずは政府のHPをググってみます。
報道発表した資料であれば、現在はほとんどがHPに掲載されていますから。
実は新聞やテレビの報道機関は、政府発表資料の概要(サマリー)に基づいてなされていることがほとんどです。
記者も報告書全文を読んでいることは少ないと見ています。
というのは、サマリーには意図的に意見を誘導するようなことが書いてあったりするからです。
本文を読んだら「そうなのかな?」と首をかしげたくなることも多々あるのに。
政府以外のものでも、大概発表ならどこかにソースは見つかりますね。
その2 複数の資料に当たる
ウィキペディアだけでなく、大学教授や報道機関などのHP,ブログ等の信頼出来る専門家や機関の情報と照らしあわせてみます。
非公式の情報の場合は難しいですが、その道の専門家が個人でたちあげているブログを読むという手もあります。
複数の所属と立場が異なる人の意見を総合して、落とし所はこのへんなのかと判断します。
その3 印刷物に当たる
やはり書籍や雑誌など印刷されたものを探して、裏付けできるかどうか見てみます。
論文等はインターネットで入手可能なことも多いので、それはここに含めます。
その4 反対意見を探す
世の中、およその事は賛成の人がいれば、反対の人もいるもの。
反対の意見を探して読んでみると、どちらの言い分に説得力があるかで、自分の意見を決めるための判断材料となります。
一方の立場だけでは、どうしても偏りますから。
例えば原子力発電所の存続問題について言えば、推進派の意見には廃棄物の最終処分という決定的な弱点があるので、納得出来ないとかね。
ブログのような個人的な媒体では、軽く済ませてしまうのでミスもあります。
これは他の人のブログもそうでしょうし、自分にも誤りがあるかも知れないと思っているということです。(羊)

- 知的複眼思考法 誰でも持っている創造力のスイッチ (講談社プラスアルファ文庫)/苅谷 剛彦
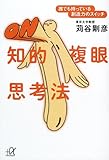
- ¥924
- Amazon.co.jp
- 知的複眼思考法 [ 苅谷剛彦 ]

- ¥924
- 楽天