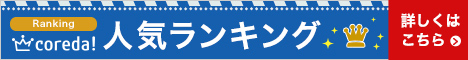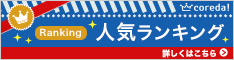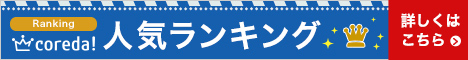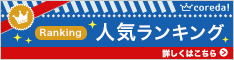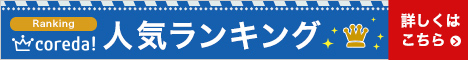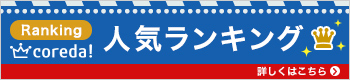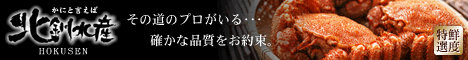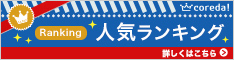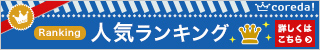火曜までの二日間。
美術館で巨大額縁入りの絵画を移動するという仕事を仰せつかったオレは、筋肉痛でぐでぐでだった。しかし、そんなことは言ってられない。今日は、決行の日だ。
オレは、切り出し方から誘い文句に至るまで、練りに練っておいた。しかし、いくらシミュレーションしたところで、相手があることだから、賽の目が出ないことには分からない。だから、どう転んでもいいように、台詞のメモを取った。さらに、断られた時にどう返すかまで決めていた。逃げの姿勢とも取れるが、これっきりにしようとしていたわけではなく、次に繋げたかったのだ。
意を決したオレは、Brixton駅の公衆電話へ。
ハードハウスのようにばくばくの心臓を落ち着かせようと、電話機の前で深呼吸をする。ただでさえカタコトな言葉、せめて、決めた台詞だけは、どもったり詰まったりはしたくなかったのだ。
20p硬貨を投入し、もらった番号を押す。
「もしもし。」
「こここ、こんばば、こんばんはKelly。」
「(笑)なに、その声?」
・・・やべえ、のっけから声が上ずった。
「大後悔時代」と書かれた巨大な岩石が天から降ってきて、脳天を直撃した。
一世一代の大勝負だというのに、オレのバカバカ・・・
台詞の書かれたメモを見ることも忘れ、何がなんだか分からなくなってしまった。
続く。