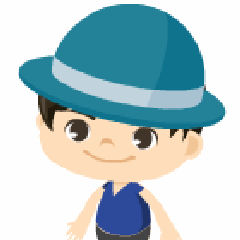さて、江戸時代末期の浄土真宗の重大な出来事・「三業惑乱」を紹介します。
この頃、全国に、「十劫安心」が蔓延っていました。
十劫安心とは、「十劫の昔に、我々は既に助かってしまっている」という異安心です。
「だから、今更求める事も、聞き歩く事も要らぬ」
「弥陀の救いはいつとはなし」
「この世で助かったという事などはない」
というのが特徴で、これが親鸞聖人の教えに反する邪義である事は、明らかです。
この「十劫安心」を正すべく、六代目能化の功存は、「信心獲得せねば後生は一大事」「弥陀をたのまねば絶対に助からぬ」等と力説しました。
しかし、「信心獲得」を強調した反動で表れたのが、「三業安心」です。
「三業安心」とは、「身口意の三業で、阿弥陀仏にお願いせねば助からぬ」「三業がこうなったのが獲信だ」と主張する信仰を言います。
この邪義を、功存の後を継いだ七代目能化・智洞が、公然と唱えたのです。
智洞の邪説をきっかけに、真宗の道俗がこぞって「私はこのように弥陀にお願いした」「お前はどのように弥陀をたのんだか」と三業を詮索するようになり、各地が騒然となっていきました。
こうして、本願寺を揺るがす信仰の大争乱へと発展していったのです。
蔓延する「三業安心」の誤りを正そうと、各地から実力ある真宗学者が立ち上がりました。
その代表が広島の学僧・大瀛(だいえい)です。彼は、智洞らの説を弾劾した本を出版。これに智洞側からは、何の反論もなく、教義上、智洞側の敗北は明らかとなりました。だが智洞達は、大瀛ら反対派に、出版妨害や風説、政治的な謀略等で応酬し、次第に暴動等、流血の惨事に至ります。
事態を重く見た寺社奉行が仲介に入り、審議の末、智洞側の邪義が明らかとなりました。智洞をはじめ、取り巻く学僧達は、本山から一掃され、本願寺を二分した大法論はこうして決着したのです。
この「三業惑乱」以来、真宗の道俗は、肝要の「たのむ一念」を毛嫌いし、「信心獲得」をろくに説かなくなりました。
三業惑乱の反動で、「十劫安心」に逆戻り、以後、明治・大正・昭和と衰退の一途を辿ったのが浄土真宗の歴史と言えるでしょう。
この頃、全国に、「十劫安心」が蔓延っていました。
十劫安心とは、「十劫の昔に、我々は既に助かってしまっている」という異安心です。
「だから、今更求める事も、聞き歩く事も要らぬ」
「弥陀の救いはいつとはなし」
「この世で助かったという事などはない」
というのが特徴で、これが親鸞聖人の教えに反する邪義である事は、明らかです。
この「十劫安心」を正すべく、六代目能化の功存は、「信心獲得せねば後生は一大事」「弥陀をたのまねば絶対に助からぬ」等と力説しました。
しかし、「信心獲得」を強調した反動で表れたのが、「三業安心」です。
「三業安心」とは、「身口意の三業で、阿弥陀仏にお願いせねば助からぬ」「三業がこうなったのが獲信だ」と主張する信仰を言います。
この邪義を、功存の後を継いだ七代目能化・智洞が、公然と唱えたのです。
智洞の邪説をきっかけに、真宗の道俗がこぞって「私はこのように弥陀にお願いした」「お前はどのように弥陀をたのんだか」と三業を詮索するようになり、各地が騒然となっていきました。
こうして、本願寺を揺るがす信仰の大争乱へと発展していったのです。
蔓延する「三業安心」の誤りを正そうと、各地から実力ある真宗学者が立ち上がりました。
その代表が広島の学僧・大瀛(だいえい)です。彼は、智洞らの説を弾劾した本を出版。これに智洞側からは、何の反論もなく、教義上、智洞側の敗北は明らかとなりました。だが智洞達は、大瀛ら反対派に、出版妨害や風説、政治的な謀略等で応酬し、次第に暴動等、流血の惨事に至ります。
事態を重く見た寺社奉行が仲介に入り、審議の末、智洞側の邪義が明らかとなりました。智洞をはじめ、取り巻く学僧達は、本山から一掃され、本願寺を二分した大法論はこうして決着したのです。
この「三業惑乱」以来、真宗の道俗は、肝要の「たのむ一念」を毛嫌いし、「信心獲得」をろくに説かなくなりました。
三業惑乱の反動で、「十劫安心」に逆戻り、以後、明治・大正・昭和と衰退の一途を辿ったのが浄土真宗の歴史と言えるでしょう。
AD