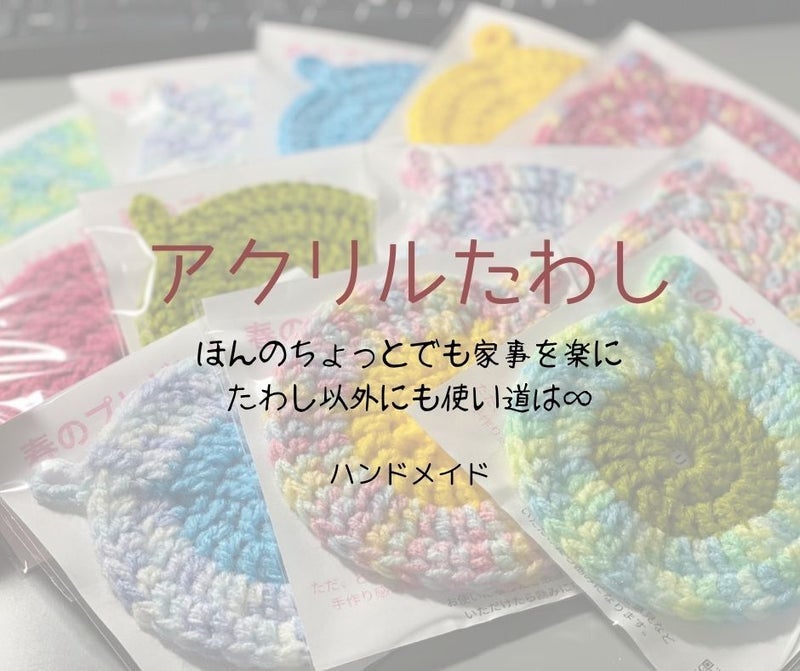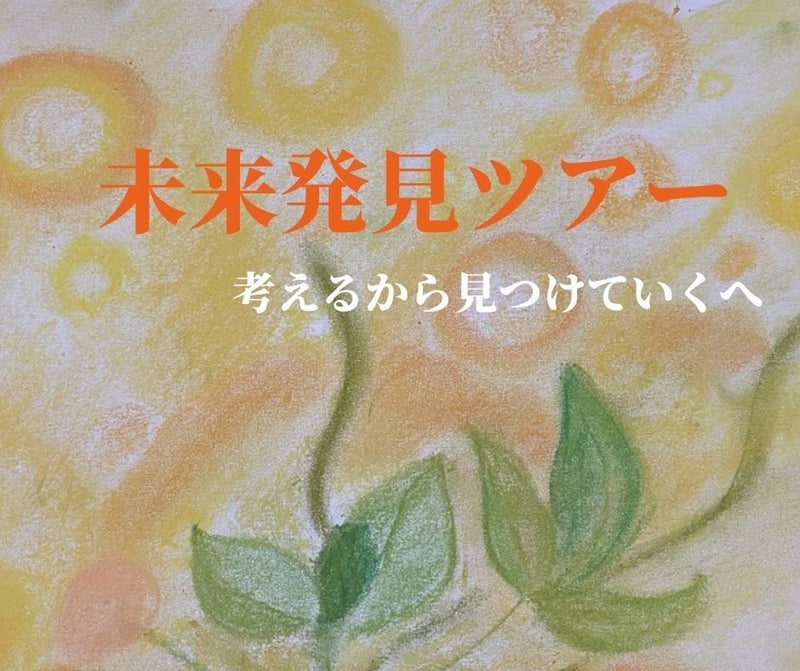みなさん、こんにちは。
お月さまが「射手座」にいる期間は4/1の4:50ころまでは相性がいい「ガレージ」「ベランダ」「バルコニー」「下駄箱」といった「エクステリアスペース」を整える。
いよいよ新学期や新年度が始まる直前!
気持ちも、生活環境なども変わると、いままであまり気になっていなかった「家」のことも気になってくるから不思議です![]()
暖かい季節にやるといいエクステリアを整えることは、フェンスのお掃除や外壁の塗装などがおすすめです
寒い季節に家周りのことをやるのは、寒いのでおすすめしません
春や秋は暑すぎず、寒すぎず、家の外側のお手入れをする季節にピッタリなのです![]()
思いがけないチャンスが舞い込んだり、行き詰っていたことに解決のヒントが見つかることもあるといわれる射手座期間
「ガレージ」「ベランダ」「バルコニー」などのエクステリアスペースは家と外界をつなぐ重要な場所
室内ではないので後回しになりがちな場所だけど、家の中だけでなく、外界にも働きかけることになるのでエクステリアを整えると得られる変化は大きいといわれているんですよ
月は2日ほどの周期で星座を移動します。
毎年、大掃除に時間がかかる、なかなか大掃除が終わらない
そのような人は、毎月めぐってくる月の移動に合わせてコツコツとお掃除を続けてみるといいですよ!
お掃除や部屋の片づけって何か理由があるとやる気が出ると思うんですよね。
だからゲーム感覚でお月さまの動きに合わせて家をパワースポットにしていくのも立派な理由の一つ![]()
2024年の射手座期間を最後にまとめてお伝えするので、今月以外にもできる期間を活用してくださいね
お月さまが「射手座」にいる期間は4/1の4:50ころまでは相性がいい「ガレージ」「ベランダ」「バルコニー」「下駄箱」といった「エクステリアスペース」を整える。
ガレージやベランダを物置代わりにしている人も多いですよね
家にモノをため込まないのは大切だけど、ガレージもベランダも家の中と同じと心得ておきましょう
ガレージやベランダを物置き代わりにする人は、「家の中じゃないからモノを置いておいても大丈夫、ちょっとくらい汚れていても大丈夫」と思っているのでは?
よく見かける物置き代わりになっているガレージやベランダには、ゴミや不要になった電気製品、枯れてしまった植物や鉢植え、プランターなどを見かけます
もし、ガレージやベランダにこのようなモノがあるならこの期間に掃除と処分をするのがおすすめ
ガレージやバルコニーが、可能性を広げ、新しい世界への扉を開けてくれる重要な場所で、住まいにおける外界との接点になる場所だから、運気アップや活躍の場を広げたいと思っている人はこの場所を整えてみて
置きっぱなしのモノを一掃して邪気のないクリアなスペースにしていく
ガレージ、ベランダ、バルコニーといったエクステリアは、外界とじぶん、じぶんの家をつなぐ重要な場所
玄関が運やチャンスの入り口で、エクステリアはエネルギーを世界に向けて発信していく“発信場所”です
不用品などを置きっぱなしにしていたら速やかに手放していきましょう
枯れた植物、鳥の糞、虫の死骸、枯れ葉などもきれいに掃除
全体をほうきで掃いた後は、手すりや給湯器などのガス器具、水栓なども水拭きをします
床の泥や土埃はデッキブラシでお掃除をしていきます
花粉が多い季節になってくるので、置きっぱなしのモノなどに花粉がたまってしまうこともきれいに掃除をすることでたまらなくなりますよ
花粉症でお掃除ができない人は、比較的花粉の少ない時間帯や、ご家族などにお願いしてみるのもいいですね
そして、下駄箱もきれいにしておきたい場所
靴は地面に直接触れるので外からの邪気が多くついています
重曹水や粗塩水で靴底を拭いておくといいですね
この期間に下駄箱をできない人は、4/7からの牡羊座期間に玄関と一緒にお掃除してもいいですよ
そして、お掃除ポイントは
ガレージ
ガレージを物置きにしない
ガレージを物置き代わりにするとエネルギーが混乱し、成功や発展の気運が頭打ちになってしまいます
ガレージに置くのは、車とアウトドア用品にとどめておきましょう
それ以外のものは倉庫などに収納するといいですよ
もし、倉庫や物置きがない場合は、しっかりとモノやペットのスペースとして区画をしたりして、用途を分けるといいですね
車や自転車もきれいに掃除
ガレージ自体をキレイにすると同時に車やバイク、自転車の汚れもしっかりと落とします
自転車置き場が別の場所なら、自転車置き場も併せてお掃除を
下駄箱
外からの邪気を吸収している靴
粗塩スプーン一杯と水を霧吹きの容器に溶かして、靴底に吹きかけて拭き掃除をします
このとき、ティッシュやウエットティッシュでもOK
靴箱の空気を入れ替える
靴をすべていったん出し、たまってる砂やほこりを取り除いたら、扉を開けて換気をして空気の入れ替えをしましょう
これからやってくる梅雨シーズンも考えて、湿気対策に備長炭シートなどを敷いておくのもおすすめ
ベランダ
家と外界との接点になるベランダやバルコニーは、掃き掃除をして、手すりや給湯器などのガス器具、室外機などについている土・砂ほこりを水拭きをしていきます
お月さまが「射手座」にいる期間は4/1の4:50ころまでは相性がいい「ガレージ」「ベランダ」「バルコニー」「下駄箱」といった「エクステリアスペース」を整える。
2024年 月が射手座にいる期間
![]()
3/2(土)~3/5(火)
![]() 4/26(金)~4/28(日)
4/26(金)~4/28(日)
![]() 5/23(木)~5/26(日)
5/23(木)~5/26(日)
![]() 6/20(木)~6/22(土)
6/20(木)~6/22(土)
![]() 7/17(水)~7/19(金)
7/17(水)~7/19(金)
![]() 8/13(火)~8/16(金)
8/13(火)~8/16(金)
![]() 9/10(火)~9/12(水)
9/10(火)~9/12(水)
![]() 10/7(月)~10/9(水)
10/7(月)~10/9(水)
![]() 11/3(日)~11/6(水)と11/30(土)~12/3(火)
11/3(日)~11/6(水)と11/30(土)~12/3(火)
![]() 12/28(土)~12/30(月)
12/28(土)~12/30(月)
エクステリア、家の外壁塗装などの家周りの相談やお見積り依頼、現地確認などのお問い合わせもお受けしています
玄関ドアの交換など「住宅省エネキャンペーン」の補助金を活用して整えていこうかなと思っている方は、ご相談お待ちしております。
家のことで気になる方は「開運!間取り鑑定」もお受けしています。
間取り鑑定のご感想
【居心地の良さ】
物を片付ける時
収納する時
居心地重視
で、心に正直だと
家も喜ぶ
と教えてもらった
住まいは、その家に住む人が元気で健康でいることで
家のパワーもアップすると、わたしは考えています。
そして、その家で心地よく、楽しく、嬉しく過ごせる空間であることも大切だなと考えています![]()
お知らせ