最高裁で元都立教諭の「損害賠償訴訟」に対する上告が破却され、またこの
「国歌・国旗」に対する考え方も示されて・・・。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことを理由に、退職後に嘱託教員として雇用
しなかったのは違法として、東京都立高の元教諭が都に損害賠償などを求めた訴
訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、起立を命じ
た校長の職務命令を合憲と判断し、元教諭側の上告を棄却した。都に賠償を命じ
た1審判決を取り消し、元教諭側の逆転敗訴となった2審判決が確定した。
最高裁は平成19年2月、国歌伴奏を命じた職務命令を合憲と初判断したが、国
歌斉唱の起立命令に対する合憲判断は初めて。
1、2審判決などによると、元教諭は16年3月の都立高の卒業式で起立せず、
東京都教育委員会から戒告処分を受けた。19年3月の退職前に再雇用を求めた
が、不合格とされた。
同小法廷は判決理由で、卒業式などでの国歌斉唱の起立は「慣例上の儀礼的な所
作」と定義。起立を命じた職務命令について「個人の歴史観や世界観を否定しな
い。特定の思想の強制や禁止、告白の強要ともいえず、思想、良心を直ちに制約
するものとは認められない」と指摘した。
その上で、「『日の丸』や『君が代』が戦前の軍国主義との関係で一定の役割を
果たしたとする教育上の信念を持つ者にとっては、思想、良心の自由が間接的に
制約される面はあるが、教育上の行事にふさわしい秩序を確保するためには合理
的だ」との判断を示した。
判決は4人の裁判官の全員一致の意見で、うち3人が補足意見を付けた。竹内行
夫裁判官は「他国の国旗、国歌に対して敬意をもって接するという国際常識を身
に付けるためにも、まず自分の国の国旗、国歌に対する敬意が必要」とした。
(産経新聞)(抜粋)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110530/trl11053017440005-n1.htm

卒業式で君が代斉唱時の起立を命じた校長の職務命令が「思想・良心の自由」
を保障した憲法19条に違反しないかが争点となった訴訟の上告審判決で、
最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、「憲法に違反しない」とする
初めての判断を示した。
訴えていたのは、東京都立高校の元教諭の男性(64)。2004年3月の卒
業式で「国歌斉唱の際は、国旗の日の丸に向かって起立するように」と校長か
ら命じられたが、起立しなかったことから戒告処分を受けた。
07年3月に定年退職する前に「嘱託員」としての再雇用を申請したが、不
採用とされたため、都に損害賠償などを求めて提訴した。
一審・東京地裁判決(09年1月)は、職務命令は合憲としながら、04年
3月以降は職務命令に従っていた点などを考慮して「裁量権の逸脱」と判断
し、約210万円の支払いを都に命じた。一方、二審・東京高裁判決(09
年10月)は、「都には広範な裁量権がある」として元教諭が逆転敗訴した
ため、元教諭が上告していた。
http://www.asahi.com/national/update/0530/TKY201105300242.html

東京都教育委員会の「日の丸・君が代」強制に従わなかったことを理由に懲
戒処分された都立学校の教職員66人の処分取り消しを求めた訴訟の口頭弁
論が3日、
東京地裁(青野洋士裁判長)であり、教師、原告側弁護士らが意見陳述をし
て結審しました。
原告の都立高校教諭の女性は、都教委の「日の丸・君が代」強制の通達が出
る以前には、生徒に対して「国歌に対してはいろいろな考えがあるので、自
分の考えにしたがって行動してください」と説明していたのに、それができ
なくなったと陳述。処分を受けたことが影響して、希望しても4年間もクラ
ス担任になれなかったこと、今年度、3年生の担任になれたが、「3月の卒
業式で起立しないと停職になるのではないかと不安でたまらない」と語りま
した。
元都立高校教諭の男性は、戦争で傷ついた人たちの心に塩を塗るように思え
て「君が代」を歌わないできたが、職務命令で「君が代」を歌えと命じられ
たときは憤りでめまいを起こすほど血圧があがり通院が必要になったと陳述。
2度目の不起立のとき生徒が「筋を通したね」と声をかけてきたことなどを
紹介し、「都教委の通達を違憲・違法だと認め、処分を取り消す判決を出し
てほしい」と訴えました。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik10/2011-02-04/2011020407_01_1.html

文部科学省のまとめによると、日の丸や君が代に関する職務命令違反で懲戒処分
を受けた教職員数は、2010年3月までの10年間で計693人。
うち国歌斉唱などを義務付ける通達を出した東京都が431人と突出して多い。
最近は減少傾向にあるが、大阪府で国歌斉唱を義務付ける条例案が議会に提出さ
れており、橋下徹知事は懲戒免職を含めた厳しい処分に言及している。
学校行事での国旗掲揚や国歌斉唱について、文部省(当時)は1989年、それ
まで「望ましい」としていた学習指導要領の表現を、「指導する」と事実上義務
付ける内容に改定。国旗・国歌法が施行された99年には、全国の教育委員会に
指導徹底を図るよう改めて通知した。
この結果、入学式や卒業式での日の丸掲揚・君が代斉唱の割合は上昇。小中学校
に比べて低かった高校卒業式での君が代斉唱率も、指導要領改定前の約5割から、
01年にはほぼ100%となった。
命令違反で処分される教職員は、国旗・国歌法施行の翌年度に急増したが、訓告
などの軽い処分が大半だった。
しかし、都教委が通達を出した03年度には、より厳しい戒告や減給などの懲戒
処分が増え、処分者数も都が約9割を占めた。
時事通信
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011053000518

サッカー日本代表イレブンが試合前、胸に手を当てて君が代を歌う。W杯などで
はおなじみの光景だが、中には歌わない選手もいる。歌う歌わないは本人の自由
意思。決して強制されるものではない
▼しかし、大阪府の教職員は起立・斉唱を強いられることになりそうだ。橋下徹
府知事を代表とする「大阪維新の会」の議員らが、起立・斉唱を義務付ける条例
案を提出した
▼なぜ今なのかという疑問がつきまとう。同会は先月、府や市の議員選で大躍進
したばかり。選挙前にはほとんど争点にもならず、市民を交えた議論がどれほど
尽くされたのか。多数を盾に、力ずくの姿勢が見え見えだ
▼条例案は、国や郷土を愛する心を育てることが目的の一つ。しかし、郷土愛な
どは自然発生的な気持ちで敬意を表すことが本来の姿であり、強制するものでは
ない
▼ましてや君が代の場合、戦争を想起させる、として拒否する人は少なくない。
だからと言って、「歌わない=愛国心がない」とは言えまい。個人の思想信条を
法律でゆがめることは許されない。
むしろ、さまざまな意見があることを教育現場で教えることが大切だ
▼押し付けられれば、息苦しい。規律の厳格化だけでは学校の雰囲気は張り詰め
る。もの言わず縮こまる先生を、子どもたちはどう思うか。不安だけが募る。
http://www.okinawatimes.co.jp/article/2011-05-30_18507/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
その昔、三無主義と揶揄される若者達が今はそれなりの年齢を重ね、中年となっ
て・・・、それでも「昔取った杵柄」にすがるかのように、「無気力・無関心・
無責任」を合言葉にして、なんにでも反対を貫く、だけに職場としての「マスコ
ミ」も、その主義には合致していて・・・。
何より公務員教師には、定年後には共済年金とかの「恵まれた老後」があるだけ
に、思想・信条もそのバックボーンが後押しをしてくれるとなれば、怖いものな
しで、そりゃ「自分の意思を貫き通す」ことも出来よう・・・。
そして以下の歌みたいに、思考を停止させ化石化すれば、今も戦いの中である。
「教訓」加川良
この上から目線の「歌詞」に違和感があると、なんとも受け入れがたいが、公務
員教師なら、これを聞けば「勘違い」はありそうで・・・。
歌詞の中の差別的主張は、今となっては批判の対象になりそうで云々だが・・・。
まぁ、どちらかといえば女性の境遇を歌うものの方が、この七十年代は・・・。
「乙女のロマン」 あがた森魚
とはいっも、この大正ロマンのテイストは、好き嫌いがあるようだが・・・。
で、この「反戦」をうたいそれなりの聞き手も頷けるが、ただその思想とか
信条とかとかと、「女の腐ったやつ」といみじくも「女性」を蔑むかの語句
を使ってしまうと、さて、では男としての「下半身」も、その思想・信条に
堅固かといえば、「ハニートラップ」という語句も存在するくらいに弱いも
ので、その立場になれば「思想・信条」も揺らいでしまう・・・。
と、結局不祥事を起こして、その立派過ぎる主張と下半身の「不貞」は相容
れない・・・。
で、そんな思いを記事の裏に感じれば、タイミング良く録画していた「午後の
ロードショー」で、「新聞記者」が無実の罪で投獄され、釈放されれば「女の
魅力」に負けて、犯罪の片棒を担いでしまうという映画があった。
それが「魔性の肉体」である。

「魔性の肉体」 〇四年未公開作
無実の罪で投獄された元新聞記者が、その罪も晴れて釈放されたところから
物語は始まるのだが、この主人公の設定が「新聞記者」というには無理があ
りありな感じで、出だしから「色物映画」の臭いが立ち込め、妖しい雰囲気
をかもす女が登場するに及んで、「ああ、これで犯罪に加担する」とベタな
展開に入り込んでいく・・・。
邦題もそんな内容をより刺激的にしたのだろうが、どうしても二番煎じな感
じは否めず、どんでん返しの展開も、あれあれ「脚本も二転三転させてつじ
つまが無理やり」な展開に・・・。
ただ、こういったものなら「なぞが謎を呼ぶ」展開に一応見えるから飽きは
しないとは思うが・・・、流石に公開されるだけの映画には魅力はない。
これだったら「魔性の」とされるエリザベス・シューの場面を持つと増やせ
ばよかったろうに・・・。
第一、ワイロを嫌った清廉潔白な新聞記者が、簡単に「金を盗み」体の誘惑
に勝てないで、他愛なく「犯罪に手を染める」のだから、昼メロの域を出て
いない・・・。
ただ「寒流」ドラマ好きなら、ほころびも何のそので「それなりの評価」が
なされそうだが・・・。
教訓/加川良
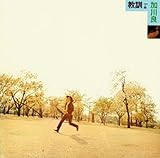
¥2,800
Amazon.co.jp
乙女の儚夢/あがた森魚

¥1,800
Amazon.co.jp といったところで、またのお越しを・・・。