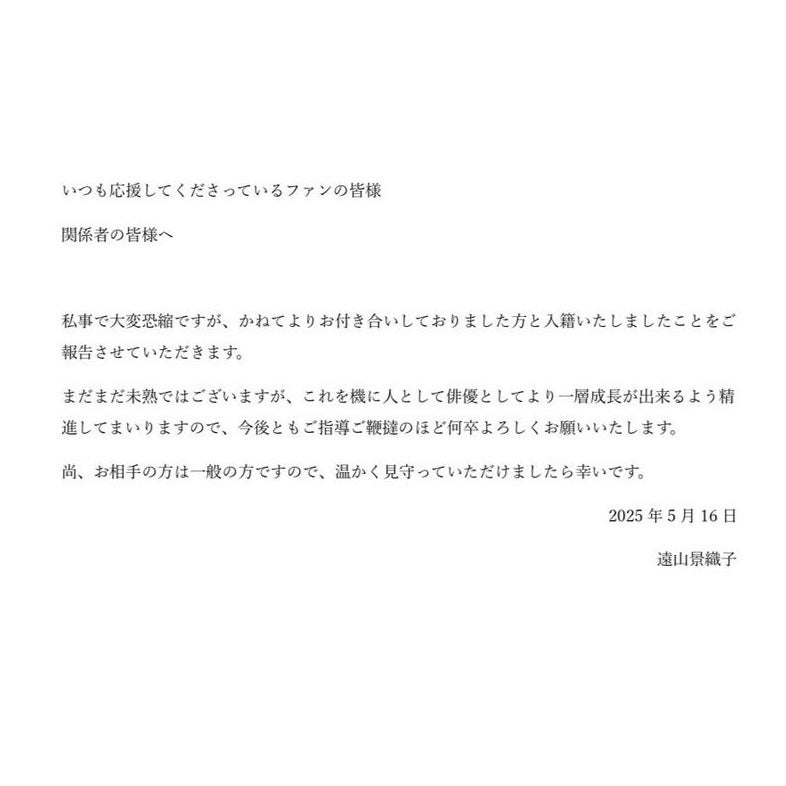前記事、‘近代化の先駆け、富岡製糸場’の続きです。
富岡製糸場のガイドツアーの前半が明治5(1872)年の建設当時、世界最大規模と謳われた近代的な製糸工場としての姿だとすると、後半は当時の工女たちの生活を垣間見ながら思いを馳せる時間となりました。
製糸場の要の『繰糸所(そうしじょ)』を一歩出ると、そこはまるで学校の渡り廊下のような作りになっていて、聞くとここには学校があったというのです。製糸場に学校![]() とびっくりですが、ここでは工女たちを働かせるだけではなく、読み書き、算術、裁縫、習字など幅広い教育を施していたそうなのです。明治時代にすでに今でいう企業内研修が行われていたのですね
とびっくりですが、ここでは工女たちを働かせるだけではなく、読み書き、算術、裁縫、習字など幅広い教育を施していたそうなのです。明治時代にすでに今でいう企業内研修が行われていたのですね![]()
まるでむかしの小学校の渡り廊下のような趣です。
さらに驚くべきことは、敷地内に工女たちのための寄宿舎や入院病棟まで備えた診療所が完備されており、工女たちはお給金をいただいた上に、学校の授業料、寄宿舎の費用、食費、医療費はすべて無料、制服は貸与という好待遇だったそうです。さらにさらに驚くべきことに、一日の就業時間は7時間30分と定められ、一週間のうち日曜日を休みとする『七曜制』の採用、お盆休みと年末年始の休暇も与えられていたそうで、これらは現代に置きかえても十分に通用する労働条件といえるでしょう。診療所や入院病棟、寄宿舎などの建物はすべて外から見学するだけですが、どの建物も保存状態がよく往時のままの姿を見せてくれていて、その空間に佇んでいると、袴姿の若い工女たちのさんざめきが聞こえてくるような気さえします。
工女たちのための診療所。『片倉診療所』と表示されているのは、昭和13(1938)年から操業停止の昭和62(1987)年までの経営者が片倉製糸紡績株式会社だったからのようです。
富岡製糸場は近代的な工場だっただけでなく、理想的な職場環境でもあったわけですが、創業前の工女募集時は、フランス人が飲むワイン![]() を見て「富岡に行くと生き血を吸われる」という流言が飛び交い、なかなか工女が集まらなかったそうです。富岡製糸場設立の目的のひとつが工女に最新の繰糸技術を習得させたのち、彼女たちが指導者となって全国にその技術を伝播してゆくことだったため、全国各地から採用することとし、旧士族の娘など優秀な女子が集められ、その数500名を超えていたそうです。工女たちは技術の習熟度によって『等外上等工女』から『七等工女』まで8ランクに分けられ、完全能力給だったそうですから、キャリアウーマンとして憧れの的ではなかっただろうかと想像します。
を見て「富岡に行くと生き血を吸われる」という流言が飛び交い、なかなか工女が集まらなかったそうです。富岡製糸場設立の目的のひとつが工女に最新の繰糸技術を習得させたのち、彼女たちが指導者となって全国にその技術を伝播してゆくことだったため、全国各地から採用することとし、旧士族の娘など優秀な女子が集められ、その数500名を超えていたそうです。工女たちは技術の習熟度によって『等外上等工女』から『七等工女』まで8ランクに分けられ、完全能力給だったそうですから、キャリアウーマンとして憧れの的ではなかっただろうかと想像します。
広い敷地内にゆったりとスペースをとって工女たちの寄宿舎が建てられています。学生数500名超えの女子高![]() と思えば、その華やかさ、賑やかさは想像できようというものですね
と思えば、その華やかさ、賑やかさは想像できようというものですね![]()
ここまでくると、わたしたちの富岡製糸場=過酷な労働=可哀そう、のイメージは完全に誤りであったことが分かります。よくよく考えると『女工哀史』の舞台は製糸場ではなく紡績工場でしたし、映画化もされた『あゝ野麦峠』の野麦峠は岐阜県高山市と長野県松本市の県境に位置し、岐阜県の飛騨地方から野麦峠を越えて長野県岡谷市の製糸工場へ出稼ぎに行く話、群馬県富岡市の富岡製糸場とはまったく違うことに気づくのですが、若い女性の出稼ぎ労働、同じ繊維を扱う仕事というので混同してしまったのでしょうか![]() 。
。
期間限定で公開されている『東置繭所(ひがしおきまゆじょ)』の二階部分。実際に中に入ってみると、長さ104.4m、幅12.3mの巨大な空間を体感することができます。
富岡製糸場は明治5(1872)年に官営工場として操業を開始し、明治26(1893)年以降は三井家ほか民間企業に払い下げや吸収合併されることになりますが、昭和62(1987)年の操業停止まで115年間にわたり生糸を生産し続けたそうです。富岡製糸場ができる前は『座繰り(ざぐり)』という人の手に頼る製糸方法だったため大量生産ができないうえに、糸の太さにばらつきがあるなど問題が多く、輸出してもクレームをつけられるほどだったものが、富岡製糸場の優秀な工女たちの紡ぎ出す生糸に代わってからは『トミオカシルク』は欧米でも上質の生糸の代名詞となり、明治42(1909)年には日本の生糸輸出量が世界の市場の80%を占めるまでに成長したのですから、彼女たちの功績は計り知れないといっても過言ではないでしょう。
手前に見える白い木造の建物は『高圧変電所』です。『東置繭所』の長さも伝わるでしょうか。
解説員さんとともに回るとこうしたお話しを数々聞くことができ、ただ建物を見学するだけでは分からないものを感じ取れるような気がします。ガイドツアーのあとはまた夫とふたり、ツアーでは行かなかった部分や資料等の展示スペースをゆっくりと回ったのですが、途中途中におられる職員さんや警備員さんのおひとりに至るまで、何を尋ねても丁寧に答えてくださり、案内してくださるのにはほんとうに感心しました。富岡製糸場が世界遺産に登録されたことに誇りを持ち、地元の遺産を大切に伝えてゆこうとする思いが感じられて、とても満ち足りた思いで富岡製糸場をあとにしました。
オマケ~![]()
行きがけの車のなかで夫が「久しぶりに峠の釜めし、食べたいなぁ~。」と言うのですが、横川まで行くのは少し遠いねと諦めていたところ、見学を終えて正門を出るとすぐ左手に『おぎのや』の幟が![]()
![]()
![]() ここで作っているのではなく、横川の本店から文字どおり峠を越えて運んできてくださるとのことで予約制でした。わたしたちがいただいた午後1時半の便がランチの最終なのか、そのあとすぐに幟がおろされました。名物峠の釜めしに舞茸の天麩羅と刺身蒟蒻がついた『妙義』(1,630円)。右上のかわいい器に入った香の物セットが釜めしのいいアクセントになっていました。
ここで作っているのではなく、横川の本店から文字どおり峠を越えて運んできてくださるとのことで予約制でした。わたしたちがいただいた午後1時半の便がランチの最終なのか、そのあとすぐに幟がおろされました。名物峠の釜めしに舞茸の天麩羅と刺身蒟蒻がついた『妙義』(1,630円)。右上のかわいい器に入った香の物セットが釜めしのいいアクセントになっていました。
![]()
![]()
![]() yantaro
yantaro ![]()
![]()
![]()