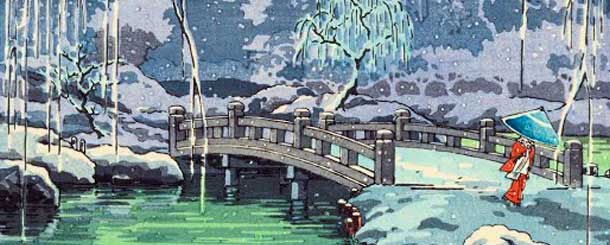ここのところ比較的暖かな陽気に恵まれているDaimal地方。
朝は冷たく寒いのですが、降霜や氷結ほどにはなりません。 札幌から帰ってきた孫と娘が到着し、微妙に忙しくなってしまい、公園の自転車散歩も久しぶり。 買い出し三家族分があるので、す~っと走るだけのお散歩です。(「噴水広場」は案内板で、実際の噴水広場はもう少し先にあります)
陽が射して日向ぼっこには最適(若干風がありますが)。
池の氷も溶けて水鳥がそそくさと「漁」に出て行きます。
訪れたグリーンセンターは沢山のボランティアさんが寒中の植え替えなどで大忙しの様子。 邪魔にならないように地味な場所をお散歩。 フェンスに巻き付いたツルウメモドキの木に誘われました。
ツルウメモドキの開いた実の残り殻
殻すら残っていないのは鳥が食べてしまった?
なぜか枯れ枝に惹かれてしまったDaimalで御座います。
枯れたツルウメモドキと云えば、蝋梅の葉は落ちたのだろうか。
一月上旬では黄葉した葉を残したまま咲き始めた圃場の蝋梅も、すっかり葉を落としていました。
黄色い花は、やはり落葉した枝に付いていた方がコントラストが効いて綺麗です。
花密度が高い方角から撮影すると、黄色いつぶつぶに埋め尽くされているような感覚になります。
少し引いて撮っても黄色いつぶつぶだらけ
うす暗い林の中でスポットライトを浴びるように浮き上がっていた、たぶんアオキ(青木)の雌木。 もう赤く成熟していてもよい頃だと思うのですが、青々とした実が付いています。
鮮やかな緑色なのに、なぜ青木? 緑の葉なのになぜ、青々と表記するの?
鎌倉時代前は色の表記が4色で赤青白黒だったそうで、緑色は青色の範疇だったとか。 その後、色を表す言葉が増えて和名では400を超える表現になったそうです(日本伝統色は465種ある)。 和名の色は、自然の動植物や物そのものから名付けられているものが殆どです。
鶯・浅葱・黄土・藍・・・・
因みに信号器の赤青黄色は、初めて出来た信号器の新聞記事が青と表記されていたことに由来するようです。 法令の方も「青」と書き直されたとか。
公園画伯の後ろ姿を眺めて、そろそろ帰路に
今日のお散歩御飯は、胡麻味噌ラーメンと迷った挙げ句、柚子塩ラーメン&餃子。
少々厚着してきてしまったので、久々に汗をかいてしまうのでありました。
1/22撮影@都立水元公園
娘が孫と北海道から戻ってきました。
引っ越しやらダンナの地方宿泊研修やらで長逗留になりそうです。
若干?気を遣ってか、オリジナル缶入り「白い恋人」を土産に持参してきました。
百均の細いクーピーペンシルでは心許ないので太いクーピーを買って一緒にお絵描き。 Daimal画伯が手をだそうものなら「じぃじぃ ない!」と叱られるのでありました。
可成りお疲れモードのじぃじぃは、孫の昼寝の隙に、北海道銘菓だけでなく九州銘菓である「あいすまんじゅう(いちご)」も頂いて癒やされるのでありましたとさ。 (写真が少し黄昏れているでしょ)
SC三階のおもちゃ売り場がみごとに改修されており、トミカ・プラレールを始めとする魅惑の大フロアと化しています。 駄々をこねるでもなくじっとみつめている姿を見てしまうと、緩んでしまった財布の紐がなかなか締まりません。。。
冬のお出掛け散歩の時間は孫に取られてしまい、ブログの更新も停滞することでしょう。