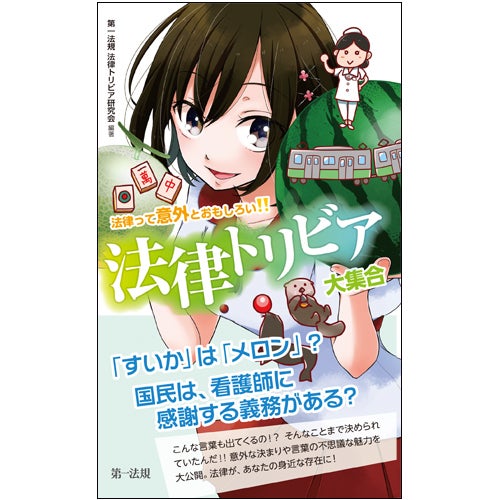こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です![]()
昔、中学の同級生に、「将来、近鉄の運転士になりたい!」と言っていた友人がいました。
休み時間や放課後、近鉄電車の運転を詳細に再現してくれるのですが、
その時の彼は、うっとりした表情でハンドルさばきを披露していました。
電車の運転というものは、人を惹きつけてやまない魅力があるようです。
さて、10月10日の記事「電車を運転するには免許が必要?」で、
電車の運転士さん(動力車操縦者)にも運転免許が必要であること、
その試験では、二つの法令に関する知識が問われることをご紹介しました。
そして10月13日の記事「電車の運転士さんが守らなければならないこと」では、
そのうちの一つ、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」について見てみました。
今回は、試験に出てくるもう一つの法令である
「運転の安全の確保に関する省令」を見ていきたいと思います。
![]() 法鉄記事の一覧はこちら ⇒ 「法鉄」の世界 ~ 記事まとめ
法鉄記事の一覧はこちら ⇒ 「法鉄」の世界 ~ 記事まとめ ![]()
◯おおもとは「鉄道営業法」第1条
まずは、条文の前に書かれている制定文を見てみましょう。
運転の安全の確保に関する省令(昭和26年運輸省令第55号)
〔制定文〕
前回の「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」の制定文と同じく、
この省令も、「鉄道営業法」の第1条に基づいて定められたものです。
◯常に心にとどめるべき、安全に関する決まり
さて本題に戻って、第1条にはこの省令の目的が書かれています。
運転の安全の確保に関する省令
第1条
この条文の中に「服よう」という言葉が出てきますが、
このように、
それでは、具体的に、どのようなことを心にとどめようといっているのか、見ていきましょう。
◯綱領
第2条には、「服よう」すべき具体的な規範として、
まず「綱領」から見てみましょう。
運転の安全の確保に関する省令
(規範)
第2条〔抜粋〕
従事員が服ようすべき運転の安全に関する規範は、左の通りとする。
一 綱 領
(一) 安全の確保は、輸送の生命である。
(二) 規程の遵守は、安全の基礎である。
(三) 執務の厳正は、安全の要件である。
・・・
このように、安全を守ることがいかに大事なことであるか、を、端的な言葉で表しています。
◯一般準則
続いて、「一般準則」が書かれています。
運転の安全の確保に関する省令
(規範)
第2条〔抜粋〕
従事員が服ようすべき運転の安全に関する規範は、左の通りとする。
・・・
二 一般準則
(一) 規程の携帯
従事員は、常に運転取扱に関する規程を携帯しなければならない。
(二) 規定の理解
従事員は、運転取扱に関する規定をよく理解していなければならない。
(三) 規定の遵守
従事員は、運転取扱に関する規定を忠実且つ正確に守らなければならない。
(四) 作業の確実
(六) 確認の励行
従事員は、作業にあたり必要な確認を励行し、おく測による作業をしてはならない。
(七) 運転状況の熟知
(八) 時計の整正
従事員は、職務上使用する時計を常に整正しておかなければならない。
(九) 事故の防止
(十) 事故の処置
この中では、「(八)時計の整正」という項目が、いかにも鉄道関係という気がします。
◯どんな状況下で書かれたのか
さて、この省令が公布されたのは、1951(昭和26)年7月2日でした。
その約2か月前の4月24日に、国鉄桜木町駅構内で、
架線工事のミスによる列車火災のために乗客106人が亡くなるという事故があり、
当時の国鉄総裁の辞任にまで至ったという出来事がありました。
この事故については、当時の国会でもたびたび取り上げられ、
議事録を読むと、国鉄が電車を導入して以来の大事故であり、
電車に乗るのが不安になっている人もいるけれども、やはりみな電車に乗らざるを得ず、
車掌さんが乗客を押し込まなければならないほど混雑している…
ということが書かれています。
そして、桜木町事故をきっかけに、
車両の構造が改善されたり、ブザーがつけられたり、パンタグラフが改善されたり
という方策が講じられました。
この省令は、そうした状況の中で策定されたもので、
この第2条「規範」の文章を見ていると、
安全確保に対する強い決意が表れているように思います。
(この記事は、2017年10月11日時点の情報に基づいています)
![]() 法鉄記事の一覧はこちら ⇒ 「法鉄」の世界 ~ 記事まとめ
法鉄記事の一覧はこちら ⇒ 「法鉄」の世界 ~ 記事まとめ ![]()
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
いかがでしたでしょうか。
ブログ本『法律って意外とおもしろい 法律トリビア大集合』もぜひご覧ください!
 |
注解 鉄道六法〔平成29年版〕
5,616円 Amazon |
是非、次回もお楽しみに![]()
![]()
by 第一法規 法律トリビア編集担当