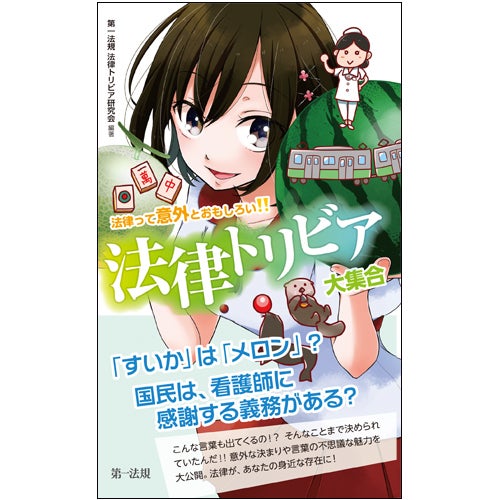こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です![]()
法律という切り口から鉄道の世界を探る「法鉄」シリーズ。
前回は、電車の運転士さんにも運転免許が必要か、を探ってみました。
今回は、はれて電車の運転士になった人が、
どんなことを守らなければならないか、見ていきたいと思います。
![]() 法鉄記事の一覧はこちら ⇒ 「法鉄」の世界 ~ 記事まとめ
法鉄記事の一覧はこちら ⇒ 「法鉄」の世界 ~ 記事まとめ ![]()
◯おおもとは「鉄道営業法」
鉄道営業に関する決まりの書かれている「鉄道営業法」を見ると、
電車の運転に関する詳しい規定は国土交通省令に定められていることが分かります。
鉄道営業法(明治33年法律第65号)
第1条
鉄道ノ建設、車輛器具ノ構造及運転ハ国土交通省令ヲ以テ定ムル規程ニ依ルヘシ
この規定に基づいて、
「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」という省令が定められています。
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号)
〔制定文〕
この省令には、
・駅や線路など、鉄道の設備に関する決まり
・鉄道係員が守らなければならないこと
・鉄道の車両が満たさなければならない基準
といった、鉄道に関するあらゆる分野にわたり、具体的な決まりが書かれていて、
初めて条文を見たとき、「宝の山だ!」と思いました。
というわけで、
この中に、電車の運転士さんが守らなければならないルールも書かれています。
なお、前回の記事でご紹介しましたが、この省令は、電車の運転免許試験に出てくる科目です。
ですので、自分が電車を運転する姿を想像しながら、見ていきたいと思います!
◯列車の間隔を空けましょう
第101条第1項には、列車の運転にあたっては、
他の列車との間隔について、安全が確保されるようにしなければならない…と定められ、
続いて、その具体的な手段が三つ挙げられています。
① 「閉そく」による方法・・・列車の走る区間を区切って、一つの区間には同時に
一つの列車しか入らないようにするという方法です。
② 列車間の間隔を確保する装置を使う方法
③ 運転士が、前方の見通しなど、安全運転に必要な条件を考慮して運転する方法
また、第2項では、例外として、
救援列車を運転する場合などは、上記とは別の安全確保措置を講じた上で、
列車を運転できるとされています。
鉄道に関する技術上の基準を定める省令
(列車間の安全確保)
第101条第1項
一 閉そくによる方法
二 列車間の間隔を確保する装置による方法
◯電車は、一番前で運転しましょう
第102条には、
鉄道に関する技術上の基準を定める省令
(列車の操縦位置)
第102条
この規定には、上記のようにただし書きがあり、
一番前じゃないところで運転する…このただし書きは、どんな場合に使われるのでしょうか?
調べたところ、
◯安全な速度で運転しましょう
列車は、線路・電線の状態、車両の性能、運転方法、信号などに応じて、
鉄道に関する技術上の基準を定める省令
(列車の運転速度)
第103条
ちなみに、この規定の中に「線路及び電車線路」と書いてあり、
一瞬「?」と思ってしまいましたが、
「電車線路」とは、変電所から送り出された電気を車両に伝えるために、
沿線に設けられた電線路のことだそうです。
◯後戻りをしてはいけません
列車は、「退行運転」(後戻り)をしてはいけないとされています。
ただし、後続列車を進入させないようにしているなどの場合は、
例外的に退行運転ができます。
鉄道に関する技術上の基準を定める省令
(列車の退行運転)
第104条
◯酒気帯び運転はいけません
鉄道にも、自動車と同様に、酒気帯び運転を禁止する規定があります。
(動力車を操縦する係員の乗務等)
第11条第3項
運転士の皆様、これからも安全運転をよろしくお願いいたします!
(※この記事は、2017年10月1日時点の法令情報に基づいています。)
![]() 法鉄記事の一覧はこちら ⇒ 「法鉄」の世界 ~ 記事まとめ
法鉄記事の一覧はこちら ⇒ 「法鉄」の世界 ~ 記事まとめ ![]()
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
いかがでしたでしょうか。
ブログ本『法律って意外とおもしろい 法律トリビア大集合』もぜひご覧ください!
 |
注解 鉄道六法〔平成29年版〕
5,616円 Amazon |
是非、次回もお楽しみに![]()
![]()
by 第一法規 法律トリビア編集担当