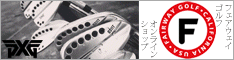さて、今回は、石川遼プロの今シーズン好調な成績のポイントのお話です。
ということで、、、。
昨シーズン迄と違い今シーズンの石川遼プロですが、すでに、日本プロとセガサミーカップとすでに2勝して、賞金ランキングトップを走っています。
その好調さを数字で昨シーズンと比較すると、
◼️今シーズン
パーオン率 66.47% 31位
平均パット 1.7207 3位
フェアウェイキープ率 59.54% 28位
トライビングディスタンス 309.54y 5位
トータルドライビング 3位
◼️昨シーズン
パーオン率 65.04% 27位
平均パット 1.7400 2位
フェアウェイキープ率 44.50% 96位
ドライビングディスタンス 289.35y 22位
トータルドライビング 76位
です。
このようにみれば、パーオン率や平均パットはほとんど変わりません。バッティングの上手さは変わらずいい数字になっています。
それで一番の違いは、ドライバーの距離と正確性を表すトータルドライビングです。
これが、76位から3位に大きくジャンプアップしています。
そして、それはフェアウェイキープ率も大きく伸ばして、さらにドライバーの飛距離が別人のように伸びています。
289yから309yと20ヤード伸びているわけです。
実際、先週のフジサンケイでも最終日の18番で339ヤード飛ばして、そのあとで回った飛ばし屋のチャンキムよりも飛んでいました。
つまり、グリーンを狙うショットやバッティングは変わらず、ドライバーが飛んで曲がらなくなったので、スコアが良くなっていると言えます。
さて、それでドライバーは、昨年と何が変わったかというと、
◼️今シーズン
1w
キャロウェイ エピックフラッシュ サブゼロ ◆◆◆(トリプルダイヤモンド)
◆◆◆(トリプルダイヤモンド)
◼️昨シーズン
実は石川遼プロは、大型ヘッドで重心距離の長いドライバーでかなり苦しんでいました。
そして、昨シーズン終盤のダンロップフェニックスから、片山プロからアドバイスを貰って、XR16のドライバーのネックに、鉛をぐるぐる巻きにして、重心距離を短くするような工夫をしていました。
この工夫は、ドライバーの安定には効果があったようです。
そして、キャロウェイが新製品のドライバー エピックフラッシュシリーズを出して、石川プロも新製品のドライバーに移行していました。
エピックフラッシュサブゼロは、スピン量が少なめなので、ヘッドスピードが速い石川プロの飛距離アップにはかなり貢献していると思います。
しかし、このドライバーには、以前試して良かった鉛がネックにはありませんでした。
僕は石川プロとラウンドする機会があり、そのときに、この辺りを聞いたら、なるほどと思われる工夫をこのドライバーにもしていました。
さすがにキャロウェイのスタッフは、いい仕事していると思いました。
どのような工夫をしているかは、石川プロも、キャロウェイのスタッフもメディアに公開していませんので、(記者が聞いてないだけかもしれません。または、企業秘密化かも。)ここでは書けませんが、大型ヘッドでも小さいヘッドに感じるような工夫が見えないところでされています。
実際石川プロは、ドライバーは、大丈夫というふうに一緒にラウンドした時に聞いていましたが、それが数字に表れ、優勝という結果にも繋がりましたね。
この調子だと、また、近いうちにアメリカツアーに戻れるような気もします。
これからが楽しみです。