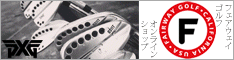ウェッジの選択と打ち方のマッチングとは?!
さて、今回は、 ウェッジの選択と打ち方のマッチング のお話です。
ということで、、、
皆さん、ウェッジは、どういうタイプを使ってますか?
1:アイアンと同じ
2:ウェッジだけ別モデル?
全体の中でいうと、アイアンと同じウェッジという人も結構います。
代表的なブランドは、ゼクシオ です。
やはり、アイアンも売れているので、アイアンに合わせてウェッジもということですね。
このアイアンセットと同じモデルのいいところは、同じ流れのシャフトや顔で、違和感なく使えるところです。
例えば、アイアンがグースで、ウェッジがストレートネックみたいな形だと、ウェッジだけ別モデルという意識が強く働きます。
販売する側からいっても、同じタイプだと、薦めて間違いないというところもポイント高いです。
それで、いや、ウェッジは、こだわりが、、、、ということで、ウェッジだけ別モデルの人も結構います。
プロゴルファーは、ほとんどこちらですね。
また、タイトリスト ボーケイなど単品ウェッジも結構バリエーションがあるので、ウェッジは、別というのも、もちろんありです。
僕も、ブランドこそ、同じPRGR Tuneですが、アイアンとウェッジは、別物という意識が強いです。
それで、プロゴルファーのウェッジへのこだわりですが、日本のプロゴルファーの多くが、新品ウェッジをそのまま試合に使うのではなく、ある程度練習にならして、少し使って使用感がではじめてから、試合に投入というプロが多いです。
その理由ですが、ツアープロが使うウェッジは、ほぼノーメッキです。
逆にメッキを使っているプロのウェッジは見たことがありません。
その理由は、スピンが掛かるためという答えです。
メッキのほうが少し、滑りやすいという意識があると思います。
もちろん、そんなことないよというデータもあると思いますが、プロの実感として、いろんな芝の状況やラフの伸び具合などトータル的に考えるとノーメッキということになるようです。
素材は、軟鉄が多いですね。多いというのはすべてではなく、鍛造よりもむしろ軟鉄鋳造のほうが多いかもしれません。
このあたりは、打感云々よりも、曲げやすい素材ということかもしれません。
それで、プロユースのウェッジですが、テレビで、タイガーのウェッジは、毎試合新品と聞いてちょっと驚きました。
タイガーは、今、テーラーメイドのウェッジですが、ソール形状など、ミルドグラインドになっていて、毎回同じモデルが手に入るということだそうです。
タイガーのモデルは、全体がノーメッキかどうかわかりませんが、市販品でもフェース面ノーメッキになっているので、やはり、ノーメッキに対する信頼感が強いのだと思います。
それで、毎試合新品だと、スピンがかなりかかるので、そのスピンコントロールをタイガーの技術でコントロールできるということだと思います。
ツアープロが新品のウェッジをすぐ使わない理由が、スピンが掛かりすぎるためということなので、(要は、想定よりスピンが掛かりすぎて、バックスピンの量が計算できない)タイガーは、やはり特別だと思います。
ツアープロの場合、大体、一か月から三か月くらいでウェッジを変えるようですが、その替え時期は、ラフから打ってポッコンボールが出た時と石川プロは答えていました。
これは、プロ独特の表現ですが、スピンの効くアプローチの打ちだし角度は、結構低くなります。
逆にスピンが掛からないと、同じ入射角で同じ距離をアプローチしても、少し打ちだし角が高くなります。
このあたりの感覚は、スピンが利いたアプローチができる人であれば、実感できると思います。
この打ちだし角が高くなることをプロは嫌がりますね。
さて、いろいろウェッジのことで長くなりましたが、ウェッジの打ち方によって、打ち方に合わせたウェッジを選択したほうが、結果的によくなります。
まず打ち方ですが、アプローチでインパクトで、左ひじを引きながら打つアプローチを多用する人。
このタイプは、実は、あまり打ち込まないアプローチになります。また、ややハンドファースト目にインパクトすることも多いです。
このようなアプローチに適したウェッジは、こんな感じです。
1:ソール幅広め
2:ややグース
代表的なモデルとしては、フォーティーンでいえば、DJシリーズとかですね。もちろん、ゼクシオなどのセットのウェッジでもOKです。タイトリスト VOKEYでいえば、K GRAINDです。
次に、フェースを開いて打つアプローチ前提で、積極的にソールを使うアプローチをする場合。
1:実質ソール狭め。
2:ストレートネック~ほんのわずかにグース
代表的なモデルは、フォーティーンであれば、FH Forged V1になりますね。他にもカスタムモデルで、ツアー支給品同等のノーメッキモデルもありますね。
フォーティーン FH Forged V1 ウェッジのお得情報はこちら!! ![]()
あと、テーラーメイドのミルドグラインド2などですね。こちらもフェース面ノーメッキモデルがあります。
テーラーメイド MILLED GRIND 2ウェッジのお得情報はこちら!! ![]()
タイトリストボーケイでいえば、ほとんどのモデルが当てはまります。
このようなプロ用モデルは、ソールをうまく使うことが前提になっているので、アプローチの種類が一つしかないと、そこまで必要ありませんが、いろんなアプローチテクニックを使うのであれば、あらゆる状況に対応できるウェッジがお勧めですね。
これは、いろいろ1本で対応できるからいいというわけではなく、1種類のアプローチしかしないのであれば、もっと簡単にそのアプローチができるウェッジがあるということです。
例を挙げて言うと、渋野日向子プロのように、アプローチはほぼピッチエンドランというようなタイプであれば、それにあったウェッジがあるという感じです。
但し、彼女は、どちらかといえば、いろいろ対応できるウェッジを使っていますので、いまのアプローチの引き出しに満足していないという表れでもありますね。
みなさんの、ウェッジはどうですか?
ということで、、、お得なウェッジの情報はこちら!!