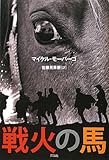
¥1,365
Amazon.co.jp
マイケル・モーパーゴ(佐藤見果夢訳)『戦火の馬』(評論社)を読みました。
『戦火の馬』は1982年に発表されたイギリスの児童文学です。第一次世界大戦におけるイギリスとドイツとの戦いを、一頭の馬の目線から描いた物語です。
訳者あとがきに詳しいですが、2007年に舞台化され、2011年にはスティーヴン・スピルバーグ監督の手によって映画化されました。今年の3月に日本でも公開されましたね。
戦火の馬 DVD+ブルーレイセット [Blu-ray]/エミリー・ワトソン,デヴィッド・シューリス,ピーター・ミュラン
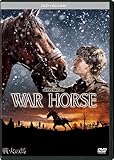
¥3,990
Amazon.co.jp
ぼくは先に映画版を観たんですが、映画を観ると原作も読んでみたくなる性分なものですから、あわせて小説の方も読んでみました。
ちなみに翻訳は、児童文学を多く出版している評論社から出ていますが、訳文、本の作りともにそれほど児童向けというのを前面に押し出してはいない感じです。
200ページくらいの短い作品なので、興味を持った方はぜひ読んでみてください。映画を観てから読むと、要所要所で印象的だったシーンが思い出されて、結構ジーンと来ます。
涙なしには読めないですね、これは。うるうるものです。うるうるものの作品ですよ。
戦争というのは、家族を引き裂き、何もかもを奪い去るものです。『戦火の馬』は強い絆で結ばれた1人と1頭、アルバートという少年と、ジョーイという馬が、離ればなれになってしまうという物語です。
戦争が始まり、ジョーイはイギリス軍のものになってしまいました。いよいよ別れの時、アルバートはジョーイとこんな約束を交わします。
「きっと探しに行くよ、おばかさん」アルバートがそっと言った。
「どこへ行こうと、おまえを見つけ出すからね、ジョーイ。大尉さん、ぼくが探しに行くまで、こいつをよろしくお願いします。こんな馬はどこにもいないんです、世界じゅうどこにも。おわかりでしょう。約束してくれますね?」(41ページ)
軍馬として戦地を駆け巡るジョーイは、思いも寄らない運命に翻弄されていきます。ドイツ軍に捕まって、ドイツ軍の軍馬になったりするんですね。
そして一方の少年アルバートも、ある強い決意を抱いていて・・・。
映画の宣伝で、”奇跡”というのが重要なキャッチコピーとして使われているように、たしかに『戦火の馬』は、ある種の奇跡の話ではあります。勿論それもとても感動的です。
ただ、滅多にありえないことが描かれているからこの物語は感動的なのではなく、戦争というある意味では異常な状況でも、失われていない人間としてのあたたかな心が描かれているからこそ、この物語は感動的なんだとぼくは思うんです。
馬のジョーイはイギリス軍、そしてドイツ軍の様々な人々と触れ合うことになります。当然というか何というか、戦争を楽しいと思っている人は一人もいません。両軍ともにです。
人々は絶望と悩みを抱え込み、矛盾を感じていながらも戦わざるをえないんですね。その姿が馬の目を通して描かれる時、深く心動かされるものがあります。
思いやりの心を持つ人々の行動にぐっと来る、うるうるものの小説です。
作品のあらすじ
こんな書き出しで始まります。
小さいころの記憶はまぜこぜになっている。小高くうねるように続く草原、暗くしめっぽい馬小屋、屋根の梁を走るネズミ・・・・・・ただし馬市の日のことだけは、はっきりおぼえている。あの日の恐怖は一生忘れない。(7ページ)
子馬の〈私〉は母親と引き裂かれて、売りに出されます。競り落とされ、連れて帰られた農家で出会ったのが、アルバートという13歳の少年でした。
「ぼくら気が合うね。おまえとぼくさ」(13ページ)とアルバートはやさしく鼻面をなでてくれ、〈私〉にジョーイという名前を付けてくれます。
農耕用の馬として使われる厳しい暮らしですが、アルバートと過ごす穏やかで楽しい日々です。しかし、やがてイギリスは、ドイツと戦争をすることになってしまったのでした。
農場の借金返済のために、アルバートの父親はやむを得ず〈私〉を軍隊のニコルズ大尉に売ることにします。
〈私〉が売られてしまうと知って、アルバートは慌てて走って来ました。アルバートはニコルズ大尉にこう言います。
「ジョーイはぼくの馬なんです。ジョーイは永遠にぼくのものです。だれが買おうと関係ありません。親父が売るのは止められないけど、ジョーイを連れて行くなら、ぼくも行きます。ぼくも軍隊に入って、ジョーイと一緒に行きます」
「君は、まさしく英国兵士の魂を持った若者のようだな」大尉はそう言いながら、ひさしつきの帽子をぬいで、額を手の甲でぬぐった。黒い巻き毛の、誠実で親切そうな顔があらわれた。
「魂は充分あるが、残念ながら年が足りない。まだ若すぎるんだ、わかるか。応募資格は十七歳以上なのだよ。一年経ったら、また来るがいい。また会おうじゃないか」(39ページ)
ニコルズ大尉は後でそっと〈私〉にささやきます。「正直に言うとな、ジョーイ。アルバートが入隊の年齢になる前に、この戦争が終わればいいと、俺は思うよ。なぜなら、いいか、実はひどい戦になりそうなんだ」(45ページ)
こうして離ればなれになってしまった〈私〉とアルバートですが、〈私〉はニコルズ大尉に大切にしてもらえます。同じく軍馬のトップソーンとも仲良くなりました。
ところが戦火の中、思いがけぬことが起こり、〈私〉とトップソーンはドイツ軍に捕まってしまいました。ドイツ軍の救急馬車をひかされることになります。
やがてトップソーンと〈私〉は、野戦病院のそばのフランスの農場で、少女エミリーとそのおじいさんとの穏やかな暮らしができるようになりました。エミリーはうれしそうにこう言います。
「大きくなって、もっと丈夫になったら、そして、兵隊さんがみんなお国に帰って戦争が終わったら、あたしあなたたちに乗って森を走るんだ。かわりばんこに」(92ページ)
ところが戦争は終わらず、〈私〉とトップソーンは再びドイツ軍で大砲をひかされることになります。面倒を見る役目を任されたのは、「アホのフリードリヒ」です。
「アホのフリードリヒ」は、ひとり言をぶつぶつ言ったり、冗談を言って一人で笑ったりしているので、周りからは頭がおかしいと思われている老兵です。
なので、嫌な仕事は何でも押し付けられてしまうんです。この「アホのフリードリヒ」のセリフが、この小説の中で最も心に残りました。
「いいかい、連隊じゅうでまともな人間は俺だけだよ。アホウなのは自分たちのほうなのに、わかってないのさ。だって、やつらは、何のためかわからずに戦争しているんだからなぁ。頭が変だろ? 着ている軍服の色が違うだけ、しゃべる言葉が違うだけなのに、どうしてそれだけの理由で人殺しができるんだ? なのに、俺のことをアホだとさ!(中略)だからな、戦争のあいだは『アホのフリードリヒ』として生き抜くのさ。そうしたらシュライデンの町に帰れて、肉屋のフリードリヒにもどれる。このバカな戦争がはじまる前は町中から尊敬されていた人間にな」(118ページ)
戦車の攻撃を受けて、命からがら逃げだした〈私〉は霧の中を走って行きます。傷だらけになりながらも、ようやくたどり着いたのは鉄条網に囲まれた「無人地帯=生きた人間のいない場所」(137ページ)でした。
つまり、塹壕(銃弾を避けるために穴を掘って攻撃と守備に備える所)でイギリス軍とドイツ軍が向かいあう、ちょうど中間地点です。どこにも行き場のない〈私〉は、このままでは死んでしまいます。
はたして〈私〉はここで息絶えてしまうのか? そして、戦場で起こった奇跡とは一体!?
とまあそんなお話です。映画と原作の違いについて少し触れておくと、原作は馬の語りで進んでいきますが、映画では馬のナレーションはなく、心理は描かれません。
「アホのフリードリヒ」の名ゼリフは映画にはなかったです。映画のドイツ軍で印象的なのはある兄弟なんですが、その兄弟は原作には出て来ませんでした。
細部は色々な違いがあるんですが、全体の流れとしては原作も映画もおおよそ共通していると言ってよいでしょう。
戦争は誰にとっても悲しい出来事です。誰もが起こってほしくないと思っているにもかかわらず、起こってしまうものなんですね。
戦争の中で馬はただ闇雲に引き回されます。その時の都合によって、あっちにやられ、こっちにやられ。
『戦火の馬』は運命に翻弄される一頭の馬を描いた物語ですが、戦争によって将来の見通しもないままに人生が揺さぶられてしまうというのは、人間でも全く同じことですよね。
そういった意味でこの小説は、馬から見た人間の愚かさを描いた作品であると同時に、一兵卒のような、力のない存在が自由を求めて必死に奮闘をする物語としても、読むことができるのではないでしょうか。
馬が語る児童文学作品と言えば、シュウエルの『黒馬物語』が有名なので、近い内にそちらも読んでみたいと思っています。
明日は、椎名誠『哀愁の町に霧が降るのだ』を紹介する予定です。