
¥880
Amazon.co.jp
山本兼一『利休にたずねよ』(PHP文芸文庫)を読みました。直木賞受賞作です。
千利休という人物をご存知でしょうか。織田信長と豊臣秀吉に仕えた茶人で、茶道を独特の境地にまで高めた人だと言われています。
豊臣秀吉に重く用いられ、北野大茶会を成功に導くなど、茶道に関してすぐれた功績を数多く残した千利休ですが、何かしらの理由で秀吉の怒りを買ってしまい、切腹を申し付けられてしまいました。
千利休はなぜ切腹を命じられたのか? 理由の推測はいくらでもできますが、これは決して解くことのできない、歴史に秘められた謎と言ってよいでしょう。
『利休にたずねよ』は、その謎に迫るというよりは、千利休の内面を深く掘り下げることによって、一つの答えを作り上げた小説と言えます。
「利休にたずねよ」というタイトルは、分かりやすく言い換えるなら、「その答えは、利休だけが知っている」なんです。千利休が切腹を命じられても絶対に譲れないものとは、一体なんだったのでしょうか。
大河ドラマや歴史小説などでは、激動の時代を自分の力で生き抜いた人が主人公になりやすいものですから、冷酷非常さを見せるものの時代の先を見据えていた織田信長や、身分の低い足軽から知恵と愛嬌でのし上がった豊臣秀吉などがよく取り上げられます。
すると、そういった物語の中では、千利休という茶人は添え物という感じで物語に登場するだけなんですね。
さらに言うなら、血なまぐさい戦と、狭く静かな空間で楽しむ茶道は対局にあると言ってよくて、茶道というのは、戦国大名の単なる道楽として描かれることが多いのではないかと思います。
さて、今回紹介する『利休にたずねよ』は、タイトルの通り、千利休という人物が中心になる歴史小説なんですが、戦国大名の単なる道楽だった茶道、そして茶人の千利休が中心の物語だなんて、面白いんだろうかと疑問に思いますよね。
読む前はぼくもそう思いました。でも、これが意外と面白いんです。
茶道というものは単なる道楽なんかではなくて、ぼくが思っていたよりも、もっと芸術的で、もっとスリリングなものでした。なんだか感心させられてしまいましたよ。むむむと唸る感じです。
たとえば、茶碗。安いものは安く、高いものは高いのが茶碗です。値段が高ければ高いほど、価値も高いわけですから、戦国大名はその茶碗をもう夢中になって欲しがるわけですね。
ただ、テレビで鑑定番組などもありますけれど、どの茶碗がよくて、どの茶碗がよくないのか、ぼくら素人には、はっきり言ってよく分かりません。
「これが100万円の茶碗です」と言われて、茶碗を見たら、「うわあ、さすがに100万円の茶碗という感じがするなあ」と思い、「嘘です。2千円の茶碗でした」と言われたら、「ああ、なんとなくそんな気もしたよね」と右往左往する感じだろうと思います。
千利休は、その茶碗のいい悪いを的確に見抜けると言えば、すごさが少し分かってもらえるでしょうか。凡人にはその判断基準は分かりませんが、とにかくいいものはいいですし、悪いものは悪いんです。
物語の中で、秀吉はこんな風に感じています。
やはり、不思議でならない。利休は、たぐい稀な美的感覚をもっている。
たとえば、百個ならんだ竹筒のなかから、あの男が花入を、ひとつ選び出すーー。
その竹筒は、たしかにまちがいなく美しいのだ。
節の具合にしても、わずかの反り具合にしても、えもいわれぬ気品があって、どうしてもその竹筒でなければならぬと思えてくる。
棗にしたってそうだ。同じ職人が作った黒塗りの棗を百個ならべておくと、あの男は、かならず一番美しい一個をまちがえずに選び出す。何度ならべ替えても、あやまたず同じ物を手にする。
ーーなぜだ。
なぜ、あんなふうに、いともあっさり、美しいものを見つけ出すことができるのか。(46ページ)
これはもう才能と言ってよいと思います。そう、千利休は茶道における天才なんです。物語の至る所で、千利休の美的センスやその才能が光る場面があります。
茶室の中に、花をどのくらいの量でどこに置くか。千利休が茶室を作ると、それがたとえ常識から外れたものだったとしても、目にした人すべてを驚嘆させる、素晴らしいものになります。
その感覚というのは、訓練で身につくものではないので、これは天才にしかできないことです。
ぼくは茶道にスリリングさを感じたと書きましたが、茶人と戦国大名と、茶室の中ではどちらが上になると思いますか?
たとえ美的感覚が劣っていても、権力のある戦国大名が上になるでしょうか。たいしてよくもない茶碗を戦国大名がいいと言えば、その茶碗の評価はあがるのでしょうか。
そんなことはないですよね。やはり茶碗を見極めるには、それなりの鑑定眼が必要ですし、茶道における感覚というのは、茶人の方が戦国大名よりも優れている場合が多いはずです。
茶人が戦国大名にうまく取り入ればよいですが、千利休は天才です。戦国大名に媚びへつらって、自分の感覚を歪めるということは決してしません。
千利休の能力に感心すればするほど、豊臣秀吉は内心穏やかではないわけですね。なぜ千利休にはその感覚があって、自分にはないのか。
すべてを手に入れたといっても過言ではない権力者が、茶道においては、1人の茶人に全く敵わないのです。そこにスリリングさが生まれて来ます。
作品のあらすじ
千利休の切腹の日の朝から、物語は始まります。奥さんの宗恩と会うのも、これが最後になります。すると奥さんが不思議なことを言い出します。
「あなた様には、ずっと想い女がございましたね」
雨音にまぎれて、よく聞き取れなかった。
「なんと言うた」
「恋しい女人がいらっしゃったのではないかと、おたずねいたしました」
「女人・・・・・・。なにを言い出すかと思えば、女の話か」
「はい。あなたには、わたくしよりお好きな女人が、おいでだったのではございませんか」(15~16ページ)
利休は答えませんが、1人になって茶の準備をしながら、遠い昔を思い返します。懐から取り出したのは、「掌にすっぽりおさまる緑釉の平たい壺」(21ページ)。
なぜ利休がこの壺をそれほど大切にしているのか、物語の最後で明かされることとなります。
この小説はやや変わった形式をしていて、それぞれの章で中心になる人物が違うんですね。次の章では豊臣秀吉、その次の章では細川忠興という風に、利休をめぐる複数の人物の目線から描かれていきます。
そしてなにより特徴的なのは、時間の流れがどんどん前に戻っていくことです。つまり、切腹の日の朝から始まって、ビデオを巻き戻すかのように、前に起こった出来事が描かれていくわけです。
そうした少し変わった形式なので、長編小説のようにぐいぐい読ませる力に欠ける小説ではありますが、茶道というもの、そして千利休という存在そのものを複合的に描き出すことに成功していて、そういう点で非常に面白い小説です。
ぼくが印象的だった章にいくつか触れましょう。やはりなんと言っても「鳥籠の水入れ」の章が面白いです。
この章では、ヴァリニャーノというイエズス会の宣教師が中心となります。ヴァリニャーノはキリスト教の布教活動をしている人物でして、伊東マンショ、千々石ミゲル、中浦ジュリアン、原マルティノの4人を連れて、豊臣秀吉に謁見することとなります。
ヴァリニャーノはヨーロッパの文化に誇りを持っていますから、日本を馬鹿にしているような所があるんですね。「建築や芸術において、日本のものでヨウロッパに勝るものはなにひとつとしてないのだよ」(161ページ)と4人に語っているくらいです。
中でもヴァリニャーノが奇怪に思っているのは、茶の湯です。
「そうだ。なぜ日本人は、あんな狭苦しい部屋に集まり、ただもそもそと不味い飲み物を飲むのかね。がらくたに過ぎない土くれの焼き物を飽きもせずに眺め、おたがいに白々しく褒め合うのかね。あんな馬鹿馬鹿しい習慣が、世界のどこを見まわしてもないことは、君たちもすでによく理解していることと思う」(162ページ、原文では「もそもそ」に傍点)
宝石ではなく、わけの分からない焼き物をありがたがっている奇妙な日本人。茶の湯があることが、日本がまだ文明国でないことの証拠だと、ヴァリニャーノはそう思っているわけですね。
日本の文化が馬鹿にされるとなんだか頭に来るものですが、冷静に考えてみれば、このヴァリニャーノの言葉というのは、もしかしたら現代のぼくらが思うことと、重なる部分も多いのではないでしょうか。
茶の湯に批判的なヴァリニャーノが、茶室に案内されて茶を飲んで、どんなことを思ったのか、そこで千利休とどんなやり取りがあったのかに注目してみてください。
同じように「野菊」の章では、名高い軍師の黒田官兵衛が、茶の湯に夢中になりすぎないように、秀吉を諌めます。
刀を持たずに茶室に入ると危ないですし、単なる道具にお金をかけるよりは、兵士を雇うべきであり、茶室で長いこと過ごすのは、時間の無駄に他ならないと言うんですね。それに対して、秀吉はどう答えたでしょうか。
この作品の中でも、とりわけ印象的なのは、「黄金の茶室」の章だろうと思います。育ちがいいからか、滅多に感情を表に出さない帝を喜ばせたいと秀吉に言われた千利休は、「黄金の茶室は、いかかでしょう」(347ページ)と進言します。
こうして黄金の茶室が作られたわけですが、黄金の茶室を作るという発想は、やはりどこか歪んだものがあります。そして、それを千利休自身が強く感じています。
流れ流れて、こんな茶室をつくってしまったじぶんが、利休は、われながら怖ろしかった。
ーーわしのこころの底には・・・・・・。
暗く、深い穴がぽっかりあいている。
そこから吹いてくる風が、いつも利休を狂おしく身悶えさせる。
利休は、さきほどの秀吉の下卑た笑いを思い出した。
大阪城で、ためしに組み立てた黄金の茶室で、秀吉は女を抱いたのだ。
見ていたわけではない。
つぎの間で控えていた利休は、女のむせび泣く声を聴いた。
聴きながら、利休は、淫蕩な想念が、勝手に走り出すのをどうすることもできなかった。
それは、黄金の茶室を思いついたときから、利休の脳裏にあった光景である。秀吉は、利休とおなじ衝動をおぼえて、実行したにすぎない。
ーーあの女・・・・・・。
利休は、またあの女を思い出していた。(351~352ページ)
はたして、利休の心に棲む女とは一体誰なのか? そして、緑釉の平たい壺にまつわる、ある出来事とは!?
とまあそんなお話です。千利休の恐ろしいほどの才能と、内に秘めた苦悩が描かれた歴史小説です。
茶道に興味のある人はもちろん、茶道に興味のない人でも、「退屈でつまらないもの」というような、茶道についての固定観念が吹き飛ばされる感じの小説ですので、ぜひ読んでみてください。
章ごとに複数人物の目線で描かれ、しかも全体的に時系列が逆という構成の妙もさることながら、茶道を通して描かれる千利休の才能が、極めて巧みに描かれた小説です。
なかなかに新しい感覚の歴史小説だと思いました。
おすすめの関連作品
リンクとして、映画を1本紹介します。「天才の死にまつわる話」と言えば、なんといっても『アマデウス』でしょう。
アマデウス [DVD]/F・マーレイ・エイブラハム
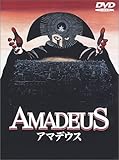
¥2,100
Amazon.co.jp
『アマデウス』は言わずと知れた天才作曲家モーツァルトとその死をめぐる物語です。
ちょっとうろ覚えなのが申し訳ないですが、ぼくが最も印象的だったシーンは、モーツァルトがサリエリという作曲家に、「ここの音はこうだよ」と言って、実際に弾いてみせる所です。
自分の作曲した曲じゃないんですよ。他人の曲を聴いて、「ここの音はこうだよ」と変えて弾くわけです。驚きですよね。
千利休が茶碗のいい悪いを感覚で判断できたように、モーツァルトも感覚的にこの流れだったらこの音であるべきと思ったわけですね。
映画を観ていて、「ああ、これぞまさに天才ということなんだろうなあ」と思わされました。
モーツァルトがかなり変なやつに描かれているので、モーツァルトのイメージが変わってしまうかも知れませんけれど、機会があれば、ぜひ『アマデウス』も観てみてください。
明日は、伊坂幸太郎『死神の精度』を紹介する予定です。