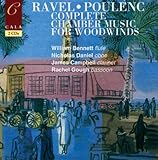「La Folle Journée au JAPON 2012」のテーマは「サクル・リュス(Le sacre Russe)」だそうで。
フランス発祥のラ・フォル・ジュルネですからテーマもフランス語なのでしょうけれど、
リュスはバレエ・リュス
のリュスで分かるにしても、サクルの方は…。
こちらも考えてみれば、ストラヴィンスキー
の「春の祭典」が「Le sacre du printemps」であることからすると、
「Le sacre Russe」はさしずめ「ロシアの祭典」ということなのでしょう。
意外にこうしたつぎはぎでも理解できるものだと思ったりするところでありますが、
「ラ・フォル・ジュルネ」自体は面白そうだと思いつつも、混雑が苦手なたちだものですから行ったことがない。
ですから、その代わりと言ってはなんですが、ロシア尽くしの演奏会に行ってきたような次第です。
何しろプログラムがムソルグスキー
、ストラヴィンスキー、チャイコフスキー
でありましたから。
ただし、こたびの演奏会の特徴はといえば、
「ロシア・ピアニズムの継承者たち」と銘打たれた企画(その第6回)でして、あくまでピアノがメイン。
ですので、最初に取り上げられたムソルグスキーの組曲「展覧会の絵
」にしても
ピアノ独奏のオリジナル版で、演奏会の最後を飾るのもチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番なのですね。
間に置かれたストラヴィンスキーのバレエ組曲「火の鳥」は、
もしかすると伴奏に徹する新日フィルの奏者(特に管楽器)の欲求不満解消用ではないか
と思ってしまったりするところでもありました。
会場で配付されたプログラムの解説に曰く、「躍動感溢れるパッションを漲らせながら
クライマックスへと突き進む鮮烈なドラマはジルベルシュタインの独擅場だ」と記された
独奏者リリヤ・ジルベルシュタインの輝かしく粒立ちのいいピアノには、
いずれも最後にぐおっと盛り上がる今回の曲目はピタリくるものだったのではないですかね。
アンコールに至って「あらら、やおらショパン ?」と(ピアノ作品を知らない者には)思えてしまった
リャードフのワルツ、そしてリスト の「カンパネラ」ばりに
ポキポキと鳴る様子も楽しい、同じくリャードフの「音楽の玉手箱」という、
傾向の違った曲を聴かせてくれたのはサービス精神でしょうか。
それでも、ここまできっちりロシア尽くしとは、首尾一貫した演奏会だったなあと思ったりするわけです。
ところで、演奏を聴きながらまたあれこれ思いつくことありだったのですが、
ここではムソルグスキーの「展覧会の絵」のことを少々。
「プロムナード」という展覧会場で絵から絵へ移っていくそぞろ歩きのイメージは、
ラヴェル編曲でこちらの方が有名になってしまった管弦楽編曲版よりも
ピアノ版の方が美術館の静かな雰囲気にマッチしますし、
BGMというよりはひとつの絵を見ての印象の余韻はそれぞれの絵で異なるわけで、
メロディは同じでも違った印象を受けた心の揺らぎが
何度か出てくる「プロムナード」ごとに異なるのは当然にしても、
やはりピアノ一台くらいでやってもらった方が一人の鑑賞者がいろいろな印象に心揺らしながら
館内を経巡るのに合ってるんじゃなかろうかと。
そうしたことを思うと、今度はそれそれの絵に立ち止まって見入るとき、
それぞれの絵のタイトルが付された曲が奏でられますけれど、
どうも演奏が大袈裟なんじゃなかろうかと思えてくるのですね。
これは今回のジルベルシュタインの演奏がということでなくって、傾向としての話ですが。
ジルベルシュタインの演奏は、従来から言われるように
この曲が求めるヴィルトゥオジティに溢れて恰も大伽藍を仰ぎ見るようでしたけれど、
この曲でヴィルトゥオジティを発揮する(分かりませんけど、弾くこと自体大変な技巧なのでしょう)ことと
壮大な建築物を見るかのような曲の見せ方(聴かせ方)は別なんじゃないかなと、ふと思ったわけです。
もしかしたら、ラヴェルの管弦楽編曲版による演奏が
この曲の見せ方(聴かせ方)の、いわば模範になってしまって、
それ故にピアノ一台でもオケと同じような壮大な世界を再現できますよ的な傾向ができてしまったのかなとか。
「プロムナード」で触れたように、展覧会場を鑑賞者が絵を見て何らかの印象を持ち、
その絵の印象を余韻として別の絵に移っていく様を描写的に作り上げた曲だと考えるならば、
ことほどかほどに爆発的な印象を絵ごとに抱えて見るということは少ないのでないですかね。
もちろん絵との相性によってはそれこそ爆発的にびりびり来てしまうような出会いもないとは言いませんが、
実はムソルグスキーの頭の中ではもそっと静かな炎のような感情の揺らぎを、
ピアノでこそ表したかったのかなと思ったりしたのでありますよ。
組曲「展覧会の絵」は、とかく爆演系のイメージのある曲ではありますけれど、
静かな感情の高ぶりとおちつきへの回帰の繰り返しのような演奏があるならば
そうした演奏も聴いてみたいことよと思うのでありました。