まあ、昨日のようなここで書かずともいろんなところでいろんなふうに展開されるであろう議論は、
弊店「chain reaction of curiosity」には必ずしもそぐわないので、また元の路線に戻ります。
戻ったところが「またアーサー王
かよ…」とお思いの方もおいででしょうけれど、
そのうちに気が付いたら興味の方が全く別の方向に行ってるものと思いますので、
ご容赦くださいませ。
いささかの探究をしつつも、物語としてのアーサー王の話を素通りしておりましたので、
手っ取り早く筋をたどれるのではと映画に頼ってみたわけでありますね。
アントワン・フークア監督による「キング・アーサー」。
前から家にDVDソフトがあったので、一度見始めたとこがあったのですが、
どうにもツカミがよろしくない!とほんの頭のところで一度は諦めたという経緯があります。
おかげさまで今回は先に周辺部分を探究しておりましたので、
も少しすんなり入り込むことができたわけでありますが!
探究していたおかげで(せいで?)「なんだ、この話?」と思ってしまったのですよ。
(ちなみに、あれこれ映画の解説を探ることなく見て気付いたことだけで書いてますので、
思い違い部分もあろうかと…)
映画はアーサーがブリトン人の王になるまでを描いたものであるようですけれど、
そもそもアーサー(クライヴ・オーウェン
)はどうやらローマ人とブリトン人との混血であるらしく、
最初からキリスト教徒であり、ローマを懐かしむような場面も時折混ざります。
そして、円卓の騎士であるランスロット、ガウェイン、ガラハッド、
そしてトリスタンらはローマに年季奉公する傭兵隊であって、
かつて勇猛で知られたというサルマティア(南ウクライナ
あたり)の
イラン系遊牧民族サルマート人だということになっているのですね。
ローマ軍はウォードと呼ばれる土着の民族(ローマから見てですが)との戦闘を繰り返しており、
そのウォードの長がマーリンであり、グウィネヴィア(キーラ・ナイトレイ)はウォードの女性闘士という設定。
北辺からサクソン人が侵攻してくる頃合に、ローマ軍はブリテン島を放棄し、
アーサーと円卓の騎士たちは紆余曲折の後にウォード(どうやらブリトン人のようです)と組んで、
サクソン人との一大決戦に臨むという…。
このサクソン人との決戦では、トリスタンが倒れます。
サルマティアから15年の年季奉公として連れてこられたのは少年時代でしたから、
イゾルデとの出会いはその後でないと話になりませんが、
ここでトリスタンが倒れては「トリスタンとイゾルデ」の話は消え失せてしまう…。
そして、ランスロットが倒れます。
苛烈な戦場にあっていささかも怯むことなく戦っていたグウィネヴィアが、
危機にさらされてまず駆けつけるのがランスロットと、その後の二人の関係を思わせるところながら、
ここでランスロットが倒れてはその後のロマンスも消え失せてしまう…。
そもグウィネヴィア姫とは、かほどにご気性の荒い方とは…ですが。
最後の部分に触れるのは反則かもですが、
結果的には何とかサクソン人を撃退し、アーサーはグウィネヴィアと結ばれることをもって(?)
ウォードすなわちブリトン人の王位を就くことになるという。
以上、全巻のおしまいであります。
てなことでですね、ひとつだけ言えるのはまかり間違っても
この映画「キング・アーサー」の筋が一般的に流布されたアーサー王のお話だと思ってはいけませんよ
ということなわけです。マーク・トウェイン
の話があるなら、これだって…なのかもですが。
そうそう、湖の騎士ランスロットを演じたヨアン・グリフィズですけれど、
どうしてもインパルス板倉に見えてしまうのは「私だけ…」でありましょうか。
![キング・アーサー ディレクターズ・カット版 [DVD]/クライヴ・オーウェン,キーラ・ナイトレイ,ヨアン・グリフィズ](https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fecx.images-amazon.com%2Fimages%2FI%2F51HKW0PQYNL._SL160_.jpg)
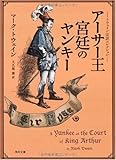
![勇気ある追跡 [DVD]/ジョン・ウェイン](https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fecx.images-amazon.com%2Fimages%2FI%2F511IJqDZfEL._SL160_.jpg)
![アラモ [DVD]/ジョン・ウェイン,リチャード・ウィドマーク,ローレンス・ハーヴェイ](https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fecx.images-amazon.com%2Fimages%2FI%2F51-rgHb8zTL._SL160_.jpg)
