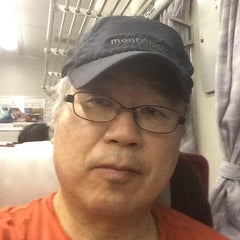我々が普段使っている日本語
母語話者は約1億2千万人。それだけ見れば世界有数の大言語です。
しかしその起源はよくわかっていません。ただ膠着語という言語に分類されるようです。過去にはアルタイ語説、ウラル=アルタイ語説などがありましたが、今では独立/孤立語説が有力です。
(岩波新書、2007年)
大国語学者の故・大野晋さんは『日本語の源流を求めて 』などで執拗に「日本語タミル語起源」を主張していますが、その証拠と挙げているものの中には、事実誤認、こじつけも多く”老害”の域を出ていないような気がします。
但し、日本列島の南(長崎、福岡南部、熊本、宮崎)と北(栃木、茨城、福島、宮城、山形内陸)に無アクセント地帯があるのは異言語との接触地帯であるからだという指摘は注目に値すると思います。縄文語は無アクセントであったという考えがあるからです。
(新潮選書、2017年)
文筆家・伊東ひとみ著『地名の謎を解く: 隠された「日本の古層」 』は、地名を手掛かりに日本語、ひいては日本人のルーツを探っています。
例えば川の源流部を「沢(さわ)」というのは、親不知・桑名線以東の東日本だけで、西日本では「谷(たに)」と言います。それは、もともと縄文語系の「さわ」があったところに弥生語系の「たに」が西から拡がり親不知・桑名線で停滞したためとしています。また台地を刻んだ小河川が造る湿地を「谷」と書いて「や」、「やつ」、「やち」、「やと」と呼ぶのも東日本だけとということを指摘しています。
ここでも縄文語があったところに、弥生語が西から拡がり両者が交わったことで日本語が誕生したという仮説が示されています。
(平凡社新書、2017年)
『通じない日本語』で日本語学者の窪園晴夫は、音声学的な観点から日本語は母音で終わる」「モーラ言語」、子音で終わることが多い英語や朝鮮語は「音節言語」であると説きます。
しかし、そのモーラ度は全国一様ではなく、関西弁はモーラ度が高く、東日本や南九州は音節言語的であると述べています。おそらく、弥生語はモーラ言語であろう(本書で明言はしていないが)と思います。
ほか、私は日本語の起源の関する本をいくつか読んでいます。
これらよりますと、日本語は縄文語の上に弥生語がかぶさって(まじわって)できたものという仮説がいまの流れの様です。
どの本だったのか思い出せませんが、縄文語の無アクセント的なところにアクセントがはっきりした弥生語がひろまったことにより方言ごとの様々なアクセントパターンを示すようになったというものがあったとの記載がありました。
では、弥生語、縄文語とはどんな言語か?なんて弥生人・縄文人がいま生きている訳ではないし、文字も持っていなかったので文献もなく当然わかっていません。中国の文献には倭人が登場しますが、”倭人がどんな言葉を話していたか?”についてまでは語られていません。
「弥生語がどこから来たのか?」は「弥生人がどこから来たのか?」に重なります。今の説では、弥生人は朝鮮半島南部または中国江南地方からやって来たとされています。
現在朝鮮半島全域で朝鮮語が話されています。朝鮮語は膠着語に属するものの音節言語であり、モーラ言語とされる弥生語とは異なります。但し弥生期以前の朝鮮半島南部が朝鮮語的な言葉を話していたという保証はどこにもありません。また、済州島(チェジュ、済州道)では古代は倭人と同じかそれに近い言葉を話していたという説があります。
一方で中国江南地方は当時「越」と呼ばれ、越人は中原の漢民族からは異民族と認識されていました。越人はオーストロアジア系言語(ベトナム語など)またはシナチベット系言語(タイ語など)を話していたと考えられますが、現在のそれらの言語多くは音節言語です。
日本語周辺にモーラ語はほとんどないわけですが、強いてあげるとすれば、太平洋の島々に広く話されているオーストロネシア系の言語(ポリネシア語など)です。
音節言語的な縄文語はどのような言語だったのかも同様にわかっていませんが、隣接するアイヌ語は音節言語です。よって本北部にアイヌ語地名が残っていることから縄文語はアイヌ語と関係するのではないかという説があります。
ただし、モーラ語と音節語のと交代は起こりうるものかもしれません。同じアーリア系の印欧語族では音節語的な英語、ドイツ語に対して、イタリア語、スペイン語はモーラ言語的であり、フランス語はその中間に位置しています。
結局のところ、日本語の起源はわからない というのが本音で、日本語はクレオール言語であると言って逃げるしかないというのが現状ではないでしょうか?