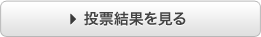ブログネタ:夏、楽しんでる? 参加中
ブログネタ:夏、楽しんでる? 参加中私は楽しんでない派!
本文はここから夏だからといって特別な事があるわけではありません。
夏だから特別に少しだけ江戸に帰ってもいいなんて言われるわけもなく…
ごめんなさい、少し愚痴を吐いてしまいました(ため息)
江戸に帰りたいというより、父様が江戸に帰っているんじゃないかとか、家にいなくても一度帰っていて私宛の置手紙があるんじゃないかとか…そういう事が気になっているんです。
『夏』という文字は、大きな面をつけて踊る人を象ったものです。
だから本来夏という季節は、騒がしく、楽しく、陽気に過ごす季節なのでしょう。
耳をすませば夏の音はひっきりなしに私の耳に入ってきます。
女の子達のはしゃぐ声、祭へと急ぐ下駄の音、打ち上げ花火の轟音、それらはまるで異世界での出来事のようです。
そうですね…私にとって身近な夏の音と言えば、蝉の鳴き声くらいですね(笑)
私は部屋で横になり、うとうとしながらその音を聞いていました。
誰かに揺すられ、起きるようにと促されるものの、頭がぼんやりしていて何事が起きているのか良くわかりません。
頭が軽く痛み、なんだか眠いし、体を動かす事が容易ではないと告げると、一杯の水を飲まされ、頭に濡れた手ぬぐいを乗せられました。
無理に起きなくてもいい、目が覚めたら飯を食え、なんならそのまま寝てもいい、そんな事を言われた気がします。
それが誰だかわからないまま適当な返事をして、私は再び深い眠りへと堕ちて行きました。
気がついたら外はすっかり陽が落ちていました。
「寝てた…」
頭の中で今日の出来事を反芻してみる。
(特に急な用事は言いつけられなかったから大丈夫か…ぁぁぁぁあ)
「あっ!」
私は慌てて跳ね起き、たらいと洗濯板を手に井戸へと向かいました。
「洗濯…洗濯するのすっかり忘れてた。どうしよう…こんなにも溜まっちゃって…今晩中に干せば朝には乾くよね?夜風も生温いし、朝からすごく暑いんだもん」
昼間に惰眠を貪った分、私は全力で洗濯物を洗って手早く干し、夕餉を食べる気力もなく部屋に戻り、また深い眠りにつきました。
そして翌朝…
「うそ…乾いてない。これも、これも、これも生乾き。なんで?干し方が悪かったの?」
着る物が乾いていないという事は、皆さんの着る物がないという事です。
「千歳ちゃん、おはようさん!悪いな~着物全部洗ってもらってよ。もう京の街中歩き回ったら汗だくでよ。汗臭くてどうにかなりそうだったぜ」
「よう、千歳、おはようさん。毎日洗濯ありがとうな。取り込むのは手伝うぜ」
「永倉さん、原田さん…ごっ…ごめんなさい」
私は頭を深く下げ、夜中に干したため着物が乾ききっていない事を、お二人に説明しました。
「あ~そういやぁ、昨日巡察に出る前に千歳ちゃんが縁側で寝てのを見た気がするな」
「ごめんなさい…」
「珍しいな。疲れて眠りこけてたのか?あんまり無理すんなよ」
「本当に申し訳ございませんでした…」
傷つけまいと気を遣ってくれているお二人の言葉がかえって心に痛く感じる。
「まったくお役に立てず、しかも惰眠を貪り、挙句に洗濯もろくに出来ないなんて…」
「いいっていいって!千歳ちゃんは洗濯係じゃねーしよ」
「新八の言うとおりだぜ。ここんところ千歳に甘えっぱなしで、さぼってたのは俺達の方だしよ」
「でも…」
不覚にも泣き出しそうな私の扱いに困り果てたお二人は顔を見合わせ、大きなため息をつきました。
「あ~…なんだ、ほれ、今は夏だ。夏ったら暑い。今年は特に暑い。こう暑いと着物一枚着ているだけでも暑っ苦しい。なぁ、左之。特に鍛錬していると着ている物が汗でべったり体にくっついて気持ちが悪いよな?」
「そうだな。新八の言うとおり、体にまとわりついて気持ち悪いな」
「はぁ…」
「だったらよ…」
「へっ?」
永倉さんは着物に手をかけ…

「いっそ着ないでいた方が快適ってもんだぜ!」
「!!!」
それに同意するように頷いた原田さんも続いて…

「そうだ!着物くらいでガタガタ言うなんて了見が狭い男の証拠だ!いっそ裸で過ごせ!」
「ちょっ///」
「左之。ついでに水浴びすっか!」
「えっ///」
「おう、いいな。朝飯前にいっちょやるか!」
着物を脱ぎ捨てたお二人は井戸の水を頭からかぶり、楽しげに歓談し始めました。
とにかく目のやり場に困るし、側で見届けるのも変なので、私は部屋に戻る事にしました。
「ふぅ…」
(何事が起きても、結局はその状況を楽しんだ者勝ちなんだな…ちょっと羨ましいかも)
「だけど…皆さん揃って一日上半身裸だったら…困るな…」
私は謝罪の言葉を考えつつ、一刻も早く着物が乾ききる事をただただ祈るのでした。