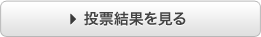ブログネタ:今シーズン、雪は見た? 参加中
ブログネタ:今シーズン、雪は見た? 参加中私は見た派!
本文はここから「雪…」
見上げれば止まる事無く、空から白い結晶が舞い降りてくる。
突き刺すような寒さに晒されながら、私はただ黙って雪の結晶を目で追いかけていた。
髪に、服に、手のひらに雪が落ちるたび、わずかな熱がその姿を消し去ってしまう。
舞う雪を桜の花びらのようだと例える人がいるが、雪は桜よりも儚く寂しい存在だと思った。
桜は地に落ちても、薄紅色のその姿が消える事はない。
雪は…地に落ちた途端、融けて姿を消してしまう。
融けきれなかった雪は大地に積もり、世界を音も色も無い世界へと変えていく。
何もない…無の世界へと変えていく。
私の傍に誰かがいる。
私はその人にかける言葉を見つけられずにいた。
私の心の中にあるのは不安、絶望、恐怖、そして…わずかな希望。
そのわずかな希望を形にしようと口を開いてみるものの、どうしても声が出ない。
黙りこくる私の隣で、その人はゆっくりと口を開いた。
「五歳優游同過日 一朝消散似浮雲 琴詩酒友皆抛我 雪月花時最憶君」
何かの歌ですか?と、恐る恐る問うてみた。
これは海を渡ったところにあった唐という国の詩人が詠んだ歌だと、その人は教えてくれた。
強く想う人を思い出しているのだろうか。
この人は今どんな気持ちでいるのだろう。
私はどんな言葉も口にする事が出来ないでいた。
どんな慰めの言葉もあたたかな言葉も、この人の傷を癒す事など出来ないと知っているから。
だから、ただ黙って雪を見ていた。
白い雪が、私の中の不安を打ち消してくれるようにと。
白い雪が、志半ばにして失われた多くの魂に、安らぎを与えてくれるようにと。

この人の心深くにある傷を…どうかこの清らかな白が浄化してくれるようにと…。
「ん…夢?」
吐き出す息が白く立ちのぼる。
「…夢…か…」
どうやら夢を見ていたらしい。
やけに現実的な夢だった。
「寒い…けど…起きなくっちゃ…」
頭ではわかっていても、体は正直だ。
手が自然と掛け布団を引き寄せ、頭まですっぽりと覆いつくしてしまった。
「二度寝最高…」
もう一度目を瞑った。
夢の中、私はどこにいたんだろう、誰といたんだろう、そんな事を考えながらさらに深い眠りへとおちて行く。
しかしそれはすぐに破られる事となった。
「おい!千歳!起きてっか?外出てみろよ、雪!雪だぜ!なぁなぁ雪合戦しようぜ。土方さんに見つかる前によ!…ん…まだ寝てんのかよ?おい!起きろ!千歳!」
「へっ平助君?はっはい!起きてる!大丈夫!起きてる…起きてるよ!着替えて顔を洗ったらすぐに行くから、平助君先行ってて」
問答無用で襖を開けられるかとヒヤヒヤして、慌ててお布団の中から飛び出した。
「おう!待ってるからな!」
夢と同じ…刺すような冷たい空気が身を包む。
伸びを一つして手早く着替えを済ませ、顔を洗うために井戸へと向かった。
あの夢はなんだったんだろう。
夢の中にいた人は誰だったんだろう。
おぼろげな残像、そして胸を締め付けられる感覚。
それだけははっきりと憶えている。
でもそんな感傷は、すぐに打ち破られてしまった。
「千歳!何やってんだよ!早く!新八っさんと左之さんが馬鹿みたいに雪玉作って投げつけてきてたまんねぇ!くっそ!多勢に無勢なんて卑怯だぞ!」
「ごめん!今行く!」
私は大慌てて平助君の傍に駆け寄り、足元の雪をすくって雪玉を作った。

刺すように冷たい雪の感覚が今朝の夢を思い出させた。
あれは…本当に夢だったのだろうか?
現実とも夢とも区別のつかない夢を、私は何度も見ている。
どれもその時感じた感情をはっきりと思い出せるくらい、現実感のある夢だった。
(正夢…まさかね…違うよね)
もしかしたら私の見る夢は、私が辿る未来の可能性なのかもしれない。
だとしたら…
近い未来、それとも遠い未来にいたあの私は、何を思い、何を考えていたのだろうか。
雪月花時最憶君
雪月花の時 最も君を憶う

雪のように儚く 月のように眩く 花のように美しく 生きる貴方を最も憶う