こんにちは。
中国コミュニケーションコーチ堀江です。
さて、前回に続き、「中国語のピンインの覚え方のコツ」についてです。
「ピンインが分からない」という原因を、
1、ピンインの読み方が分からない。
2、漢字の読み方が分からない。
の2つに分けて、前回は1の「ピンインの読み方が分からない」について説明しました。
読んでいない方はこちらをご覧ください。
中国語のピンインの覚え方のコツ1:「読み方が分からない」では、今日は「漢字の読み方が分からない」を解説していきますね。
例えば、中国語で
「我是日本人.」
と見て、直ぐに
「Wo3 shi4 ri4 ben3 ren2」
とピンインが出てこない。
ぶっちゃけ、これも
「一つ一つ漢字を引いて、覚えてください。」が答えなんですが、いくつか傾向と対策もあるので、それをご紹介します。
1.日本語の読みを引きずらない例えば、「我」を「ga」とは読まず、「wo3」と読む。
「いやいや、当たり前じゃないですか!」
って突っ込むあなた!
良かった。そういうあなたはきっと大丈夫。
ですが、結構いるんですよ。
「なんで「我」を「wo3」って読むんですか?」って質問する人が。
日本人は下手に漢字文化なので、無意識にそっちに引っ張られるようなんですね。
しかも「我」なんて、漢字だけ見たら日本語も中国語も同じ、意味も同じ。
そこで読み方だけ違う事に対して頭が違和感を覚えるようなんです。
これはもう完全に意識するかしないかの問題ですが、大前提として「日本語と中国語は違う言葉である」という事を再度認識してください。
少なくともそれだけで、「あぁ~!なんでこの漢字こんな変な読み方するんだよぉっ!」というイライラから解放されるはずです。
2.漢字の構造を理解する。「漢字の部首には2種類有ります。
1つは意味を表す「意符」、もう一つが音を表す「声符」です。
例を出した方が分かり易いですね。
例えば、
「芬、氛、纷、汾、粉、份、忿」の場合。
声調はそれぞれ違いますが、全部「fen」と読みます。
そして、全ての漢字に共通している「分」これが、音を表す声符となります。
もう一つ、例えば、「粮」という漢字の左側の「米」、これは穀物である事を意味を表す意符となります。
漢字は基準となる少数の漢字を除き、通常は意味を表す「意符」と音を表す「声符」から構成されているのです。
先ほどの「粮」も、
「米」=食糧を意味する。
「良」=音を意味する。「Liang2」
って事で、「粮」は「Liang2」と読むわけです。
また、先ほどは「芬、氛、纷、汾、粉、份、忿」(fen)のように分かり易い例を出しましたが、声符と読み方が違うパターンが主に3つ有ります。
1.声母が違う。あっ、ちなみに、「声母」(せいぼ)とは中国のピンインを構成する要素の一つで、英語で言えば「子音」みたいなものです。
「Wo」なら「W」が声母となります。
反対に、英語の「母音」にあたるのを「.韻母」(いんぼ) と言います。
「Wo」なら「o」が韻母となります。
例えば、
赴(fu4)と卜(bu3)
同じ、声符「卜」を持ちますが、声母が「f」と「b」で事なります。
他にも、
桃(tao2)と兆(zhao4)
共通部分が「ao」で、声母が「t」と「zh」で事なります。
2.韻母が違う。今度は逆のケースですね。
例えば、
废(fei4)と发(fa1)
声母が「f」で共通していて、韻母が「ei」と「a」で異なります。
他にも、
结(jie2)と吉(ji2)
声母が「j」で共通していて、韻母が「ie」と「i」で異なります。
3.全く違うこれは例外って事で、仕方が無いですね。
と、ちょっと小難しい話をしましたが、これはざっくりと覚えていれば大丈夫です。
もちろん例外も沢山あるので、「漢字が読めないけど読まなきゃいけない」とか、「パソコンで中国語を入力したいけど、ピンインが分からない」って時に、こうじゃないかな~?と「あたり」をつけるくらいでしょうか。
また、実際に辞書で読み方を調べた際に、「やっぱりこの漢字はこう読むのか」と理解していれば、覚えるのも早くなります。
「丸暗記」なのか、「理解した上での暗記」なのか。
後者の方がずっと記憶に残ります。
3.日本語の「音読み」を参考にする。「上述の「1.日本語の読みを引きずらない」と反対の事を言っていますね。
分かっていますよ。(@^▽^@)
「日本語の読みを引きずらない」って言うのは気持ちの上での話しで、
「日本語の「音読み」を参考にする」って言うのはテクニック的な話だと理解してくれると嬉しいです。
ご存知の通り、日本の漢字って中国から伝わってきた訳ですよね?
そして、伝わったのは漢字の「形」だけではなく、「音」も伝わってきたわけです。
それが漢字の「音読み」ってやつです。
(ちなみに、元々あった日本語に漢字をくっつけたのが「訓読み」です。)
もちろん、当時の中国語は今の中国語と違います。
でも、元をただせば同じ中国語。
日本の漢字の「音読み」からも、何となーく中国語の発音が見えてくるんですね。
「見えてくる」というか「パターン化される」と言えば良いでしょうか。
1つ、有名な例を出しますね。
ちなみに、中国語の学校に通っている方。
先生がこの話を知らなければ、その先生はへなちょこ先生だと思って良いくらい、実用的且つ有名な例です。
中国語学習者を悩ませる発音の一つに「n」と「ng」というのが有ります。
中国語を勉強していない方にも分かるように説明すると、
両方とも同じ「ン」の発音なんですが、
「n」がきっぱりと切る「ン」、
「ng」が鼻にかかる「ン」。
え~と、もっと分かり安く言うと、
「案内」(あんない)の「ん」は「n」で、
「案外」(あんがい)の「ん」は「ng」です。
ちょっと言ってみてください。
どう?ちがうでしょ?
日本語はこの2つの「ン」使い分ける言語体系ではないので特に注意する事はないのですが、中国語ははっきりとこの2つの「ン」を使い分けるんですね。
で、どの漢字が「n」なのか「ng」なのかですが、日本の漢字から判断が出来るんです。
それは、
音読みで読んで「ん」で終われば、中国語でも「n」で、それ以外は「ng」。
例えば、林。
音読みは「りん」、中国語は「lin」。
その他にも良く見る「りん」と読む、「琳、凛、臨、隣、吝、霖」は中国語でも「lin」。
もちろん例外もありますよ。
鈴は音読みで「りん」でも、中国語では「ling」で「ng」となります。
でも、大体は当たっています。
これも例外は沢山ありますので、多用は出来ませんが、「日本語の読み方は分かるんだけど!」という漢字が有れば、試してみる価値はあります。
例えば、「紅」の中国語は「hong2」、音読みは「こう」と知っています。
「洪」という漢字の中国語は分からないけど、音読みは「こう」と知っています。
すると、「う~ん、同じ『hong』かな?」と見当がつくわけです。
(そして実際に「洪」の読み方は「紅」と同じ「hong2」です。)
もちろん、上述の「声符」も応用できます。
「共」は中国語で「gong4」ですので、声母が違うだけで、発音は近いですよね。
ちなみに、中国人でも全ての漢字を読めるわけではありません。
例えば、私の名前の「堀」の字。
中国語にはあるのですが、常用漢字ではないので、ほとんどの方が読めません。
では、彼らは何と読むかというと、似たような漢字の「掘」の発音「jue2」と読むんですね。
(上述の声符の事を知っている中国人は、「屈」という字が「qu1」よ読むので、こちらに近い発音で読みます。)
さて、長くなってしまいましたが、「漢字の読み方が分からない。」というお悩みの解決のヒントをご紹介しました。
もちろん、上記ご紹介したのはちょっとした考え方のコツなので、原則は「面倒だと思わずに、分からない漢字に出会ったら辞書を引く」ですが、調べられない環境下や、ちょっとした理解の一助になれば幸いです。
ピンインが読める、分かるという事は「発音を聞いても分かる」という会話能力の基礎になります。
ここを面倒臭がって適当に過ごすと、後に壁にぶつかるので、しっかりと基礎を作るようにしてくださいね。
ではでは!
今日の話は面白かったですか?良ければクリックして応援お願いします!
↓ ↓ ↓
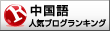
中国コミュニケーションコーチ堀江 昇
Blog:
http://ameblo.jp/chinahorie/