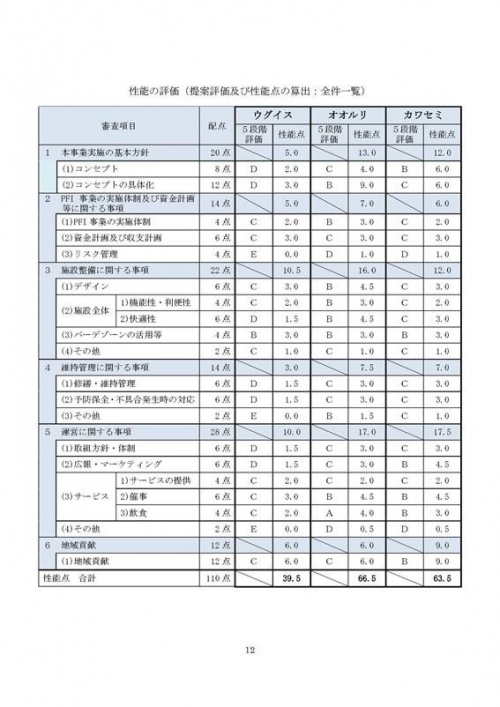以下、犬猫救済の輪さんブログ 動物愛護活動ドキュメンタリーから転載させていただきます:
元ブログ: http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-entry-7301.html
*******
拡散希望
☆茨城県動物指導センター管理飼養業務委託に関する提言書を提出しました。
大事な犬猫の命を扱う委託会社を選ぶのに
「審査内容については非公開とする」「結果についての異議申し立ては一切認めない」という茨城県
「茨城県動物保護収容及び飼養管理業務委託に係るプロポーザル」審査における透明性、
公平性確保に関する質問書について 県から回答
http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-entry-7304.html
茨城県知事
大井川和彦様
茨城県動物指導センター管理飼養業務委託に関する提言書
2020年5月13日
犬猫救済の輪 TNR日本動物福祉病院
代表 結 昭子
知事におかれては、ご公務繁多の折、私どもの質問書に対してご回答を頂き感謝いたします。その上で、今後の茨城県動物指導センター管理飼養業務委託先選定方法のあるべき方策について以下の通りご提言申し上げる次第です。県民本位の県政を推進されていかれるためにも、どうかその思いを受け止めていただき改善していただきますよう要望いたします。
ご検討のほどお願い申し上げます
(県民や登録譲渡団体等への情報公開)
(1)今回、公募型プロポーザル審査の形式をとられた理由のひとつとして、その会社が「感染症に対して適正な防疫措置がとれるかどうかなど柔軟に評価、選定したかったから」とご回答いただきました。登録譲渡団体としましても、センターに収容された迷子の愛犬愛猫を探す飼い主の立場からも感染症は大変心配な事項です。
不幸にして昨年 センターでパルボが発生し多くの犬が犠牲になったこともあり、今回、感染症対策に関してどのような提案が入札希望業者からなされたのかは、是非公表していただきたいことの一つです。当時の委託会社(今回委託が決定した会社と同一)がとった防疫措置に改良すべき点があったのではないかとの見方があることも事実ですので、なおさら公開されるべきであると考えます。感染症対応は一つの例にすぎません。せっかくプロポーザル方式をとられたのですから、あらゆる事項について、会社からの提案内容や審査に係る一連の事柄の情報公開はこのような点からも必須であると考えます。県の委託業務先の情報については今後、県民への情報公開を原則として制度改善を求めます。
(委託期間)
(2) 毎年入札が行われており、今回の契約期間も1年とあります。1年では会社が提案し受託した業務を持続的に県民に提供することに不安があります。
請負する側の会社からすれば、通常、安定的な経営が確保されなければ、1年後に落札できなかったら社員や経営の見通しが全く立ちません。
一方、審査する立場からすれば、その会社の実績とともに、少なくとも、安定的な経営が確保されているかどうかの実績や現状及び見通し等の経営方針を確認する必要があります。にもかかわらず、1年の委託期間であることに疑問を抱かざるを得ません。
形の上では1年毎に入札があり自由競争の形を呈していますが、実際には一社だけに長く安定的に仕事を与え続けることが暗黙の了解となっているのではないかと疑念が生じることにもなりかねません。
プロポーザル方式を採用する場合には、入札希望全社からの提案内容をより広く県民に公開し透明性を持った厳しい審査を行い、少なくとも3年程度の期間の委託とすべきだと考えます。
委託期間を3年以上とすると同時に、3年以上とするからには、審査項目はより詳細に多岐にわたることと、審査に係る全ての情報を公開することをご検討ください。
(委託会社の契約違反行為に対する罰則)
(3)委託会社に契約規約違反があれば契約を解除するとのご回答ですが、契約違反となる場合の具体的な事項について明確ではありません。それ以外にも契約解除をせざるを得ないケースとして、経営破たんや法令順守違反(コンプライアンス)等不測の事態はいつ起こるとも限りません。委託会社が、こうした契約違反を行った場合には、今後一定の期間は入札できない等の罰則規定を取り入れ厳格に対処すべきです。
(次点会社の扱い)
(4) その場合、次回入札がある年度末まで、動物の飼養管理者を不在にすることはできません。この様なケースを想定して、多くの自治体はプロポーザル方式では得点が次点であった会社が暫定的に残りの期間あるいはそれ以降も一定期間は委託を受けることになっています。こうした意味からも、落札した会社のみならず、次点の会社の情報(会社名、提案内容、審査における得点等)も公にしておかれるべきと考えます。受注会社が業務を続行できなくなった場合に、次点会社が速やかに業務を請け負うことを規定に入れていただく必要があります。
(審査会の構成員)
(5)審査会の委員を「公にする規定はありません」とのご回答ですが、他都市では、多くの場合、あらかじめ審査会委員の一覧がホームページに掲載されています。さらに今回の審査委員は県生活衛生課内とされていますが、多くの自治体ではメンバーには県職員だけはなく、外部の有識者が委嘱されて氏名所属共に公開されています。担当課は事務局となって、公平性に配慮しています。審査会委員メンバーの公表は、どれだけその選考審査が公平公正であったか、専門的な視点で行われていたのか等を知らしめるために、避けることはできません。外部有識者をはじめ県民の代表も含めて委員会を構成し、その審査会委員の名簿も公開されるべきです。
(指定管理者制度の活用)
(6)以上のことから、センター業務の委託化の手法については、本来は「指定管理者制度」を活用し運営されるべきです。全国的にも、県直営施設がある一方で、指定管理者制度を活用している自治体も少なくありません。あるいは、センターの一部の業務だけを委託することも考えられますが、その場合であっても、1年契約では、安定的な業務運営をすることは困難です。今後、他都市の先進事例を参考に、指定管理者制度での運営が可能となるよう検討ください。
(参考、他都市における事業者選定に関する情報公開の一例 )
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/chiikishisetsu/kamigo/0823morinoie.files/0003_20180710.pdf
最優秀提案者の選定にかかる審査は、学識経験者等で構成する審査委員会が担当し た。審査委員会の委員は、次の5名で構成される
氏名 所属・役職
委員長 宮本 和明 東京都市大学都市生活学部教授
委員 勝又 英明 東京都市大学工学部教授
委員 齋藤 真哉 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授
委員 原 悦子 アンダーソン・毛利・友常法律事務所弁護士
委員 廻 洋子 敬愛大学国際学部特任教授