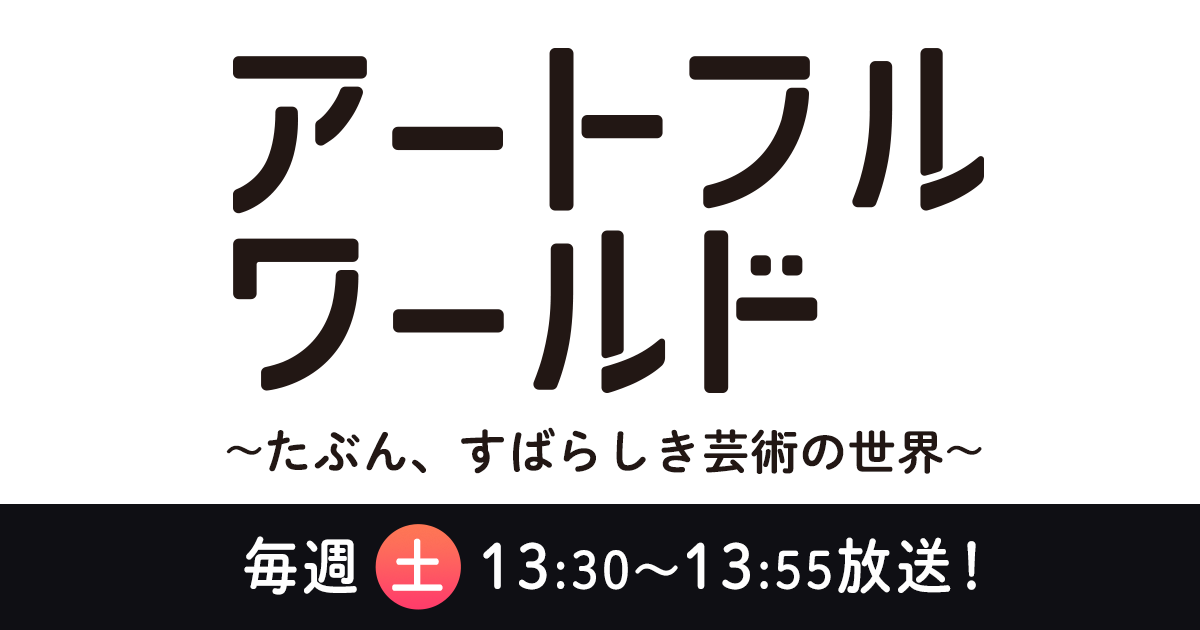前回、前編の内容を
書かせていただきましたが、
8月6日の再放送、ご覧いただきましたか?
今回は、その後半。
再放送は、8月10日(水)26:35~
です。ぜひ。

引き続き、リヒターさんの作品を
ご紹介していきます。
(素人目線での語りになりますこと、
ご容赦くださいませ)
具象と抽象画の間を描く
リヒターさんの作品は、
大きくは、「主観性を排出しての
絵画の可能性」
というテーマ、という事は、
前回お話しました。
今回の番組内容は、リヒターさんの
抽象絵画シリーズ
「アブストラクトペインティング」
からスタートしました。
「スキージ」というへらで、
重ねた絵の具を
削り取り、描いていきます。
その絵画について、
小関さんは、「蛇の皮」のようと、
イメージされました。
(余談ですが、私は竹の節にみえました )
)
のちに出てくる「8枚のガラス」
に象徴されるような、
「物事の見方はひとつじゃない」
に繋がっている気がしました。
リヒターさんは、「自然」という
言葉を大切にしていて、
作者が創造するのではなく、
イメージを「生成」するということ。
人間とは関係なしに、そこに
イメージがあらわれるというのはどういうこと
か、という考えで、描いています。
(「生成」という言葉は、生じること。
また,生じさせること、
という意味なんです。)
写真が生まれたことによって、
肖像画というものの他に、
「絵にしかできないもの」として、
抽象画の歴史が刻まれ、
時代時代によって、
様々な特徴が生まれてきました。
リヒターさんは、その中で、
絵画は、どういう風に作る事ができるのか、
絵画と写真の関係性を追及して
描き続きてきたそうです。
「3月」という作品は、
小関さんは、「デニムっぽい」
という印象。
(ここでも余談ですが、私は、
湖に浮かぶ船に見えました 。)
。)
そして、ほら、
抽象イメージなのに、
何かに見えてしまうという
作品たちなのです。
小関さんがいい質問をされました。
人に好かれるバランスが計算されているか?
ここで、案内していただいた
舛田さんが、
「シャイン」という言葉を。
意味は、 光 とか 現れ
という意味。
人間は、光をないと何も
観ることができない。
その光を、様々な表現で
あらわことができる可能性。
人の根源的な部分に触れているので、
いろんな方を魅了する。
間口を広く、深みもあるということ。
絵を普段見ない方も含めて、
間口を広くして、多くの方を受け入れる
作品でもあり、かつ、
深みもあるということ
なのでしょうか。
いろんな感性の方を、
包み込むような作風なのですね。
「8枚のガラス」
物事の見方はひとつじゃない。
ハーフミラーでつくられた作品。
焦点の合わせかたにより、
物の見方がかわってくる。
ガラス素材そのものや、
映り込むものを観る、
など、いろんな
見方ができる。
これは、「網膜の比喩」
となっていて、
あらゆるものの中で、
何に焦点をあてるか、
何を認識していくか、
という人間のメカニズムに
着目して作られたガラスの作品だそうです。
舞台は変わり、愛媛県の無人島 豊島へ。
ここには、2015年に製作した
ガラス作品が展示されいます
(毎年、期間限定公開です)。
「豊島のための14枚のガラス(無用に捧ぐ)」
観光・地域振興として、
アートが、地域の価値を
高める核になるのではないか、
という考えて
企画されたそうです。
観光を促進するというより、
あの場所へ一度、行ってみたいという、
「気持ち」を「惹き付ける」ものとし
てその企画は取り組まれたそうです。
リヒターさんもその企画に承諾し、
実際に豊島に出向き、
自然が残る島に感銘を受けました。
リヒターさんは、これを、
ガラスの立体作品
最後の作品として、作られました。
実際に見える瀬戸内海などの景色と
ガラスに映りこんでいる世界
(瀬戸内海だったり周りの景色だったり)、
つまり、「実像と虚像が入り乱れた世界」
を合わせてみていく、
というのが、豊島での作品の
楽しみ方だそうです。
天候、時間によって、
光が入り加減が違うので、
作品がまるで変っていくような。
好きな方は一日いて、
その変化を楽しまれるそう。
ここでも、まさに、光が
キーポイントなんですね。
こちらは、期間限定で
毎年一般公開されているそう。

 詳細はこちら。
詳細はこちら。
再び、館内。
暗い空間へ。。。
絵画と複製が向かい合わせに
展示されている。
「ビルケナウ」
これは、ナチスドイツの
強制収容所のこと。
絵画には、表面の下層
(表面からは見えない)
に絵が描かれている。
写真を絵画に描くフォトペインティングに
アブストラクトペインティングを
重ねている作品。
ガス室と火葬場のユダヤ人の組織
ゾンダーコマンドが
命をかけて撮影された写真を
フォトオペインティングで描き、
その上をアブストラクト
ペインティングで仕上げました。
こちらに描かれたもとの写真には、
実際に、ガス室で撮影され、
この時に起きていた
凄惨な風景がうつされています。
そして、それは、室内でしか
撮影できないもの、
撮影者は、ガス室で撮影用。
つまり、命をかけて
撮影したことになります。
大変に貴重な写真です。
当時の記録が残されていない中で、
ホロコースト(ドイツが(ナチスドイツ)を
ユダヤ人などに組織的に行った絶滅政策)
表すことは可能だろうかと
議論になっていた。
何か象徴化されてしまうような形では、
全てを語ることができないためでした。
(ここでは、アンネの日記が
その例に挙げられました。)
リヒターさんは、60年代から
描こうとしていましたが、
断念を繰り返し、
82歳の時にようやく
書き上げることができた作品です。
長年、自分がやらねばならないことと、
捉えていたことです。
この展示を体感した小関さんは、
空間に入ったときからダークな印象を
受けておられました。
その後、リヒターさんは、
2019年の作品を最後としていましたが、
昨年もドローイングで作品を残されいます。
小関さんは、
リヒターさんが、90歳になっても
絵を描く衝動が生まれてくるというところに、
感銘を受けておられたようです。
(小関さんも90歳でも
俳優さんを続けてくださいね!)
リヒターのとらえ方、視点、
光の要素だったり、
最終的に、自分自身に向かい合う
ようになったり、
空間全体を通して、
出会った自分の価値観を
感じられるところが
興味深いとのことでした。
多分、こんな風におっしゃっておられました、素敵。。
リヒターさんの作風や作品の
世界をかみ締めながらの、
丁寧な言葉選び。
さすがですね。
素敵な感想です
私の素人目線ですが、
具象と抽象は、
光と影のようにも
イメージできるのかなと思いました。
よく言われる表現ですが、
光を当てる事で影ができ、
影があるから光も際だつ。
その光と影の感じ方を、
観た人それぞれが
自分の中に落とし込むことで
生まれる
感性を味わえるのが、
リヒターさんの作品
なのかなと思いました。
こちらの番組は、
とても良質です。
BSフジさんで放送で、
再放送は、フジテレビ
関東ローカル放送です。
展覧会は、今後、秋には、
愛知県へ舞台は映ります。
ぜひ、全国放送での再放送
をお願いしたいです!