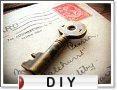糸立ての続きです!
昨日は、側板に糸立て部分の印を付けるところまで
書かせてもらいました。
ボビンもかけられる糸立て作ってみませんか!?Part1
板の裏表を確かめて、絶対に印の向きが間違ってないか
しつこいくらい確認してくださいね!

この位置で大丈夫かな~!?って思ったら
青の線端からの距離を測ってみてください。
側板に、糸立て部分と、天板・底板を仮置きしてみましょう!

右側が底になります。
大体こんな感じでOKです!
底になる部分をほんの1~2㎜ほど浮かすと
ガタが出にくくて良いかと思います。
側板にダボ穴と下穴を開けます。

まず、ダボ穴から
今回、8㎜の丸棒でビス跡を隠すようにダボを入れるので
錐は7.5㎜を使います。
8㎜で開けるとゆるゆるになるので0.5㎜小さいのにします。
天板と底板は、端からそれぞれ20㎜くらいのところで
板厚の真ん中にくるようにしてます
次に下穴を開けます。

木工用はすぐに折れてしまったので、
私は鉄工用の3.0㎜を使ってます。
木工教室の先生は、今回使用するビスの長さでは
チタン製の3.3㎜を使っています。
ビスの長さによって太さも変わるので
4.2とかも使う時があります。
下穴を開けるときは、
捨て板を下に敷くとバリが出にくいようです。
ドリルは、抜くときも回しっぱなしで抜きます。
捨て板を使用しないときは、
素早く抜き差しするとバリがでにくいようです。
糸立て部分に5~6㎜ほど穴を開けます。

私、ボール盤や、ドリルスタンドは持ってません。
基本全部手でしています。
錐はこれを使ってます。

スターエム 先三角ショートビット 4.5㎜
先がネジ式だと、止めたいところで止まらないようです。
私が持っているビットはほとんど先三角のものです。
糸立ての丸棒が5㎜なので、0.5㎜小さい4.5㎜のを使用します。
ビットの先にテープを巻いておくと、どの辺まで彫れたかの
目安になりますよ。
今回、6㎜くらいです。
ビットの先をブスッと挿して位置がずれないよう気を付けます。
全部穴を開けたら、ボンドを付けた棒を金づちでコンコン!
1本棒を入れるごとに直角を確認していきます。

めんどうですが、この作業は、きれいに棒を並べるため
重要です。
スコヤで2方向から確認して、曲がっているようでしたら
チョイチョイと手直しします。
ボンドは、入れた時にはみ出ないよう
先にちょこんとにしてくださいね。
後で塗装が乗らなくなることがあります。
糸立ての一番上のみ、75㎜の棒を入れて
残りは65㎜の棒を入れていきます。

ここが一番時間がかかりますが頑張って!!
片方の側板にボンドを付けて、
天板、底板、糸立て部分を付けて放置!
固まってしまうと外すのがやっかいなので
慎重に位置決め!
次にビス留めしますが
側板の下穴から更に木口にもう一度下穴を開けると丁寧です。
それから45㎜の細ビスでビス留めしました。

次に、もう片方の側板を留めるためボンドを付けます。
私は天板と側板の木口には、速乾ボンド
糸立て部分にはロングタイムのボンドを使ってます。
(2015年現在は全部速乾です。)

特に糸立て部分には、あまり付けすぎないようにしましょう。
自分でやってなんですが、写真はちょっと付けすぎです

今度は放置しないですぐに作業です。

板が反っているとどうしても糸立て部分がずれがちです。
底板と天板を留めた後、ずれていると思いますので
傷が付かないように気を付けてコンコンと叩いて
いい位置まで持ってきてから留めましょう。
まだこれで終わりではありません。
ビス跡を埋めるので8㎜の丸棒で隠します。
サンダーで丸棒を少し丸くします。

ボンドを軽くつけて打ち込みます。
この時、全部入らないようにした方がいいと思います。
丸棒をカットしますが、
いらない薄いポイントカードがあったら
傷防止のために使います。

私は、片刃のレザーソーでカットしてます。
前の写真にチラッと写っていますね。
(ゼットソーのライフソークラフト145が使いやすいです。)
出っ張りをサンダーで削ります。
#100を使っています。
ラワン丸棒よりも、檜があったら、ちょっと高いんですが
柔らかくて削りやすかったですよ。
20か所、全部埋め込みました。

#100で削ったので#180でもう一度サンダーがけします。
お好きな塗装をして完成です

36本もいらないんだけど!って方は
糸立ての下の段を棚にすると、ロックミシンの糸や
ボンヌママンの空き瓶など飾れますよ~!
アレンジして、お好きな大きさ、形で作ってみてくださいね^^
最後までお読みいただきありがとうございました!
糸立て、作ってみるよ~!
参考になったよ~!って思って下さった方
ポチッと押していただけると
更新の励みになります^^