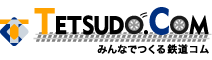急行伯耆という列車覚えていますか。
鳥取県西部の旧国名で(米子市、倉吉市、境港市、東伯郡、西伯郡、日野郡)が該当するそうで、昭和50年のダイヤ改正まで運転されていました。
この列車名を聞いて懐かしいなぁというかたは、間違いなく40代以上かな?笑
昭和49年の時刻表から 「急行伯耆・みまさか」時代
この列車は、私にとっては思い入れの深い列車でした。
と言いますのは、私の父親が鳥取出身で、私も幼少の頃から父親に連れられて田舎に行っていたこと、年の近い「いとこ」が居たことで、小学校高学年になってからは、長期の休みになるとこの列車を利用して遊びに行っていました。
特急に乗ると高いこと、急行ならば当時の家族割引を使うと乗車券だけ、それも5割引きで行けたのが理由ですが、急行だいせんではなく、なにゆえ伯耆だったのか、未だに不明ですが、当時は何も疑うこともなく、この列車を使っていました。
伯耆2号は、大阪~倉吉間の運転で、津山までは「急行みまさか2号」を津山からは「急行砂丘2号」を併結して運転される今から考えれば独り立ちできない?急行列車でした。
まぁ、線路容量の関係もあるのでしょうね。
結構な長大編成で、因美線などでは最後尾は1両なり2両がホームから外れるので、前から降りてくれと言いつつ、選択開閉できないので、ホームのないところのドアも開いていました。
他にも、津山で併結と解放を行うので20分近く停車する大盤振る舞い?であり。
駅のホームで大仙牛乳を買うのが楽しみだったりしました。
昭和51年時刻表から 急行みささ時代
それよりも何よりも、この列車10両ほど繋いでいたのですが、常に満員だったという印象がとても強いんです。
中国自動車道も開通しておらず、主たる交通機関は鉄道しか無かった時代であり、陰陽連絡の使命を持った路線として山陰本線よりも重要視されていた時代でした。
実際、中国自動車道が開通して、国鉄も大阪~津山間に高速バスを設定したら、播但線の利用者が殆ど高速バスに流れてしまい、「伯耆・みまさか」は減車を余儀なくされてしばらくして廃止されてしまいました。
これにショックを受けた国鉄はそれからしばらくは、国鉄バスの路線新設には躊躇したと言われています。
現在の姫新線時刻表
播磨新宮までは列車本数が多くて利用しやすいダイヤになっていますが、それ以降は1時間ですね。
また、現在の方が播磨新宮までの列車本数は増えていますが、優等列車もなくなり寂しい限りですね。
blogランキングに参加しています。
このblogが気に入っていただけましたら、クリックをお願いします。