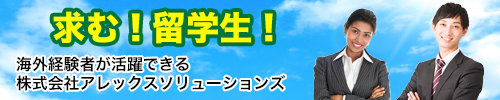弊社は今年20周年を迎えます。
10周年のときは、私の指揮で、保温マグなどを作成して社員に配りました。
作成したノベルティも、私の一存で、予算を立てて作りました。
そこから10年経った今回は、「20周年委員会」を作り、手上げ制で委員を募り、その委員が話し合いながら、行事の企画を進めています。
私からの注文は、20周年を祝うのは「これまでいっしょに頑張ってきた社員に感謝を伝える」会にしてほしいということ。
それを受けて「来賓やスペシャルゲストを呼んで何かしてもらうのは、社員にとって有益か?」「派手なパーティをするより、20周年手当のほうが現実的にうれしいんじゃない?」などと、作業班に分かれて議論を進めているようです。「OBの動画を取りたい」という話も上がってました。
10周年は代表の私が動いていたことが、20周年は社員の力で動かしている。
そこに当社の組織が成長していることを実感します。
20周年は2026年4月から2027年3月の期間です。
「社員への感謝」をキーワードに、その間に行う様々な行事を、どう創っていくか、今から楽しみです。