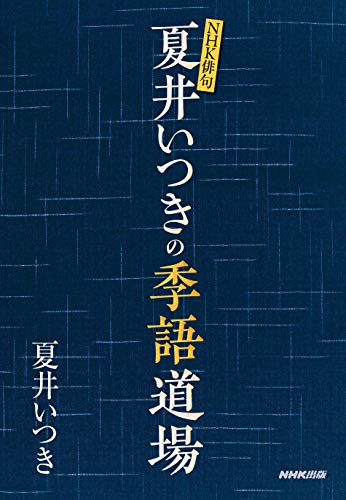昨日も書いた、国民文化祭へ向けて、
アクションを起こしました。
郵便局へ行って、国民文化祭向けの投稿料(詩・短歌・俳句・川柳)、各1,000円で合計4,000円を振り込みました。
これで、否応なく、どれもやらないといけないことになりました。笑
作品は、まだどれも出来ていませんが、基本的には〆切が6月下旬か、7月下旬なので、
いくつか候補案を今から用意しておこうかと思います。
まずは、以前、読んでいた、夏井いつきさんの『季語道場』を読み直してみます。
そこに書かれていた、いい句を作る推敲ポイントは五つ。
①季語は機能しているか。
季語の主役と脇役をはっきりさせる。
②意味やイメージが重複していないか。
「風が吹く」「夕日が沈む」「花が咲く」等は(略)「吹く」「沈む」「咲く」等の言葉が、捨て石のように機能する場合もあるが、まず省くこと。
③説明や感想になっていないか。
例えば「てるてる坊主さみしそう」は一種の感想です。てるてる坊主のどんな状態、どんな映像が、「さみしそう」だと思わせたのが、そこをきちんと描写すれば、句を読んだ人の脳内にも同じ映像が再生される。
④助動詞・助詞が正しく選ばれているか。
⑤語順・発想・叙述などを吟味しているか。
一瞬、何が? という疑問を投げかけ、最後でまとめる。
ささやかなオリジナリティーを手に入れるための工夫の一つに、立場を逆転させる発想があります。
上五で余る音数を処理して、中七下五で七五の調べを取り戻すのが定石です。
以上ですが、特に、この最後の類想を避けることが、大切だと思いました。
そこを夏井さんは以下のように述べられます。
「結局みんな同じ類想の土台にあるのだけれど、その類想を味方につけてオリジナリティーやリアリティーを手にした句が入選句の上位に入っています。」
「季語の本意を掴む、つまり季語の持っている情報は五感+連想力だと思っているんですが、その第六感を完全に腹に入れていないと類想につながってしまう。「こんな感じかな」程度で作ると類想で止まってしまうんです。この六感をきちんと消化していると、類想を抜けられる。」
「季語に実際に触れる以上の武器はありません。(略)見られないところや凍鶴の生活する背景を想像して周辺情報もたくさん取得して、それを糧にまた想像を広げる。」
などというのは、なるほどと納得させられます。
あとはこれらをどう血として、肉とするだけであろうかと思います。
では、ということで、
まず兼題が4つある、川柳を取り敢えず作句しました。
うーん、出るわ、出るわ、類想句が。笑
取り敢えず、メモしたものを寝かして、
また、川柳の入門書を熟読してから、推敲することにします。
まだまだ川柳は、交通完全の標語的なものしか出来ませんから。
こんな感じで、候補案を作成します。
俳句は、普段から十二音日記にメモしている句を、歳時記で季語を調べ直して、
本意を読み込み、きっちり当てはまる季語を入れ直すつもりです。
詩以外のの短詩型たちの中で、
俳句が一番、勉強する必要があって難しいんですが、
逆にしっかりやれば、僕のような素人でも、65点ぐらいの作品は出来るかな、と思っております。
ただ、入選するなら、85点ぐらいの作品を書かないといけないので、
それこそ類想との勝負ですし、現代詩的なアプローチを盛り込むことでオリジナリティを加えられるでしょうか。
川柳など、最初から類想との、真っ向勝負だと考えております。
短歌は、俳句のビジュアル感覚プラス、現代詩的なアプローチ、
異化効果かな、と考えます。
また、短詩型を作り続けることで、
自分の中に、近代詩的な五七調の日本語リズムを体得させたいと思っております。
欲張り作戦でしょうが、頑張ります。