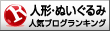僕は彼女を見つめていた。行きつけの小さな喫茶店のカウンターの中には、マスターとアルバイトの彼女の二人だけ。彼女は美大を出てからこの喫茶店でアルバイトをしている。まったく化粧っ気もなく、ひどくぞんざいな服装をして、宇宙の空虚を写し取ったような瞳をしている彼女を、僕は美しいと思った。僕はそんな彼女に、ただただ魅かれて、カウンター席で彼女の姿を見つめていた。そんな僕の視線を受けとめると、彼女は微笑んだ。その時だけ、宇宙の空虚を宿した目に光が灯った。「はい、これはサービス、いいでしょ、マスター。」時々そう言って、彼女は僕にコーヒーをもう一杯くれる。
僕はこの3月に大学を卒業して、定職にはつかず、中学の非常勤講師をしながら世に出る当てもない作曲をしている。稼ぎは少ないが、時間に余裕がある。父親の家で暮らしているので、今のところ生活に困ってはいない。彼女も父親を既に亡くし、今は童話作家をしている母親と二人暮らしだ。家ではひたすら絵を描いている。
僕はよく閉店まで店にねばって、仕事を終えた彼女と一緒に帰るようになった。駅まで二人で歩き、電車に乗り、彼女は5つ目の駅で降りる。時には駅前の安酒場で一緒に酒を飲むこともある。僕は彼女といると自分がよく分からなくなる。自分が男なのか女なのか、青年なのか少年なのか、時には自分が少女のように思えるときもある。
梅雨の終わりの雨の夜、「今日は雨の中を家まで歩いて帰りたい気分。付き合ってくれる。」、「それだと僕は家に帰れなくなる。」、「私の家に泊ればいい、客間に布団はあるから。」そう言われ、僕は彼女についていく。僕はいつも彼女の後を追いかけている。そして彼女は振り返りながら、僕を見ている。いつしか僕らはそんなポジションをとっている。雨の中、僕らは傘をさしながら歩く。
穏やかな雨で、空気がつややかで、かえって気持ちがいい。途中、自販機で缶ジュースを買い、閉まった商店のひさしの下で休憩する。「僕はあなたをどう思っているのか自分でもわからない。」、「それはわたしも同じ。わたしたち何なのかしらね。」と彼女は笑う。
雨の夜は美しかった。街路灯に照らし出される住宅地の庭木の緑のみずみずしさ、銀の糸のような雨、庭の植栽とどこか懐かしい土の匂い。やがて僕らは酔狂にも長い道のりを歩き通し、どこかビクトリア様式を思わせる古めかしい彼女の家にたどりついた。
遅い時間にも関わらず、彼女の母親の作った夕食を頂き、入浴までさせてもらい、彼女の父親が存命中に来客用に使っていた寝巻を借りて客間のベッドの上に一人座り込んでいた。母親は気さくな人だったが、どこか愁いを帯びたところがあり、それがこの古い洋館に馴染んでいた。年代物の半開きのカーテン、窓ガラスをつたう雨、年輪を重ねた屋敷、一瞬、僕はいつの時代にいるのだろうと思った。
ドアがノックされた。「どうぞ。」と言うと、白黒のチェックのパジャマを来た彼女が入って来た。彼女は窓辺に歩み寄り、カーテンを開けて、窓を開け放った。「こっちに来て、外を見てみない。」と言われ、僕も窓辺にいった。庭の常夜灯に照らされた静かな雨、濡れた庭木の葉と湿った土の匂い、静寂がそこにあった。
「雨の夜もまんざら捨てたものでもないでしょう。」風はわずかにあるものの、雨が吹き込むほどではない。「わたし、秋になったらパリに行くことにした。」そのことを聞いても、僕は意外とも思わなかった。この人は翼を持っている。遅かれ早かれ彼女が飛び立って、僕はただそれを見送るだろうことは予感していた。「やっぱり、行ってしまうんですね。」僕の言葉に無言で頷いた後、「それまでの間、わたしたちはどうしましょう。」彼女は少し悪戯っぽく微笑を浮かべていた。
静かな雨の夜のせいだろうか、僕は心が乱れることもなく自分の気持ちを話せた。「僕はあなたに魅かれています。それが、あなたを好きなのか、それともあなたになりたいのか、よく分かりません。ただ臆病なだけかもしれません。すみません。妙なことを言って。」彼女は何かに耳を澄ませているようなそぶりをしながら、「わたしもあなたに魅かれているのかもしれない。でも、どうしてか、わたしはあなたに臆病だ。」、「僕もそうです。」、「だからこのままでいたい。」、「僕もこのままでいたい。」、「でも、こんな雨の夜だから、ちょっとだけ、ほんの少しだけ勇気が出る。」彼女の唇がかすかに僕の唇に触れた。「これは忘れて頂戴。」、「ええ、忘れます。」そして彼女は客間を出て行った。
それから、僕らは相変わらず、変わりなく暮らした。梅雨が明け、夏雲が湧き、秋の風が吹く。その間、僕たちは喫茶店で時間をつぶしたり、酒場で酒を飲んだりしていた。そして、彼女の母親と二人だけで、パリに行く彼女を見送った。帰りの電車の中で、彼女の母親から、「あなたは娘を止められなかったのですか。」と言われた。「ええ、止められませんでした。」とだけ答えた。行かないで欲しいという気持ちがなかったと言ったら嘘になる。
でも、僕は気付いていた。僕と彼女はある一点でだけ異常に接近する公転周期を持った二つの彗星なのだ。だからその後には別々の空間へと飛んでいく。たとえ生まれ変わったとしても、同じように出会い、同じように別れていくのだろう。ただ、その一点でだけ、僕と彼女は微笑み合う。彼女が残したものは唯一つだけある。それは彼女が僕にくれた一冊の本、「この本はわたしの分身。」と彼女は言った。その後、その本は僕を何度も救ってくれた。あれから30年以上が過ぎて、僕は彼女が何処で、何をしているのか、知らない。
ブログランキングに参加しています。クリックしていただけると励みになります。