早いところでは
たぶん土曜日くらいから
いよいよ発売になります
PHPは『歴史街道』さんに
浅倉の短編が掲載されております。
歴史街道 2016年 09 月号 [雑誌]
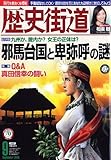
¥680
Amazon.co.jp
改めまして、タイトルを
『関ヶ原の丑三ッ』といいます。
すでになんとなく
お察し下さっている方も
いらっしゃいます通り、
まあいわばこちらは、
タイトル通りの
ある種の怪異譚であります。
――夏向きですね、確かに。
イラストもその辺り、
いい感じにおどろおどろしく、
書き起こして
いただいておりまして、
後編にどんなイラストが
仕上がってくるのか、
今から担当さんともども
大変楽しみにしていたりもします。
こんな場所からですが
挿画の須貝さん、
どうもありがとうございました。
さて同作は、つらつらと
ここ何年かで、
『フーガ』のシリーズとは
また別のくくりで、
書きためていたものの中の一つです。
今回は前後編に分けての
掲載となりますので、
この段階であまり踏み込んで
ぎりぎりネタバレに
なってしまってもいけないので、
適当なところで自粛しますが、
『黄蝶舞う』に収録した
一連の作品群を
自分でものすことができたことが、
やはり本作への着手に踏み切れた
きっかけというか、
一つの背景ではありました。
この『黄蝶舞う』については、
いずれ機会を改めて
少しここでも取り上げようかなと
思っていなくもないのですが、
なかなか似ているものの
見つかってはこない一冊には
仕上がっているのではないかと
自分では実はそれなりに
思っていたりもします。
まあとにかく
今日の記事の眼目は
『関ヶ原~』ということで。
さて、前回もご案内した通り、
自分が石田三成を書くとしたら
どういう描き方が
可能だろうかというのが、
着想の根幹ではありました。
もっとも今回の掲載分では
同人物は
まさに最後のページにしか
ほぼ登場しておりません。
さて、どんな話でしょう。
もっとも今回は前編だけですので、
この辺りで止めておくのが、
おそらくは慎みというやつでしょう。
書きたいけれど、自重します。
詳しい話はまた来月の今頃か
もう少し後に
とっておくことと致します。
さて本誌の方ですが、
今号の総力特集は、
『邪馬台国と卑弥呼の謎』だそうで。
記事の内容は僕もこれから、
じっくりと拝読させて
いただくところではありますが、
どうしたってこのテーマだと
僕なんかは個人的には手塚さんの
『火の鳥・黎明編』の
衝撃を思い出さずには
いられなかったりします。
改めて本当、
手塚さんの作品群に
もし子供の頃出会っていなければ、
自分でフィクションを
作ろうなどとは
思わなかっただろうなあ、と
まあそんな感慨を、
届いたばかりの見本誌の
裁断されたばかりの
独特の手触りを確かめながら、
思い起こしている
ところであったりします。
知らない時代の概略が
なんとなくわかったような
気分にさせてもらえたうえ、
その世界でしか
起こりえないようなドラマがある。
やはり手塚作品は、
自分がフィクションに求めるものの、
一つの理想型であるのだなあと思います。
さて、それから同誌の巻末に
いよいよ予告も載っていますが、
10月号の総力特集は、
そのものずばり『関ヶ原』だそうで。
もちろん拙作の後編も、
こちらに掲載される運びとなります。
いや、まだ校了には
なってはいないのだけれどね。
万が一にも事故のないよう頑張ります。
前後編ともども
お目に留まる機会がありましたら
大変幸甚でございます。
では最後に、冒頭でもリンクした
この前の記事に
コメント下さった方への御礼です。
まずlionheartsvegaさんへ。
僕が人気作家であるかどうかは
まあひとまず措いておくとして、
すったもんだがあることは、
さすがに認めざるを得ないようで。
その辺、記事に
出てしまってますからねえ。
まあ、あえてちょっとずつ
ほのめかしている部分も
正直なくはないですけれど。
いや本当、要らない苦労を
しているのかなあと
自分でも思わないでもありません。
そこら辺はでもまあ、
いずれ相手のあるお話ですので、
薄々察して戴く程度で
どうかよろしくお願い致したく。
『フーガ』をお読みいただいた方には、
なんとなく想像して
もらえているのではないかなとも
思ったりもしているのですが、
まあ、ああいう、
いわばテキストの外側に
出て行こうとする種類の
面白さを追求したい作品群なんで、
それをなんというか、
ご本人も楽しんでいただける方に
このテキストは
渡したいなあという、
いわば僕の側の
ある種の贅沢の結果だったりします。
でもねえ、自信もなくはないですよ。
ここまで某音楽系の雑誌の
編集長さんとかほか数人は、
面白く読んでくれたみたいだし。
――いや、でも。
やっぱりあまり
口さがなくならないうちに、
この辺でやめておくことにします。
いつか絶対ちゃんと本にします。
そのために妥協しないで、
ここまで粘ってきているし。
それからキャッチャーさんも
文藝お買い上げの御報告ほか、
いろいろとありがとうございます。
三谷さんのコメントは
たぶん僕も同じものを
読んでいるような気がします。
確かJRとかにおいてある、
『真田丸』のパンフに
掲載されていたものではなかったかと。
「敗者のドラマ」もまた、
僕の場合はやはり
手塚作品から多くを
教わったような気がしますね。
黎明編のナギやあるいは
猿田彦の最期のシーンは
今でも容易に思い出すことができます。
それはやはり、
子供心にもそれほど
強烈な印象だったと、
そういうことに違いない訳で。
むしろでも、そんな作用の本質は
実は時間の非情みたいな
部分だったりするのかもしれません。
一度起きてしまったことは
たとえどれほど望んでも
決して覆ることはない。
いや、似たような内容は
これまで発表した作品の中でも
幾度も書いてきたような気も
しないでもないのですけれど。
そういう意味でも
この前の回だったかの
『真田丸』のラスト間際の
兄弟のやりとりには痺れましたねえ。
それから今回の『関ヶ原~』も
楽しみに待っていて下さったようで、
本当に光栄でございます。
御期待に違わなければと、
重々願っているところです。
ところでここだけの話ですけれど、
もう一本、いつだったか
やはりここで
タイトルだけ出しておいた
『吉野詣』の方の
メイン・キャラクターの一人は
実は秀頼だったりしますので、
そちらもまた、
御披露目が叶います日を
期待していただければと存じます。
彼もまた史上に名を残す、
敗者の一人であることは、
疑いを差し挟む余地も
ないだろうかと思われますし。
そして最後に、
「武将といえば三成」は、
もちろん僕も知っております。
むしろ今回みたいな記事の
冒頭をこの一節で
始めてみようかなと、
実はひそかに思っていたくらいで、
先を越されてしまいました。
知らない方のために、
少しだけ紹介しておくと、
滋賀県が作った、三成のPRの
CMみたいなものがありまして。
はっきりいってこれ、頭沸いてます。
「武将といえば」ですぐ
出てくると思いますので、
ご興味のある方はお探しください。
おそらく腹筋つりますので、
適度に準備運動などされてから、
再生されることをおすすめ致します。
さて、決してマメではないのですけれど、
まあこんな感じで、
ここでは頂戴したコメントには、
お返事返させていただいておりますので、
もし皆様も気が向いたら、
何かおいていっていただけますと幸いです。
僕も今この時代に
まだ紙の書籍なり雑誌なりを
手に取って楽しんで下さっている方が
いったいどんな皆様なのか、
正直すごく知りたいなと
思っておったりもしますので。
機会がありましたら、
どうぞよろしくお願いします。