この方も相当どころではない重鎮である。
追憶の雨の日々~プレシャス・ソングス/ジョン・ケイル
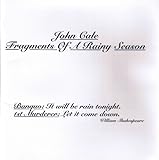
¥2,621
Amazon.co.jp
このケイルが何で有名かというと、
一般的には、
ヴェルヴェッツ・アンダーグラウンドの
オリジナル・メンバーだったという
点ではないかと思われる。
ヴェルヴェッツは基本
アメリカのバンドなのだが、
このケイルは英国はウェールズの出身なので、
やっぱり今のうちに、
ここで取り上げておくことにしたという次第。
なお、一応軽く説明しておくと、
ヴェルヴェッツ・アンダーグラウンドは
先年亡くなったルー・リードが
そのキャリアをまず最初に
スタートさせたバンドで、
何よりも、アンディ・ウォーホルが、
このバンドのデビューの全体を
プロデュースしたという点で有名である。
まあ実は僕は、ほぼ同じようなことを
以前某所で書いているのだが、
この彼らのデビュー盤、
ウォーホルに手による
バナナのイラストがメインのデザインで、
しかも初回プレスでは、
このバナナの皮が
剥けるような仕掛けに
なっていたのだという。
残念ながら、現物にお目にかかったことは、
この歳になるまで一度もない。
スティッキー・フィンガーズもまた然り。
一度見てみたいなとは
常々思っているのだけれど。
なお、同バンドの音楽については、
もちろん本企画がアメリカに渡ってから
改めてきちんと取り上げるつもりである。
ではジョン・ケイルの話へと戻ろう。
ケイルは結局、二枚のアルバムに
参加したのみで、
このヴェルヴェッツを脱退している。
だいたい69年頃の出来事だと思われる。
ルー・リードとの音楽的な
志向性にかかる対立が
原因だったとされているようだが、
詳しいことはよくわからない。
ただ、後年の二人の関係を鑑みると、
決して全然合わなかった訳でもなく、
むしろ逆なのではないかという気もする。
いずれにせよ、
ヴェルヴェッツを離れたケイルは
イギー・ポップやニコなどの作品の
プロデュースを手掛けたり、
あるいはミキサーとしての
スタジオ・ワークなどを経験した上で
71年、ソロ・アーティストとして、
コロンビアからデビューを果たす。
その後70~80年代を通じ、
ワーナーやアイランドなど、
レーベルを変えながらも、
コンスタントに作品を発表していく。
作風も非常に多岐にわたっており、
実験的な現代音楽有り、
映画のサウンド・トラック有り、
パンキッシュなロック有りと、
まさに変幻自在といえる。
要は才人なのだろう。
後年リードと再び組んで発表した
90年のSONGS FOR DORELLAなどは、
時に架空のロック・オペレッタと
形容されたりもしている。
そんなジャンルの括り、
ほかでは目にしたことがない。
この作品は、アンディ・ウォーホルの生涯を
音楽によっていわばシアトリカルに
たどりなおすことを
試みたという一枚である。
だから、芝居も脚本もないのに、
サウンド・トラックだけを仕上げた、
みたいな感じなのだと思う。
これが基本、ケイルとリードの
どちらから出てきた
アイディアだったのかまでは
わからないのだけれど、
もちろんどちらにとっても
このウォーホルが、
それぞれの生涯において
唯一無二の特別な存在であったことには
微塵も変わりはないはずである。
だからこういう発想を
作品として完成させるために、
再びタッグを組めてしまうところが、
この二人の不思議なところなのである。
そしてケイルはこの翌年91年に、
ヨーロッパを中心にした
ソロ・ツアーを敢行している。
これがまったくの、
いわば字義通りのソロだった。
つまりバック・バンドもコーラスも伴わず、
舞台に立つのは最初から最後まで
ケイル一人きりというステージで、
全曲が彼のピアノか、
あるいはギターによる
弾き語りによるものだったのである。
80年代半ば辺りからすでに、
セットリストの半分くらいを
このスタイルで演奏することも
試みていた模様ではあるのだが、
いわばそれを徹底した形である。
そしてこのツアーを、
当時ベルギーにあった
クレプスキュールという
インディーズ・レーベルが獲得し、
ライヴ・アルバムとして
発売したのが、今回掲げた
真っ白いジャケットの一枚なのである。
いいアルバムである。
収録曲が本当に、
佳曲揃いなのである。
しかも全20曲。お得です。
もちろんケイル本人が
そもそも意図していた
ことなのだろうけれど、
この形式で演奏されることにより、
余分といってはやや語弊があるが、
要は雑多な装飾を完璧なまでに
削ぎ落とされて、
基本彼の手による楽曲群が、
それこそ見事なまでに、
メロディーの美しさと、
リリクスの強靭さとを、
いわば真っ向から、
ぶつけてくるのである。
僕自身はこの方に関しては、
本作の後から、
幾つかの作品を手にしてみたという
程度なのだけれど、
刷り込み的な効果もあるのだろうが、
なんとなく、どの曲もどの曲も
この弾き語りヴァージョンの方が
格段にいいように
思えてきてしまうから不思議である。
ある意味ではこの試み、
後年のいわゆる
アンプラグド・ブームの
走りであったのかもしれない。
なお、このツアーは、翌92年には
日本にも招聘されており、
実は僕も東京公演に
足を運んでいたりする。
さて、今回表題にしたParis 1919には、
サビの箇所の、君は幽霊、という
強烈な一節のほかに、
もう一箇所、個人的に
ひどく心に残っているラインがある。
――Efficiency, efficiency they say.
効率、効率と彼らはいう。
三コーラス目の冒頭に
この一節が置かれている。
同曲はソロ・デビューから三枚目、
73年発表の同名のアルバムからの
ピック・アップである。
だから、僕にはもうこの時点から、
このケイルという人が、
今この21世紀の現代にも通じるような
ある種の歪みを看破し、
警鐘を鳴らしていたように思えて
仕方がないのである。
詳しいことは機会を譲ることにするけれど、
なるべくかいつまんでいうと、
実は誰もが今無自覚に日々、
平然と縛られているものこそが、
ひょっとしてこのEfficiencyという
奴なのではないかと
ひしひしと感じる場面が随時あるのである。
だからこそケイルは、この曲の最後を
自分は鉄のドラムをたたきながら、
意義を申し立てるためにやってきたのだと、
そんなことをいって
締めくくっているのではないかと
まあそんなふうに考えて
しまったりもするのである。
なお、昨年10月のリードの逝去に際し、
ケイルは深い悲しみを表明しつつ、
互いがどちらかを失うことなど
考えられなかったとの旨の
コメントを公にしている模様である。
だからやはり、
互いが互いに十分な敬意を抱くが故の、
この二人の衝突であり、
軋轢だったのであろうと、
今となってしまっては、改めて
そんなことを想像するのみである。
さて、本当は今回のテキストは
ここでこのまま締めてしまうのが、
やっぱり一番キレイだよなあ、とは
自分でも思わないでもないのだけれど、
今回はトリビア代わりに
どうしてもここで一緒に
書いておきたいことが
もう少しだけあったりする。
09年に僕が発表した小説に
今回御紹介のアルバムの
その邦題と同じタイトルの、
『追憶の雨の日々』という一冊がある。
もちろんこれは本作から拝借している。
――拝借してはいるのだが。
あるいはこれだけで
ひょっとして鋭い方は
お察しになって下さったかな、と
思わないでもないが。
まあ、では種明かしである。
実は、この作品にこの邦題をつけたのは
何を隠そう
この僕自身だったりする。
――雨の季節の欠片たち。
原題をそのまま訳せばこうなる。
最初はこれで行こうかとも
思わないでもなかったのだが、
でもなんだかちょっと違う気がして、
それからものすごく考えた。
このニュアンスを活かしつつ、
ケイルの作品っぽくしたい。
しかも、過去のカタログからの
ソング・ブック的な
意味合いも強いのだという部分も
どうにかしてわかるように出したい。
そんなことを悩んでいるうち、
「追憶」の一語が出てきて、
あの一節になったという次第。
だから、実のところあの本の
一番基本的なギミックというのは、
僕が自分でつけた邦題を引用し、
そのタイトルに沿って
小説を一本書き上げるという
たぶん後にも先にも
こんなことは僕以外の誰にも
できないであろう、という、
まあそもそもがそういう
ある種馬鹿馬鹿しい着想から
作品のきっかけが
出来上がっていたりするのである。
諸般の事情から、文庫化の際に
改題を提案され、
この時は頷いてしまったのだが、
もしいつか、どこかが再発に
手を挙げて下さるような機会があれば、
その時は、同書に関しては、
是が非でも、元のタイトルに
戻したいと考えている。
今世紀に入ってから
DVDというメディアが登場し
どこにしまってあったのか、
このツアーの映像がソフト化され、
その国内盤が某社から
リリースされた際に、
商品タイトルにこの
『追憶の雨の日々』というフレーズを
そのまま採用して
くれているのを見つけた時は、
少なからずどころではなく
嬉しく思ったものであります。
だからまあ、手前ミソっちゃあ
相当手前ミソかもしれないのだけれど、
でも、それでもこのアルバムは、
本当にこのジョン・ケイルという人の、
ソングライター、とりわけ
メロディーメイカーとしての
圧倒的な卓越性を、
まざまざと感じさせてくれる一枚である。
レノン/マッカートニーにも
比肩しうるような、数少ない
存在の一人だとまでいっていい。
そこは声を大にして断言しておく。
そして、こういう重要な作品を
本邦に紹介するという仕事に
自分自身が関われたことは、
多分に偶然のもたらしてくれた
幸運な結果であったとはいえ、
今になってみれば
本当に大きな一つの勲章だと
そう、心の底から思っているのである。