いや、あえていわれなくても
ほぼ自明のことであろう。
こんなとぼけた一文が
この人たちの歌のタイトルなのである。
まあたぶん、文脈からして
毛を剃るという方の
意味なんだろうとは思うのだけれど、
それでもやっぱり、
印象は似たようなものである。
Frank/Squeeze
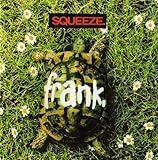
¥1,791
Amazon.co.jp
そもそもがこのジャケットからして、
相当どころではなくとぼけている。
よくわからないかもしれないけれど、
中央に映っているのはカメである。
本当に甲羅にアルバム・タイトルを書いて
撮影したのかどうかまでは
さすがに定かではないけれど。
さて、スクィーズというバンドである。
無理やりにでも搾り取る、といったような意味。
スクイズ・バントのスクイズと同じ。
このバンド、キャリアはそれなりに長いし、
作品数もそこそこに多いはずなのだが、
本邦でも十分に有名であるとは
さすがにちょっと
いいがたいのではないかと思われる。
実はこのバンドについては、以前
ヒューマン・リーグ(♯46)を
取り上げた時に一度だけ
ちらりとだが名前を出している。
彼らのツアーに参加していた
ジュルス・ホーランドなる人物が、
一時期このバンドのキーボーディスト
だったはずだという流れだったのだけれど、
この方、現在はどうやら一般的には
ジュールズと表記するようである。
本稿は一応手持ちの商品に準拠して、
このままジュルスでいくけれど、
まあブルーフォードとかゲイブリエルとか、
いろいろ変わってきちゃうからねえ。
もっとも、このスクィーズの中心人物は、
このジュルス・ホランドなる方ではなく、
グレン・ティルブルックと、
クリス・ディフォードなる二人である。
二人が二人ともフロントに出て
ギターなり鍵盤なりを弾きながら歌う。
楽曲も、代表作のほとんどが
この二人の共作によっている。
だからこの人たち、当時はよく、
イギリスが産んだ第二の
レノン&マッカートニーともいうべき
ソングライティング・チーム、
みたいな感じで
紹介されていたようにも記憶している。
――確かにわかる気はするのである。
とりわけHELP以前の
レノン&マッカートニーの作品群と、
このスクィーズの曲作りの方法論とは、
どこか共通しているような気がする。
決して奇を衒っている訳でもないけれど、
メロディーに重きを置いた
シンプルで斬新なフレーズを見つけて、
あるいは模索して作り出しては、
ぎりぎりバッティングしかねない
それらの幾つかを巧妙に組み合わせ、
中盤の展開できちんと繋ぎ、
一つのトラックとしてまとめ上げる。
この二人も、そういった方法論を
徹底しているような気が、
なんとなくだがするのである。
もちろんこういうのは所詮、
僕の個人的な
所感でしかないのだけれど。
さて、78年のデビュー当初には、
シーンの趨勢から、このスクィーズも、
パンク/ニューウェイヴの一バンドといった
押し出し方をされていた模様である。
だけど僕の知る限り、
この人たちの音楽は、
むしろパンクとはかけ離れている。
スタイリッシュと呼ぶには
やや泥臭い感触があるけれど、
それでも極めてポップなのである。
エイト・ビートのトラックをやっても、
なんとなくロックという言葉さえ
そぐわないような気がすることもある。
さらには、時折ジャズのジャンルの、
それもニューオリンズ・ジャズとか、
ラグタイム、あるいはブギウギなんて
呼ばれている辺りの音楽たちから
とりわけ軽快さみたいな部分を
巧妙に選んで抽出し、
自分たちのスタイルの中に消化して、
きちんと提示してくる辺りが、
非常に心地好かったりもする。
だから、この辺りの要素を担っていたのが
たぶんジュルス・ホランドという人で、
おそらくはスタカンにおける
ミック・タルボットのような
位置を占める存在なのだろうと、
勝手に思い込んでいたものだから、
この方のお姿を、こともあろうに
ヒューマン・リーグのステージの映像で
目にした時には
少なからず戸惑ってしまったのである。
ある意味では真逆な
音楽性みたいに思えたからね。
まあ、きっとなんでも出来るし、
なんにでも興味を持てる人なんでしょうね。
さて、今回のご紹介のトラックは
89年の8thアルバム
FRANKからのピックアップ。
この曲、シングル・カットされて
ちゃんとプロモーションされていたように
記憶していたのだけれど、
どうやらそんな事実もなかったようで、
単に同作の収録曲中で、
僕自身が一番気に入っていて
それで印象に残っていた模様である。
なお、彼らの音源で僕がちゃんと聴いているのは、
80年代の後半に発表された本作とその前作、
そしてこの二作に続いた
ライヴ・ベストともいうべき
A ROUND AND A BOUTという作品の
計三枚だけなのだけれど、
本当にいい曲を書き、
きちんとしたアルバムを仕上げてくる
優れたバンドだったと思っている。
本作も前作も、曲数がけっこう多いのに、
一曲一曲ちゃんとアプローチが違っていて、
一枚かけて退屈するという場面がなかった。
なかなかできることではないと思う。
She Doesn’t Have to Shaveは、
このすっとぼけたタイトルとは裏腹に、
あるいはその通りに、
たぶん結婚して一緒に暮らし始めた
若いと呼ばれていい時期を
ひょっとして、やや通り過ぎて
しまったのかもしれない男女の光景を、
半ばシニカルに、でも基本的には
とても暖かい眼差しで描写している。
開幕は、キッチンの前で
お皿を洗っていた彼女が、
突然泣き始めるというシーンである。
耳に手を当てて叫び声を上げる彼女に
主人公は黙って腕を回し、
好きなだけ泣けばいいんだよ、
みたいなことを口にする。
そして曲の後半になって不意に、
A fairy tale finishなんて一節が出てくる。
だからたぶんこれ、
恋愛の高揚感みたいなものを
すっかり通り越してしまって、
改めて二人して、例の日常というものに
向き合わなければならなくなっている
男女の光景を描き出した曲なのである。
何もかもが自分のせいに思えて
上手く眠れていないような時、
彼女がどうしてもたどり着いてしまう
沸点みたいなものがある。
だけどさ、彼女はもう毛を剃らなくていいし、
僕だってこのくらいの痛みで済んでる。
それはやっぱり、幸運なことなんだよ。
まあ多少の意訳はしているけれど、
大体のところは
こんな感じであろうかと思う。
さすがにティーンネイジャー向けとは、
つまりポップ・ミュージックの
メインストリームに乗っかってくるとは、
到底いいがたい種類のこんなリリクスが、
軽快だけれど、微妙にセンチメンタルな
メロディーラインに載せられている。
やっぱりなかなかの佳曲だと思う。
このほか、アルバムのオープニングに相応しい、
最初のシングルにもなっている
If It’s Loveなんてのも、
展開が非常に気が利いていて、
まさに彼ららしいポップ・チューンだといえよう。
かと思えば、まるっきり4ビートの、
Slaughtered, Gutted and Heartbrokenとか、
あるいはホランドによるDr. Jazzなんて
ラグタイムのパロディみたいな曲もある。
振り幅がそこそこ大きいのに、
どれもがこのバンドならではの曲である。
こういうのをたぶん、個性的というのだろう。
だから、ちょっと誉め過ぎに
なってしまうかもしれないけれど、
あるいはもしビートルズが解散せずに、
初期のテイストを維持したままずっと
80年代も活動していたのだとしたら、
ひょっとして彼らみたいな音を
やっていたのかもしれないな、と、
ちょっとだけ思えてきてしまうのである。
なお、余談ながら本作が、
ホランドが参加していた
最後のアルバムになったはずである。
ではトリビア、というか、
これは本編の続きみたいなものかな。
前回前々回とここで取り上げてきたように、
ニック・ロウがコステロの才能を見抜いて、
デビューを後押しした場合と少し似ていて、
やっぱりお互いに目指している音楽に
共通する要素がある場合、
感じ合うものが生じてくることは
やはりしばしばあるようで、
このスクィーズに関しては、
今度はそのコステロが
このバンドにすっかり惚れ込んで、
81年の4thアルバム、EAST SIDE STORYの
プロデュースを一部手がけていたりもする。
そして、同作所収のTemptedなるトラックが、
アメリカにおける、現在に至るまでの
彼らの代表曲となっている。
もっともチャート的にはこのFRANKの前作、
7th アルバムBABYLON AND ON所収の
Hourglassの方が少なからず上で、
15位という彼らの最高位を
記録してはいるのだけれど、
その後のサントラやCMへの起用などで、
今ではこのTemptedの方が
巷では格段に有名である模様。
80’sを標榜したコンピレーションに
同バンドの曲から採用されるのは
もっぱらこちらの曲である。
ただしこのトラックのリード・ヴォーカルは
グレンとクリスのどちらでも
なかったりするのだけれど。
ちなみに、上のBABYLON AND ON、
個人的にあの頃本当によく聴いたのだけれど、
何故かCDを買いなおしそびれたまま、
今に至ってしまっている作品の一つだったりする。
あ、FRANKは最初からCDで買ったのね。
そしてさらにちなみに、
実は次回とその次とは、
そういう今手元にはないアルバムからの
ピック・アップになる予定である。
さて、ちゃんと書けるだろうか。
ま、なんとかなるでしょう。